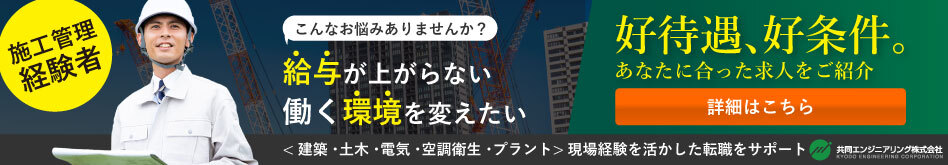目次
2級建築施工管理技士試験の合格率

2級建築施工管理技士とは、建設現場で施工計画の作成や現場の工程管理、安全管理、品質管理を行うための国家資格です。資格を取得するには、第一次検定と第二次検定の両方に合格する必要があります。
ここからは、試験を実施する一般財団法人 建設業振興基金の公表データから、第一次検定と第二次検定の合格率について解説します。
出典:一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級建築施工管理技術検定 結果表」
第一次検定の合格率・合格ライン
令和6年度の第一次検定合格率は、約50%です。例年35〜50%前後で合格率が推移しています。
2級建築施工管理技士の試験制度は令和6年度(2024年度)に改正され、第一次検定は試験実施年度に満17歳以上であれば誰でも受検可能になりました。
試験問題は建築学等、施工管理法、法規の科目から四肢択一か五肢択一で出題されます。解答はマークシート方式で、60%以上の得点が合格ラインです。試験合格後に国土交通省に申請すると、2級建築施工管理技士補の合格証明書の交付を受けられます。
合格基準や試験内容は年度ごとに変更されるため、事前に「受検の手引き」を確認してください。
出典:一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 受検の手引き」
第二次検定の合格率・合格ライン
令和6年度の第二次検定合格率は、約40%です。例年25〜50%前後で合格率が推移しています。
第二次検定は、第一次検定に合格していないと受検できません。しかし、1級建築施工管理技術検定の第一次検定や一級建築士試験に合格している場合は、同等の資格とみなされて受検可能です。そのほか、改正後は第二次検定を受検する際に次の実務経験が必要になりました。
・2級建築施工管理技術検定の第一次検定合格後、3年以上の実務経験
・1級建築施工管理技術検定の第一次検定合格後、1年以上の実務経験
・一級建築士試験合格後、1年以上の実務経験
令和6年度改正前の旧受検資格は令和10年度まで適用されるため、詳しくは「受検の手引き」を確認してください。
第二次検定の試験問題は、施工管理法、躯体施工管理法、仕上施工管理法の科目から出題されます。選択問題と記述式があり、60%以上の得点が合格ラインです。試験に合格すると、2級建築施工管理技士の合格証明書が国土交通大臣から交付されます。
2級建築施工管理技士を取得する難易度
2級建築施工管理技士の資格取得の難易度は、総合的にみてやや高めです。ただし、第一次検定はそれほど難しくなく、専門的な教育を受けていなくてもしっかり試験勉強すれば合格できるレベルといえます。
一方、第二次検定では記述式の能力試験があり、難易度があがります。仕事で経験を積みながら長期的な学習計画を立てて取り組みましょう。
2級建築施工管理技士を取得するメリット

2級建築施工管理技士は、現場で必要とされる重要な資格です。資格者の需要は高く、以下のさまざまなメリットが期待できます。
・施工管理計画の作成や工程管理を担当する責任ある立場で働ける
・実務経験を積めば主任技術者になれる
・資格手当や昇給で収入が増やせる
・就職や転職で有利に働く
・1級建築施工管理技士試験の受検資格が得られて、キャリアアップにつながる
第二次検定に落ちても、第一次検定に合格していれば「施工管理技士補」の資格が付与されます。技士補でも監理技術者の補佐として現場で働けて、仕事の幅が広がります。
施工管理技士補の詳細については、以下の関連記事で紹介しています。あわせて参考にしてください。
「【1級・2級】施工管理技士補とは?受検資格と試験内容について」
2級建築施工管理技士試験に合格するポイント

ここからは、学習方法や試験対策のポイントをみていきましょう。試験の難易度はやや高めでも、しっかり対策すれば合格を目指せます。
2級建築施工管理技士試験に合格するポイントは、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせて学習計画を立てる際の参考にしてください。
受検まで100~300時間の勉強時間を確保する
試験前の学習時間の目安は、100~300時間で、合格には十分な勉強時間の確保が重要です。試験日から逆算して、自分がどれくらい時間を確保できるか確認しておきましょう。
働きながら試験に臨む場合は、限られた時間の中で効率良く学ぶ必要があります。平日1日3時間、週15時間の勉強時間を確保できるなら、150時間勉強するためには2.5か月必要だと考えてください。
2級建築施工管理技士試験は、前期と後期で年2回開催されます。試験日を確認して、早めに学習スケジュールを立てましょう。
丸暗記ではなく内容を理解する
勉強のスケジュールを立てたら、次に大切なのがテキスト選びです。2級建築施工管理技士試験に関するテキストは、数多く出版されています。そのなかでも、過去問に特化したものがおすすめです。過去問の解説や説明をわかりやすく解説しているテキストを選べば、効率良く勉強できます。
また、勉強するときには問題を解きっぱなしにするのではなく、解説も読んで理解を深めることも重要です。解説を読んで理屈や要点を把握すると、知識の定着を図れます。
過去問に取り組む
試験は過去問からの出題が多いため、一通りテキストを読み込んで知識が身についたら、積極的に過去問に取り組みましょう。過去問を解くと出題傾向がわかり、対策しやすくなります。
繰り返し過去問を解き、採点と復習を繰り返して問題に慣れるのが合格への早道です。試験直前は時間を計りながら模擬試験に取り組み、当日に備えましょう。
第二次検定の記述対策は実際に書いて覚える
第二次検定の記述対策では、答案を記述しながら覚える方法が最も効果的です。記述問題は、テキストを暗記するだけでは合格できません。
問題に対する回答を自分なりにまとめて、文章で伝えるよう訓練しましょう。第三者に解答を添削してもらうか、添削の実例集を見るのも勉強になります。
講習や通信講座も活用する
最近はYouTubeをはじめとした動画でも有益な学習が可能です。無料で勉強できるので、過去問の解説動画は非常に効率良く学習できます。
体系的にしっかり学びたい場合は、2級建築施工管理技士試験対策をしているスクール講習や通信講座の受講がおすすめです。
講習・通信講座はポイントを細分化した動画で続けやすく、効果的に学習できます。また、実務経験が少ない方は、第二次検定の対策として実務経験を積んでおくことが大切です。
まとめ

2級建築施工管理技士の難易度はやや高めですが、きちんと勉強すれば取得できる資格です。取得するとキャリアアップのための実務経験を積めるようになり、1級建築施工管理技士資格を取得するのも夢ではなくなります。1級建築施工管理技士資格を取得すると、年収1,000万も目指せる上に、より大きなやりがいを感じられる業務に携われます。
BREXA Engineeringでは各分野の施工管理技士取得をサポートしており、未経験から建設業界での活躍を目指せます。教育制度が充実していて、継続して社員向け研修や資格取得の講座を受講可能です。
建設現場で着実に実務経験を積んでいけば、キャリアアップや年収アップも期待できます。施工管理の仕事に興味がある方は、どうぞお気軽にご応募ください。