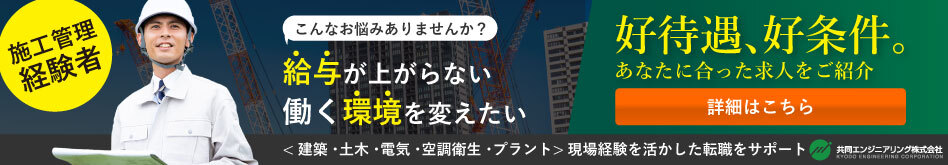目次
施工管理技士補とは技術検定制度の変更で新設された資格
施工管理技士補は、2021年の施工管理技術検定の見直しにより新設された称号です。まずは、技術検定制度の変更点について説明します。
変更前の技術検定制度
技術検定制度の変更前は、検定の名称が「学科試験」「実地試験」となっていました。
また、実地試験が不合格の場合は学科試験合格の翌年〜2年間以内の学科試験が免除となります。ただし、2回不合格になると、学科試験からの再受検が必要です。
変更後の技術検定制度
施工管理技士補の称号が付与されることになりました。
さらに、施工管理技士補取得後の一次試験は、期間・不合格の回数を問わず免除となります。
変更点をまとめると、下記の通りです。
検定の名称
旧制度 | 新制度 |
学科試験・実地試験 | 一次検定・二次検定 |
免除期間
旧制度 | 新制度 |
学科試験合格の翌年~2年以内 | 一次検定合格後、無期限 |
一次検定(実地試験)合格後の再受検
旧制度 | 新制度 |
2回不合格となった場合は、実地試験から再受検となる | 不合格の回数に関わらず、二次検定から再受検できる |
一次検定(実地試験)合格時に付与されるもの
旧制度 | 新制度 |
なし | 1級施工管理技士補・2級施工管理技士補 |
施工管理技士補が新設された理由

建設業界における人材不足や監理技術者の減少は、業界全体の課題となっています。これらの問題を解決するために、施工管理技士補が新設されました。ここでは、資格が生まれた背景や、建設業界にどのような変化をもたらすのか詳しく解説します。
理由1|施工管理技士が不足しているため
自然災害によるインフラの復旧や、老朽化による整備など、建設業界を取り巻く環境は大きく変化しています。しかし、これらのニーズに対応できる施工管理技士が少なく、特に経験豊富なベテラン技術者の退職によって、人材不足が深刻化しています。
また、若年層の入職も減少傾向にあり、現場の技術継承が課題です。そこで施工管理技士補制度が新設され、新たな人材育成と現場での技術向上が図られるようになりました。現場の人員確保と技術力を強化することで、建設業界の持続的な発展につながるでしょう。
理由2|新・担い手3法の影響によるもの
施工管理技士補の新設は、2019年に国土交通省が公表した「新・担い手3法」の具体的な施策のひとつです。建設業界の慢性的な人手不足を解決するために、給与体系の見直しや福利厚生の改善など、働きやすい環境を整備することを目的として法改正が行われました。
従来の施工管理技士の試験は、受検資格が厳しく、建設業界への新規参入が難しい状況でした。そのため、施工管理技士補制度を設けることで、若年層や経験の浅い人材が段階的にステップアップできる仕組みができたのです。
つまり、「新・担い手3法」の施策は、建設現場の人材確保や後継者育成に重要な役割を果たしているといえます。
理由3|監理技術者の配置義務を緩和するため

1級建築施工管理技士補が新設された理由として、監理技術者の業務効率化と人材不足の解消があげられます。従来の制度では、建設現場には必ず専任の監理技術者を配置することが義務付けられていたからです。
そのため、複数の現場を抱える建設会社では、監理技術者の需要と供給が追いつかず、人材確保が困難となるケースがありました。
しかし、制度改正が行われたことで、監理技術者の配置義務が緩和され、1級建築施工管理技士補がいる現場であれば、監理技術者は複数の現場を兼務することが可能になったのです。
また、1級建築施工管理技士補を現場に配置することにより、監理技術者の負担軽減にもつながります。監理技術者と施工管理技士補が協力することで、より効率的で質の高い施工管理が可能です。
1級施工管理技士補と2級施工管理技士補の違い

1級施工管理技士補と2級施工管理技士補の違いは、大きく分けて下記の3点です。
・担当できる業務内容
・経営事項審査加点の条件
・取得できる年齢
具体的にどのような違いがあるのか、それぞれの違いを詳しく解説します。
1級施工管理技士補
<担当できる業務内容>
1級施工管理技士補は、監理技術者補佐になることができます。
例えば、大規模工事における下記の業務を担当できるようになります。
・施工計画の作成
・工程管理
・品質管理
・予算の管理
・下請け業者への指導監督
<経審加点の条件>
1級施工管理技士補は経営事項審査の加点対象です。ただし、技士補の資格取得だけでなく、主任技術者要件を満たす必要があります。
<取得できる年齢>
2級施工管理技士補の取得後、1級施工管理技士補の一次検定に合格するまでは、最短で6年〜7年程度かかります。取得できるのは、24歳〜25歳になるでしょう(※)。
※18歳で2級施工管理技士補を取得し、実務経験(卒業後4年半)を積んでから2級施工管理技士を合格、その後1級施工管理技士の一次検定を合格した場合
ただし、建設業法の次回改正により、受検資格の緩和が見込まれています。(2023年時点)令和6年度の試験から、19歳以上であれば学歴・実務経験問わず受検できるようになるとの改正案が出されているのです。
そのため、将来的には最短19歳で1級施工管理技士補を取得できる見込みです。
2級施工管理技士補
<担当できる業務>
2級施工管理技士補は、1級施工管理技士補とは異なり、補佐として活動できるわけではないので、業務範囲は増えません。
<経審加点の条件>
2級施工管理技士補の場合、CPD(施工管理技士・施工管理技士補対象の継続教育制度)で取得した単位数に応じて加算されます。
<取得できる年齢>
2級施工管理技士補は満17歳以上であれば取得できるため、高校在学中の学生も取得可能です。
施工管理技士補を取得するメリット
次に、施工管理技士の資格取得を目指している人へ向けて、施工管理技士補を取得するメリットについてご紹介します。
一次検定だけで資格を取得できる
施工管理技士補が新設されたことで、一次検定の合格だけで資格が得られるようになりました。
また、一次検定の合格後は期間を問わず、何度でも二次検定に挑戦できます。施工管理の資格取得に向けてモチベーションを維持できる点もメリットといえるでしょう。
中小企業で重宝される
施工管理技士補は、条件によって経営事項審査における加点対象となります。経営事項審査は公共工事の競争入札に必要で、加点が多いほど信頼と実績を認められます。
そのため、特に中小企業で重宝されます。勤務先に貢献できる点も、メリットのひとつです。
就職・転職時のアピールになる
施工管理技士補は国家資格です。有資格者は、そのスキルを公的に証明することができます。
そのため、施工管理技士補の有資格者は就職・転職で有利になることがあります。特に建設会社や工務店では1級(2級)施工管理技士補の有資格者であることを応募条件としている場合も多く、勤務先の選択肢を広げられる点でもメリットです。
施工管理技士(一次検定)の受検資格・試験内容・難易度

次に、それぞれの受検資格や試験内容、難易度について解説します。
施工管理技士(一次検定)の受検資格
一次検定では、土木、建築などの7種目から選択し、合格する必要があります。2級は満17歳以上であれば学生も対象です。
なお、令和6年度より建築施工管理技士の受検資格が変更となり、1級を受検する年度末の時点で19歳以上であれば誰でも受検可能になりました。また、一次検定に合格すれば、学歴や実務経験不要で1級・2級施工管理技士補の資格を取得できます。
ただし、「施工管理技士」の資格を取得するには、二次検定に合格する必要があります。新旧いずれの制度においても実務経験は必須です。
施工管理技士(一次検定)の試験内容
2級の一次検定では施工管理の基礎知識が出題されます。応用能力問題は全4問で、1問につき2解答の正答が必要です。出題数は50問のうち、40問を選択して解答します。
1級の一次検定では、監理技術者補佐としての知識があるかが問われます。応用能力問題は全6問で、2級と同様、1問に2解答の正答が必要です。出題数は82問のうち、72問を選択して解答します。
ともに制度変更前の学科試験をベースに、能力問題が追加されています。
施工管理技士補(一次検定)の合格率と難易度
建築施工管理技術検定を例に、合格率と難易度をみていきましょう。2023年における一次検定合格率を見ると、1級、2級のどちらも40%〜50%程度といえます。
【一次検定の合格率】(2023年度)
1級建築施工管理技士 | 2級建築施工管理技士 |
41.6% | 49.4% |
出典:
総合資格学院「1級建築施工管理技術検定の合格率について」
総合資格学院「2級建築施工管理技術検定の合格率について」
難易度はやや難しい〜普通程度ですが、一夜漬けでは合格は難しいと考えられます。特に1級では出題範囲が広いため、効率的に勉強することが大切です。過去問を中心に、計画的に知識を身に付けていきましょう。
この記事をお読みの方におすすめの求人
「未経験で施工管理になりたい」「働きやすい職場に転職したい」といった方は、共同エンジニアリングがおすすめです。共同エンジニアリングでは、施工管理未経験でも安心して働ける環境を整備しています。
「キャリア形成」「適正配属」「社内情報連携」の3つの項目を軸として活動するキャリアサポート課が、面談や社内研修を通じて、一人ひとりがより幸せな未来、充実したキャリアを築くための支援をしています。
スタートアップ研修や専門技術研修(建設業界に関する基礎知識)、CAD研修など、研修制度も充実していますので、未経験で施工管理に挑戦したい方は、ぜひご相談ください。
まとめ
施工管理技士補は、1級を取得すれば監理技術者補佐として働くことができます。一次検定を合格すれば何度でも、いつでも二次検定に挑戦できるため、資格取得のモチベーションも維持できるでしょう。
共同エンジニアリングでは、未経験者・経験者を問わず、施工管理職を募集しています。資格取得支援研修や手当も充実しているため、施工管理としてスキルを磨きつつキャリアを築きたい方はぜひ下記から詳細をご確認ください。