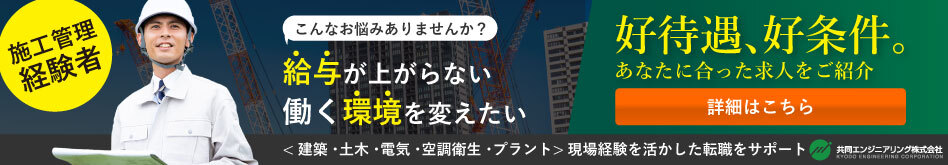目次
「すごい」といわれる1級建築施工管理技士の平均年収は?
厚生労働省の職業情報提供サイト(日本版O-NET)によると、1級建築施工管理技士の平均年収は約632万円です。全業種の平均年収よりも高く、取得すれば年収アップが見込めるでしょう。
また、年収632万円という数字は関連業種の土木施工管理技士や送電線工事などと比べて、やや高めの水準です。土木施工管理技士の平均年収は約603万円、送電線工事は約550万円となっています。労働時間や平均年齢などについては、大きな差はありません。
また、2級建築施工管理技士から1級建築施工管理技士になると、担当できる仕事の範囲が広がります。2級だと主任技術者としてしか配置できませんが、1級だとそれに加えて監理技術者としての配置も可能です。規模の大きな現場も担当できるようになるため、年収アップにつながります。
出典:
職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tag「建築施工管理技術者 - 職業詳細」
職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tag「土木施工管理技術者 - 職業詳細」
職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tag「送電線工事 - 職業詳細」
1級建築施工管理技士が「すごい」といわれる理由

1級建築施工管理技士の資格を取得しようと考えている方の中には、なぜ「すごい」といわれるのか気になっている方も多いでしょう。その理由は、主に担当する工事の規模や資格の難易度などが関係しています。ここでは、1級建築施工管理技士が「すごい」といわれる理由について詳しく解説します。
大規模工事の責任者になれるため
1級建築施工管理技士の資格を保有している方が責任者として担当する現場は大規模工事が中心です。大型商業施設やオフィスビルなどの高層ビルから公共施設まで幅広く担当できます。
1級建築施工管理技士の資格を保有していると建築工事の現場で「監理技術者」になれるためです。監理技術者というのは建築現場の責任者のことで、一定規模以上の元請工事を受注する業者に対して、現場への配置が法律上義務づけられています。
具体的には外注総額5,000万円以上の元請工事を受注する場合が対象です。また、建築工事一式を受注する場合にも、8,000万円以上なら監理技術者を配置しなければなりません。
そのため、1級建築施工管理技士の有資格者は、大規模工事の責任者として活躍できます。地域のランドマークになるような建物の建築工事を担当することもあり、「すごい」といわれることが多いのです。
1級建築施工管理技士は、巨大な建物の建築工事を成功に導く重要な役割を担っています。現場全体の進行管理・品質管理・安全管理・原価管理などを担当するのがメインの仕事です。
仕事そのものは中小規模の現場を担当する場合でも同じですが、現場の規模に比例して協力会社の数が増えます。現場で働く職人や作業員の人数も増えていくため、中小規模の現場とはその点が変わってきます。
したがって、現場で働く多くの作業員が一体感を持って業務に取り組めるようにするためには、高いマネジメント能力やコミュニケーション能力が求められます。さらに、経験に基づいた判断力や指導力も必要となるでしょう。
専門スキルはもちろんのこと、マネジメントスキルなども十分に備わっている方でないと務まりません。こうしたスキルの高さ・責任感・統率力などが建築業界や他業界でも高く評価されています。
資格取得の難易度が高いため
1級建築施工管理技士の試験は、学科試験の第一次検定と実地試験の第二次検定に分かれています。ここ数年の合格率はいずれも40%前後で推移していますが、第一次検定の方が少し高めです。
| 1級建築施工管理技士 | 2級建築施工管理技士 | ||
| 第一次検定 | 第二次検定 | 第一次検定 | 第二次検定 |
令和3年度 | 36.0% | 52.4% | 49.0% | 52.9 % |
令和4年度 | 46.8 % | 45.2 % | 42.3 % | 53.1 % |
令和5年度 | 41.6 % | 45.2 % | 49.4 % | 32.0 % |
出典:
総合資格学院「1級建築施工管理技術検定の合格率について」
総合資格学院「2級建築施工管理技術検定の合格率について」
2級建築施工管理技士の資格も、1級と同様に第一次検定と第二次検定に分かれています。ここ数年の合格率は、第一次検定が40%台、第二次検定が50%前後で令和5年度だけ低めです。合格率だけを見れば、1級も2級もそれほど違いはありません。難易度もあまり差がないように捉えてしまう方もいるでしょう。
しかし、決して1級建築施工管理技士の資格が簡単というわけではありません。1級と2級では受験者全体のレベルが大きく違います。
1級建築施工管理技士を受験する人は、2級を取得済みの人が多いです。知識や経験なども2級の受験者と比べて豊富な傾向にあります。そのため、ある程度土台ができたうえで受験に臨む人が多いというわけです。
ただし、そのぶん2級と同じような感覚で挑んで合格するのは難しいといえます。1級の出題範囲は広く、深く掘り下げた内容の出題が多いです。表面的な理解だけでは合格できないでしょう。
1級の出題の中でも二次検定の「経験記述」は最難関とされています。自分が実際に業務で経験した工事について記述するというもので、かなり具体的に詳しく書かなければなりません。具体性の低い内容の解答では合格できるだけの点数を取るのは難しいでしょう。
経験が少ない方だと、内容が薄くなってしまうこともあります。そのため、テキストで勉強するのに加えて現場での経験も必要です。
また、具体性の高い内容でも、本人の感想のような主観的な内容で書くのもあまり高得点にはつながりません。具体的でなおかつ客観的な視点で書くことが重要です。
経験記述で高得点を取るには、これまで自分が担当した工事について頭の中でよく整理しておく必要があります。
十分な経験を積んでいながらも、経験記述で自分の経験を上手く書くことができず、合格を逃してしまう方も多いです。
施工管理の仕事は時期によって休みが減ってしまったり残業も増えてしまったりすることもあるため、勉強時間の確保も難しいのが実情です。スキマ時間を上手く活用するなどして、コツコツ勉強しなければなりません。
年収1000万円も目指せるため

1級建築施工管理技士の年収の幅はかなり広く、平均年収前後が資格取得後の年収の目安というわけではありません。
1級建築施工管理技士の資格を取得することで、仕事の幅が大きく広がります。1級の資格をうまく活かせば、年収1,000万円も目指せます。
ただし、建築施工管理技士の仕事で年収1,000万円に達するには、1級の資格取得だけでなくさまざまな条件があります。例えば、会社の規模や経験、役職などです。
会社の規模が大きければ、規模の大きな工事を担当する機会を多くもてます。規模の大きな工事は、工事費用も高額になりやすく、その分だけ施工管理を担当する人の年収も高くなるでしょう。
規模の大きな会社なら海外赴任をする機会もあります。海外の工事は大規模なものがほとんどで、JICA(国際協力機構)関連の案件も多いです。海外赴任手当も支給されることから、年収アップが見込めます。
海外での建築需要は増加しているため、年収1,000万円を目指すなら海外赴任を自ら希望するのも良いでしょう。海外赴任と聞くとハードルが高そうに感じる人もいるかもしれませんが、案件によってはTOEICで600点程度取れれば問題なく働けます。
また、国内のみで働く場合も、経験豊富な施工管理技士なら、重宝されることが多いです。そのため、経験が増えれば増えるほど給料も上がる傾向にあります。
役職に就くのにも、1級建築施工管理技士の有資格者とそうでない方を比べれば、有資格者のほうが有利です。建設業界に限ったことではありませんが、上の役職に就任すればそれだけ年収も上がります。
現在の職場の給与水準があまり高くない場合には、転職して年収1,000万円以上を狙うのもひとつの手です。1級建築施工管理技士の有資格者なら、建築業界でかなりの需要があるため、好条件で転職できることもあります。
年収1,000万円の条件で転職するのは難しいかもしれませんが、転職先で経験を積み役職に就くなどすれば、十分実現可能です。
最短で1級建築施工管理技士になるには?
最短で1級建築施工管理技士になる方法について見ていきましょう。
まずは「技士補」の取得を目指す
令和3年4月1日より、1級建築施工管理技士補という資格が誕生しました。1級建築施工管理技士の第一次検定に合格することで取得できます。
技士補の資格を取得できれば、それ以降は1級建築施工管理技士を目指すにあたって、第一次検定を受ける必要はありません。第一次検定は免除され、第二次検定にのみ合格すれば1級建築施工管理技士の資格を取得できます。
講座や予備校を受ける
1級建築施工管理技士の資格は、資格試験学校などで講座を開講していることも多いです。講座を受講することで、プロによる解説を聞けるため独学よりも効率よく学習できます。記述問題などは添削を受けられるのもメリットです。
講座によって数日から数ヶ月など期間もさまざまあるため、予算やスケジュールに合ったものを選ぶと良いでしょう。
建設関連の会社によっては、社内講師による研修や受験費用の負担などで資格取得をサポートしているところもあります。建設関連の会社へ面接に行く際は、資格支援に関する質問をしてみるのも良いかもしれません。
過去問を繰り返し解く
資格試験では、過年度と似た傾向で出題されることが多いです。そのため、過去問を繰り返し解くようにしましょう。出題傾向や文章の長さなどに慣れることができます。本番の試験もイメージしやすくなるでしょう。
また、参考書などで知識をインプットするだけでは十分ではありません。アウトプットも行うことで得点できる力をつけられます。
過去問演習とあわせて、令和3年度から試験内容が再編されたことについても確認しておきましょう。これまで第二次検定で出題されていた内容の一部が、第一次検定に追加され、知識問題も第二次検定に移行されている部分があります。
未経験なら派遣からがおすすめ
2級建築施工管理技士の資格を保有している人が1級建築施工管理技士を受験するには、5年以上の実務経験が必要です。未経験でキャリアをスタートして施工管理技士になった人にとっては、長い道のりでしょう。
そこで、派遣で働くという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。共同エンジニアリングは、未経験者の教育体制が充実した建設業界の人材派遣に特化した会社です。自身の待遇を高めたいなどの希望を踏まえて、就業をサポートしています。大手を含む600社以上の企業と取引実績があるのも強みです。
未経験で1級建築施工管理技士の資格を取得し、高年収を目指すなら、ぜひ共同エンジニアリングにご応募ください。
この記事をお読みの方におすすめの求人
「未経験で施工管理になりたい」「働きやすい職場に転職したい」といった方は、共同エンジニアリングがおすすめです。共同エンジニアリングでは、施工管理未経験でも安心して働ける環境を整備しています。
「キャリア形成」「適正配属」「社内情報連携」の3つの項目を軸として活動するキャリアサポート課が、面談や社内研修を通じて、一人ひとりがより幸せな未来、充実したキャリアを築くための支援をしています。
スタートアップ研修や専門技術研修(建設業界に関する基礎知識)、建築設計ソフト講座など、研修制度も充実していますので、未経験で施工管理に挑戦したい方は、ぜひご応募ください。
まとめ
1建築施工管理技士は施工管理の難関資格で、一次検定と二次検定の両方に合格することで取得できます。取得に必要な勉強時間は100~400時間程度で知識だけでなく経験も必要です。
平均年収は約590万円ですが、働き方次第では年収1,000万円も夢ではありません。建築施工管理の仕事をしていて、年収アップを目指したい人は、1級建築施工管理技士の資格取得を目指しましょう。