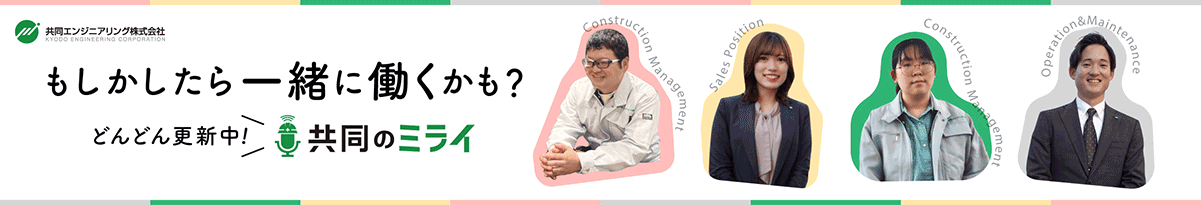目次
建設業界の現状とは

2020年から続いたコロナ禍は落ち着き、人々の生活は平常の生活に戻りつつありますが、建設業界への影響は依然として大きく残っています。また、資材の高騰によるコスト高問題も大きく影を落としているのではないでしょうか。そこで、建設業界の現状をまとめました。
建設投資額の減少
バブル期の1992年は約84兆円に達していた建設投資額は、2011年には約42兆円まで落ち込むものの、その後増加傾向にありました。しかし、2023年は約70兆円の見込みとピーク時に対して約2割減のラインです。
出典:「令和5年度(2023年度)建設投資見直し」(国土交通省)
東京オリンピックを契機とした再開発事業などは進んだものの、コロナ禍の影響による建設中止や受注低迷などの影響もあり、建築投資額の伸びは鈍化している状況となっています。
資材の高騰・円安
建設業界は、資材の高騰によるコストの上昇にも見舞われています。
コロナ後の需要回復による木材や鋼材の価格が高騰する、ウッドショック・アイアンショックで資材不足が続いていたところに、ウクライナ情勢によるエネルギー価格の上昇や急激な円安による資材高騰が加わり、公共投資への影響が懸念されています。
増加する建設業界の倒産件数
建設業界では、倒産件数も増加しています。2023年1~9月期の倒産件数は1,221件と、前年を上回る増加率です。
倒産の背景にあるのは、コロナ禍による受注低迷やコスト高だけではありません。人材や後継者不足も問題となっています。
建設業界は今後も「需要が続く」と予想
「建設需要が減っていて、将来が不安だ」という意見はあるものの、建設業界は需要が途切れるリスクが少なく、安定した将来性のある仕事です。とはいえ、社会や経済の状況は日々変化していて、建設需要がいつまで続くのかと不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
ここでは、建設業界の需要が続くといえる理由を解説します。
理由1.老朽化対策や災害対策が必要だから
住宅やビルといった建築物やインフラは、一度建てたら終わりというわけではありません。
建築物は、長年使い続ければ風雨にさらされて老朽化します。定期的なメンテナンスや再建の必要があるため、建設の仕事は途切れることがなく、常に一定の需要があると考えて良いでしょう。
また、地震や洪水といった自然災害による建設物や都市構造の破損も無視できません。自然災害は今後も発生すると想定されており、将来に備える災害対策が進められています。なかでも防災インフラの整備・管理は、国土強靭化基本計画にて基本的な方針として推進されている分野です。
出典:「国土強靭化基本計画」(内閣官房)
理由2.大規模な建築プロジェクトは続いているから
東京オリンピック、パラリンピック開催の影響により、会場建設や付近のインフラ整備で一気に建設需要が高まりました。閉幕とともにオリンピック需要は終了したものの、同様の経済効果が期待できるイベントは、オリンピックだけではありません。
日本では、今後も大きなイベントの開催計画が進んでいます。たとえば、大阪万博の開催にともなう会場の建築や周辺整備がそのひとつです。
そのほか、2027年に開業予定のリニア新幹線をはじめ、高速道路などの大規模な建築プロジェクトも着々と進んでいます。このような大規模イベントや建築プロジェクトによる需要は、開催都市や都市部に限ったものではありません。今後も全国的に建築需要が伸びると予想されています。
建設業界が抱えるふたつの課題
需要が続くと予想はされているものの、建設業界では解決すべき課題がいくつか残っています。現状の建設業界が抱える課題をみていきましょう。
課題1.人手不足
建設業界が抱える課題のひとつは、人手不足です。少子化の影響であらゆる業界で労働者は不足しているものの、建設業界はとくに職人の高齢化がすすみ、人手不足は深刻です。
国土交通省がまとめた「建設業及び建設工事従事者の現状」によると、建設業で働く労働者の約34%が55歳以上であり、高齢化が進んでいるのがわかります。29歳以下の労働者は全体の約11%にとどまっていて、専門的な知識や技術を受け継ぐ若手の育成が求められています。
出典:「建設業及び建設工事従事者の現状」(国土交通省)
課題2.長時間労働
ほかの業種よりも労働時間が長い傾向があることも、建築業界の課題のひとつです。
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和3年分結果確報」によると、令和3年の建設業の月間実労働時間は、165.3時間におよびます。全産業を示す調査産業計の136.1時間と比べると、建設業で働く労働者の就業時間は長いことがわかります。
建設業では労働時間を減らすと工期が遅れ、売り上げの減少につながりやすいというリスクがあります。多少無理をしても納期を守ろうという意識から、週休2日制がなかなか進んでいないことも課題のひとつです。
とはいえ、建築業の月間実労働時間は前年比では減っているため、業界の労働環境は改善が進みつつあります。
出典:「毎月勤労統計調査 令和3年分結果確報」(厚生労働省)
建設業界の課題解決に向けて進められている対策
解決すべき課題はあるものの、建設業界では問題を改善するべく働きかけが進んでいます。今後は、労働者にとってより働きやすい環境が整えられると予想されています。
課題解決のために、建設業界で進められている具体的な対策を紹介します。
時間外労働の是正
建設業界では、長時間労働の是正に積極的に取り組んでおり、2023年度までに労働者の全週休2日工事を目指しています。業務負担が大きい労働者もより働きやすくなるでしょう。
これまで建設業界では、36協定で定める時間外労働の上限の制限を受けていませんでした。しかし、2024年4月からは罰則付きの時間外労働規制が適用されます。
違反すると6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性があり、企業に対する良い抑止力になっています。
建設業の残業規制についてもっと知りたい方は、「2024年4月に施行される建設業の残業規制で業界はどう変わる?」の記事で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
労働者の処遇改善
建設業界で行われている労働環境の見直しも注目されています。人手不足から業務負担が大きくなりがちな労働者の負担を軽減し、雇用の安定に期待がもてます。
国土交通省では、建設業界全体を対象に、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の利用を推進しています。これは、技能者を適切に処遇するための、建設業共通の制度インフラです。
技能者の資格や社会保険の加入状況、現場の就業履歴などを登録してデータ化することで、労働者の技能や経験を客観的に評価できます。キャリアパスや処遇の見通しにも活用され、労働環境に不安をもつ方も安心して働けるよう、整備が整えられています。
出典:「建設キャリアアップシステムポータル」(国土交通省)
DXによる業務効率化
建設業界ではDX(デジタルトランスフォーメーション)化も進められています。3次元モデルによる建設生産システムや営業システムの導入、クラウドサービスの利用などのデジタル化は、業務効率の改善や労働者の負担軽減に役立ちます。とくに人手不足が深刻な建設業界では、DX化による恩恵は大きなものとなるでしょう。
国土交通省でも、ドローンの活用や3次元データによる施工、施工管理、建設機械の自動運転化といった、建設業界の「i-construction(アイ・コンストラクション)」を推進しています。
これは、現場の測量から設計、施工、検査、建設物の維持管理までのすべてのプロセスにICT機器を導入し、全体の生産性向上を目指す取り組みで、現場の少人数化が実現します。
出典:「i-construction(アイ・コンストラクション)」(国土交通省)
女性の積極的な採用
これまで建設業界は、「体力が必要できつい仕事」というイメージがあり、女性からは敬遠されがちでした。しかし、建設業では女性の採用を積極的に進めていて、性別を問わず就業のチャンスが広がっています。
女性や若い世代の労働者を増やすために、建設業界では労働環境の改善が進んでいます。国土交通省でも「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画~働きつづけられる建設産業を目指して~Plan for Diverse Construction Industry where no one is left behind」を策定して、入職者に占める女性の割合を、令和6年までに前年度比で増加させることを目指しています。
目標は女性が就業しやすく、長く働き続けられる職場です。官民一体となって改善に取り組んでいます。
出典:「建設産業における女性の定着促進に向けた取組について」(国土交通省)
建築業法改正
建設業界は工事費の上昇や人材不足による負担が、下請事業者にかかりやすい構造となっています。そこで国は下請事業者への負担軽減の一環として、2023年1月より改正建設業法を施行しました。2022年11月の閣議決定からのスピード施行です。
改正建設業法では、工事金額要件が見直しされています。変更点は以下のとおりです。
| 現行 | 改正後 |
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工 | 4,000万円(6,000万円) | 4,500万円(7,000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する | 3,500万円(7,000万円) | 4,000万円(8,000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 | 3,500万円 | 4,000万円 |
※()内は建築一式工事の場合
外国人労働者の活用
2022年8月の閣議決定により、建設分野における特定技能制度の業務区分が「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分へ統合され、外国人労働者の柔軟な人材供給の態勢が整備されました。
旧業務区分は19区分あり業務範囲が限られていましたが、区分統合により在留資格上従事できる業務が広がっています。
インフラシステム海外展開
国内市場の縮小への対策として、インフラシステムの海外展開も進められています。
国土交通省は、さらなる受注機会拡大のため「インフラシステム海外展開行動計画2022」を策定しました。海外展開推進に向けビジネス環境整備や機会創出、中堅・中小建設業者の海外進出支援などの取り組みを掲げています。
まとめ
建設需要は人口減少、大規模イベントの開催などさまざまな要因によって、多少の浮き沈みがあります。とはいえ、住宅やビルの建設、インフラの整備のニーズは安定していて、将来性があることに変わりはありません。
一昔前は、「3K(きつい、危険、汚い)」というイメージがあったものの、現在の建設業界は労働環境の改善が進んでいます。若い世代や女性の活躍も推進しているため、転職先に検討してみてはいかがでしょうか。