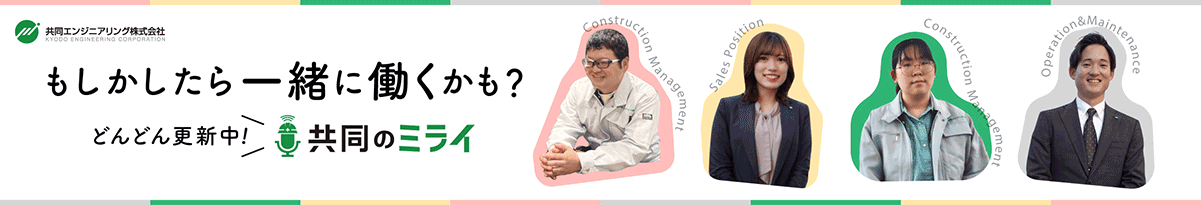目次
主任技術者になるには実務経験・資格取得が必要

主任技術者になるには、次にあげる3つの要件のうち、いずれかひとつを満たす必要があります。
・ひとつの業種の実務経験を積む
・複数業種に従事して実務経験を積む
・国家資格を取得する
いずれの要件においても、基本的には一定以上の実務経験が求められます。
では、それぞれの要件について具体的に解説していきます。どの要件を満たすことが自分にとってベストな選択か考えてみましょう。
【主任技術者】要件1.ひとつの業種の実務経験を積む

ひとつの業種に集中して必要な実務経験年数を積むことで、主任技術者を目指す方法です。この場合、指定学科を修了した学校によって、主任技術者になるために必要な実務経験年数が異なります。
①大学(短期大学を含む)の指定学科を卒業している者…3年以上
②高等専門学校の指定学科を卒業している者…3年以上
③高等学校の指定学科を卒業している者…5年以上
④上記以外の学歴…10年以上
指定学科を卒業していない人の場合は、10年以上と非常に長い実務経験が必要となりますが、①〜③のように指定学科を卒業している人は、3年または5年以上の実務経験で主任技術者になることができます。
なお、指定学科とは、国土交通省令によって定められている学科のことです。建設業には29種類の業種がありますが、建設業法施行規則第1条により、それぞれの業種に対して指定学科が定められています。
例えば、建築工事業の場合、指定学科は「建築学または都市工学に関する学科」であり、このどちらかについて学ぶことが求められます。
それぞれの業種の指定学科は次の表のとおりです。
許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |
土木工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科 |
舗装工事業 | |
建築工事業 | 建築学または都市工学に関する学科 |
大工工事業 | |
ガラス工事業 | |
内装仕上工事業 | |
左官工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
とび・土工工事業 | |
石工事業 | |
屋根工事業 | |
タイル・れんが・ブロック工事業 | |
塗装工事業 | |
解体工事業 | |
電気工事業 | 電気工学または電気通信工学に関する学科 |
電気通信工事業 | |
管工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科 |
水道施設工事業 | |
清掃施設工事業 | |
鋼構造物工事業 | 土木工学、建築学または機械工学に関する学科 |
鉄筋工事業 | |
しゅんせつ工事業 | 土木工学または機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学または機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 | 建築学、機械工学または電気工学に関する学科 |
消防施設工事業 | |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学または機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学または機械工学に関する学科 |
出典:「土地・不動産・建設業」(国土交通省)
【主任技術者】要件2.複数業種に従事して実務経験を積む

複数の業種に係る実務経験を積んできた人も、定められている要件をクリアすれば主任技術者になることができます。
いずれの業種の主任技術者を目指す場合も、それぞれで「指定された2種類の業種で合計12年以上の実務経験を有する者のうち、許可を受けようとする業種の実務経験が8年以上あること」が要件となっています。
例えば、大工工事業の主任技術者になりたい場合は、「建設工事業及び大工工事業に係る建設工事に関して12年以上、そのうち大工工事業に係る建設工事に関して8年以上」の実務経験を積むことが必要です。
建設業には29業種ありますが、そのうち10業種(大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、しゅんせつ工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業、解体工事業)において、このルートから主任技術者になることができます。
ここでは、一例として大工工事業、とび・土工工事業、ガラス工事業、解体工事業において主任技術者になるために必要な複数業務に係る実務経験の要件を次に示します。
許可を受けようとする建設業 | 実務経験 |
大工工事業 | 1.建設工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者 |
2.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 | |
とび・土工工事業 | 1.土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
2.とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 | |
ガラス工事業 | 1.建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
解体工事業 | 1.土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
2.建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 | |
3.とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
出典:「土地・不動産・建設業」(国土交通省)
【主任技術者】要件3.国家資格を取得する
国家資格を取得することによっても、主任技術者になることができます。建設に関わる各種工事の技術検定や、建築士・技術士試験、職業能力開発促進法に基づく技能検定などが要件を満たす国家資格です。
例えば、建築工事業の場合は1級・2級建築施工管理技士及び1級・2級建築士のうち、いずれかの国家資格を取得することで主任技術者になることができます。
ただし、国家資格によっては一定以上の実務経験を満たしていることが受験資格に含まれていることがあります。必ずしも実務経験無しで主任技術者になれる訳ではないことを把握しておきましょう。
例えば、建築施工管理技術検定の場合、以下のような年齢・実務経験が受験の際に必要となります。
・第一次検定…試験実施年度において満17歳以上
・第二次検定…学歴によって1年以上~8年以上の実務経験
国家資格ごとに受験資格が異なりますので、資格取得を目指す際には、必ず事前に確認しておきましょう。
なお、建設業における全29業種それぞれで指定された国家資格があります。今回は一例として、木工事業、建築工事業、電気工事業、大工工事業、ガラス工事業の5つの業種における必要な資格をまとめました。
許可を受けようとする建設業 | 国家資格 |
土木工事業 | ①技術検定 |
建築工事業 | ①技術検定 |
電気工事業 | ①技術検定 |
大工工事業 | ①技術検定 |
ガラス工事業 | ①技術検定 |
出典:「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧」(国土交通省)
主任技術者に必要な資格と難易度
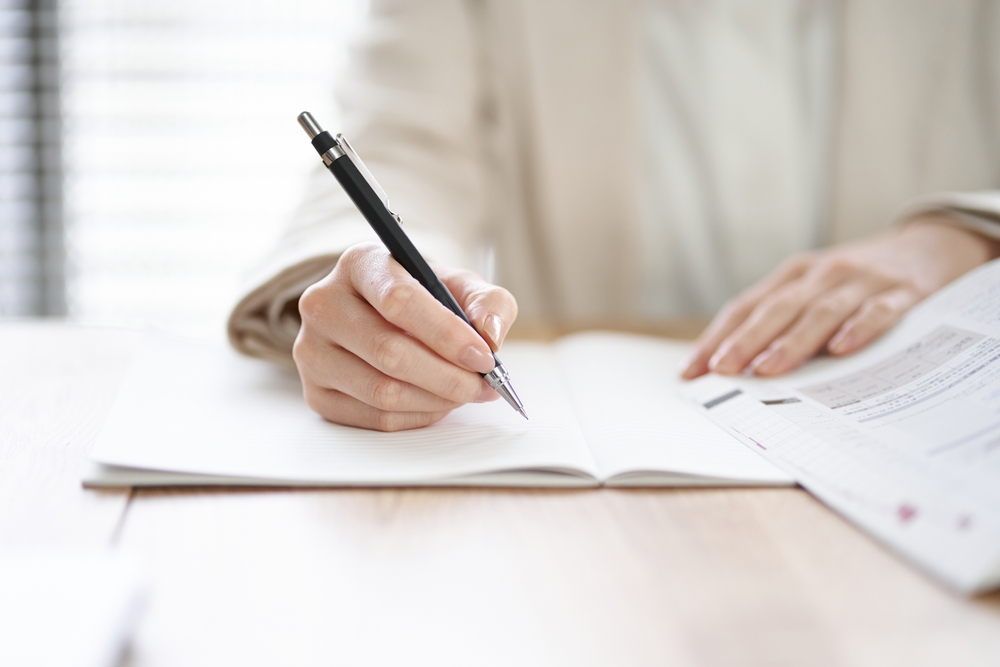
主任技術者に必要な代表的な国家資格の合格率や試験の難易度を解説します。主任技術者へのキャリアアップを目指すには、下記のいずれかの資格を取得しましょう。
2級施工管理技士
2級施工管理技士の資格には業務内容に応じて以下の7種類があり、建設業種区分により指定された資格種類・技術種別の2級施工管理技士の資格者は主任技術者になることができます。
・建築施工管理技士
・土木施工管理技士
・電気工事施工管理技士
・管工事施工管理技士
・建築機械施工管理技士
・造園施工管理技士
・電気通信工事施工管理技士
資格取得には学歴や技能検定合格に応じ、実務経験が必要となります。また、どの分野の施工管理技士も出題範囲が広いため、目指す分野で必要なスキルや知識を総合的に習得しておきましょう。
建築・土木・電気工事・管工事の2級試験における2022年度の合格率は以下のとおりです。
・建築:第一次42.3%、第二次53.1%
・土木:第一次63.8%、第二次37.7%
・電気工事:第一次55.6%、第二次61.8%
・管工事:第一次56.8%、第二次59.7%
2級建築士
2級建築士は、戸建住宅など比較的小規模な建築物に限り設計や工事監理を行える資格です。2級建築士は、建設業種区分のうち以下の業種において主任技術者になれます。
・建築業(建築一式)
・大工工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・屋根工事業
・内装仕上工事業
2級建築士は比較的難易度の高い試験で、2023年度の本試験の合格率は35.0%でした。
第2種電気工事士
電気工事士は、電気工事の欠陥による災害防止を目的として電気工事作業へ従事する方に必須となる国家資格です。第2種では住宅や店舗など、比較的小規模の電気工事が可能です。 第2種電気工事士の資格取得と3年の実務経験を経ることで電気工事業での主任技術者になれます。
第2種電気工事士は比較的取得しやすく、2022年度の第一次検定の合格率は平均56.0%、第二次検定の合格率は平均72.6%でした。
技能検定(技能士)
技能検定は、建設業では建築大工やとび、左官などさまざまな種類があります。資格は1級~3級にわかれており、2級以上を取得していればそれぞれの業種における主任技術者になれます。
2級の合格率は28%前後と少し難易度が高く、主任技術者になるには3年以上の実務経験が必要です。
主任技術者を目指す際に念頭に置いておくこと
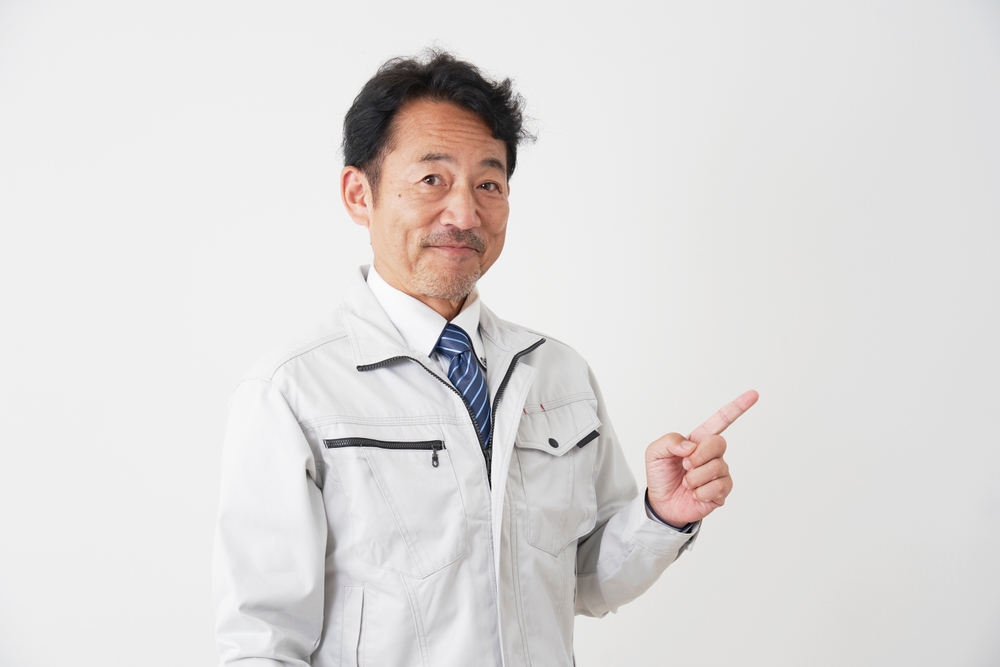
主任技術者は、工程管理や品質管理、工事現場における施工の従事者の技術向上を促す指導などの役割を担っており、主任技術者の仕事の質は建設工事そのものの品質に大きく影響します。
そのため、不適格な業者を見極め、適格な施工を確保する観点から、当該建設業者と主任技術者の間には、「直接的かつ恒常的な雇用関係」が求められます。また、重要な建設工事においては、主任技術者は現場の兼任をすることはできません。
この2点について、以下で解説します。
正社員である必要がある
主任技術者の配置の際は、建設会社が責任を持って、適切な知識と技術を有する主任技術者を選ぶことが求められるため、先述のとおり、主任技術者と建設会社は「直接的かつ恒常的」な雇用関係になくてはなりません。
そのため主任技術者は、建設会社との間に第三者が介在しない雇用関係、つまり、アルバイト契約や派遣契約のような雇用関係ではなく、正社員であることが求められます。また、他社からの出向なども認められていません。
重要な建設工事では現場を兼任できない
公共性のある施設や多くの人が利用する施設を建設する工事では、施工品質を確保するために、主任技術者は専任であることが義務付けられています。
ただし例外もあり、次のふたつの条件を満たす場合には、兼任可能です。
・密接な関係のある建設工事であること
・同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する工事であること
上記の条件を満たしていれば、基本的にひとりの主任技術者がふたつの現場を兼任できます。
なお、工事請負金額が3,500万円未満で、そもそも主任技術者の専任が求められない工事であれば、これらの条件に関係なく兼任が可能です。
主任技術者の申請方法・必要書類
主任技術者になるには、ここまで紹介してきた要件を満たしている必要があります。要件を満たす証明書を用意し、工事請負契約時に申請書類を作成し、提出しなければなりません。
要件を満たすことを証明できる書類を用意する
まず、発注者との契約書類である、主任技術者資格を客観的に証明できる書類を準備しなければなりません。証明書として利用できる書類は以下のとおりです。
資格:資格者証や免許書、登録証、合格証明書など
実務経験:実務経験証明書及び所属業者が特定できる健康保険被保険者やJCISの所属情報など、常勤を証明できる書類
登録技能者講習:講習終了証
申請書類を作成・提出する
工事請負契約にあたっては、発注元に主任技術者を通知しなければなりません。
「現場代理人及び主任技術者等通知書」や主任技術者の「経歴書」など発注元が指定する書類を、要件を満たしていることを証明する書類とともに提出します。
まとめ
主任技術者は、正社員としてやりがいのある仕事に就くことができるうえ、給与・待遇の面でも魅力的なポジションです。
一方で、国家資格の取得や実務経験など、主任技術者になるための要件を満たすことは容易なことではありません。
ご自身の学歴や経験に自信がない場合は、実務経験を積みながら、資格取得を目指していくことが主任技術者になる近道といえるでしょう。
共同エンジニアリングでは、入社時研修やOJT研修、専門技術研修など、さまざまな研修制度があり、国家資格の取得に向けた資格支援も行っています。大手建設会社出身や、資格取得者なども所属しているので、自分の成長にあわせて研修も可能です。
未経験で建設業界を目指している方は、どうぞお気軽に共同エンジニアリングまでご相談ください。