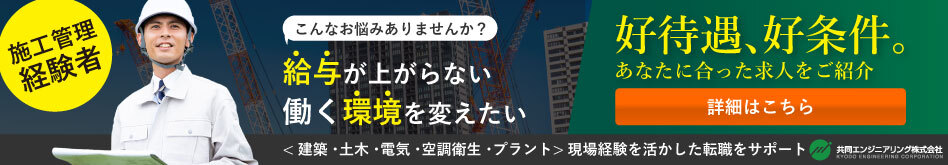目次
管工事施工管理技士とは?

管工事施工管理技士とは、建設業法第27条第1項に基づく国家資格です。上下水道の配管設備、ガス配管、空調設備などの管工事のエキスパートとして、幅広いニーズがあります。
管工事施工管理技士には1級と2級の2種類があり、級によって業務範囲が異なります。まずは、それぞれの受検資格や試験内容の違いをみていきましょう。
なお、試験は国土交通大臣が指定する一般財団法人 全国建設研修センターが例年実施していて、合格すると「技術検定合格証明書」が交付されます。詳しい受検資格や手続きは、センターの公式サイトで確認しましょう。
出典:一般財団法人 全国建設研修センター「技術検定」
1級と2級の違い
管工事施工管理技士の資格は、1級と2級で下記の違いがあります。
保有資格 | 特徴 |
管工事施工管理技士1級 | ・監理技術者や主任技術者として認められる |
管工事施工管理技士2級 | ・主任技術者として認められる |
1級を取得すると主任技術者としてはもちろん、監理技術者としても認められます。
元請の特定建設作業者が総額5,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円以上)の下請契約を行う場合、監理技術者の設置が法的に義務付けられています。規模の大きい建設工事では、監理技術者の設置が欠かせません。
2級を取得している場合は、主任技術者として活躍できます。上記のように監理技術者の設置が求められている工事以外は、元請・下請のいずれも主任技術者の設置が法的に必要です(※)。
1級管工事施工管理技士を取得すれば、監理技術者として従事でき、より規模の大きな工事にも携われるようになります。
※特定専門工事(土木一式工事・建築一式工事以外の建設工事の中で、施工技術が画一的かつ技術上の効率化を図る必要があるもの)において、主任技術者の配置が不要となる場合を除く。
1級管工事施工管理技士
1級管工事施工管理技士は、2級管工事施工管理技士の上位資格です。資格を取得すれば、建設業法で定める主任技術者、監理技術者などの立場で働けます。
受検資格
1級管工事施工管理技士の試験は第一次検定と第二次検定の2種類あり、それぞれ受検資格が異なります。
第一次検定の要件は、年齢のみです。19歳以上であれば学歴や経験等は関係なく、誰でも受検できます。受検したい年度中に19歳以上の者なら受検できるとされています。
第二次検定は、受検者の状況によって要件が異なります。主な要件は、それぞれ下記の通りです。
受検者の状況 | 受検資格 |
1級一次合格者 | 第一次検定に合格後、下記いずれかに該当 |
2級二次合格者であり、1級一次合格者 | 2級第二次検定に合格後、下記いずれかに該当 |
特徴は、令和6年度(2024年度)から新受検資格に変更されたことです。新受検資格では、指導監督的実務経験が要件から外されました。
令和5年度以前の旧受検資格からの改正にともなう経過措置として、令和10年度(2028年度)までの5年間は旧要件を満たした方も従来通りに受検できます。
試験の概要
1級管工事施工管理技士の試験は、第一次検定と第二次検定に分かれています。第一次検定は学科、第二次検定は実地試験で、それぞれ日を分けて開催されるため同時受検はできません。
第一次検定はマークシート方式で行われて、機械工学、施工管理法、法規の科目から出題されます。全体得点60%以上、うち施工管理法の得点50%以上が合格ラインです。
第二次検定は記述式による筆記試験です。施工管理法の知識や能力に関する問題が出題されます。第二次検定合格ラインは、得点60%以上です。
2級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士は、管工事施工管理技士の登竜門的な資格です。資格を取得すると、一般建設業の専任技術者、主任技術者として働けます。
受検資格
2級管工事施工管理技士の第一次検定も、1級と同じく学歴や経験を問わず受検できます。受検する年度中に17歳以上となる者とされており、2009年4月1日生まれの方も対象に含まれます。
第二次試験の受検資格は、受検者の状況に応じて異なっており、それぞれ下記の通りです。
受検者の状況 | 受検資格 |
1級一次合格者 | 第一次検定に合格後、実務経験1年以上 |
2級一次合格者 | 第一次検定に合格後、実務経験3年以上 |
2級管工事施工管理技士の受検資格も、令和6年度(2024年度)から新制度に変更されています。1級と同じく経過措置もとられており、令和10年度(2028年度)までは旧要件を満たしている方にも受検資格があります。
旧受検資格では、2級管工事施工管理技士も指定学科の卒業者、他校や他学科の卒業者など、学歴や保有資格に応じて実務経験数が細かく定められていました。新要件となった2024年度や2025年度は、学歴を問わず試験の合格状況によって上記の受検資格が設けられています。
試験の概要
2級管工事施工管理技士の試験も、学科の第一次検定と実地の第二次検定があります。2級の場合は第一次検定と第二次が同日開催されるため、同時受検が可能です。第一次検定、第二次検定とも、得点60%以上が合格ラインとされています。
管工事施工管理技士の難易度

管工事施工管理技士は、合格ラインから考えても難易度が極端に高い資格試験とは言えません。加えて、新要件が適用されている令和6年度以降は、実務経験による縛りが緩和されており、幅広い方が受検できるようになりました。
きちんと要点を押さえて勉強することで、多くの方が合格を目指せる難易度です。参考までに、直近5年間(令和元年~令和5年度)の合格率は下記の通りでした。
第一次検定 | 第二次検定 | |||||
実施年 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
令和5年度 | 11,068人 | 7,701人 | 69.6% | 10,385人 | 8,552人 | 82.3% |
令和4年度 | 11,051人 | 6,274人 | 56.8% | 8,316人 | 4,962人 | 59.7% |
令和3年度 | 9,070人 | 4,406人 | 48.6% | 13,099人 | 6,054人 | 46.2% |
令和2年度 | 9,535人 | 6,064人 | 63.6% | 12,678人 | 5,514人 | 43.5% |
令和元年度 | 9,118人 | 6,321人 | 69.3% | 13,064人 | 5,760人 | 44.1% |
引用:KGKC建設技術教育センター「受験者数・合格率動向」
第一次検定は、令和3年度を除けば50%以上の合格率で安定していることがわかります。令和3年度は第二次検定も高くない合格率となっていることを考慮すると、例年よりも合格者が出にくかった特別な年と言えます。
総合的に見ると、第一次試験は少なくとも2人に1人以上の割合で合格できる難易度です。
第二次検定は、令和元年度~3年度にかけて50%未満の合格率が続いているものの、直近の2年間は受検者の半数以上が合格しています。中でも令和5年度は、上記以外の期間も含めた直近10年のうち、最も高い合格率となりました。
加えて、令和5年度は第一次検定も合格率がもっとも高くなっています。選択問題も含まれていることを考えると、効率良く暗記すれば堅実に点数を高められる試験です。
管工事施工管理技士を取得するメリット

管工事施工管理技士は、管工事の管理業務に関する専門知識、技術、経験を有することを証明する資格です。管工事の現場は多岐にわたるため、建設業界で資格者のニーズは高く、需要は安定しています。
管工事施工管理技士の資格を取得するメリットをみていきましょう。
資格取得で仕事の幅が広がる
資格を取得すると専門的な知識や技術があると評価されて、できる仕事の幅が広がります。大きな案件に携わり、実力を発揮するチャンスが得られるかもしれません。
1級管工事施工管理技士を取得すれば、特定建設業の専任技術者になれます。コミュニケーション能力や統率力も求められる、重要でやりがいのある仕事です。
2級管工事施工管理技士の場合は、一般建設業の専任技術者になれるチャンスです。工事の裏側を知り、視野や知見を広げるきっかけになるでしょう。
キャリアアップにつながる
管工事施工管理技士は、信頼を得やすい国家資格です。取得すれば社内評価が上がり、昇進に期待がもてます。クライアントからの信頼も得やすく、実力を発揮できるでしょう。
資格手当が出る企業もあり、収入アップや将来的な転職にも有利になります。
管工事施工管理技士になるための勉強方法

管工事施工管理技士の資格を取得するには、次の3つの方法があります。
・専門学校に通う
・通信講座を受講する
・テキストやアプリで独学する
それぞれの特徴やメリット、デメリットをみていきましょう。
専門学校に通う
管工事施工管理技士のコースがある工業系の専門学校に入学すれば、対面式授業で基礎からしっかり学べます。
履修内容によっては受検資格の実務経験が免除になる場合があるため、仕事を始めて間もない方にもおすすめです。コースが豊富な学校を選べば、管工事施工管理以外にも複数の施工管理関連の資格取得を目指すことができます。
一方で、専門学校は卒業までに時間と費用がかかります。2年制のコースでも、200万円以上の学費がかかるのが一般的です。また、昼間に授業を行う学校もあるため、仕事と通学の両立が難しい傾向があります。
通信講座を受講する
資格学校の通信講座は、自宅でプロの解説や記述問題の添削指導が受けられるのが魅力です。
通信講座には数日の短期コースから数か月の長期コースまであり、費用はさまざまです。WEB受講を取り入れている講座もあり、仕事と勉強を無理なく両立できます。専門学校より学費が安い講座が多く、なるべく費用負担を減らしたい方におすすめです。
一方で、学習管理が難しく、挫折しやすいデメリットがあります。また、講師がすぐそばにいないため、質問があってもすぐに回答が得られないことも多いです。
テキストやアプリで独学する
市販のテキストや問題集を使えば、独学もできます。テキストの購入費用だけで済むため、学校や通信講座を受講するより費用負担をおさえられるのが魅力です。
とはいえ、2級でも1日2時間の学習を半年前後続ける必要があり、学習管理が難しく、モチベーションが続きにくいと感じる方もいます。独学だと試験の情報を入手しにくいため、講習会も上手に活用しましょう。
派遣で働きながら学ぶのもおすすめ!

未経験者の場合は、費用負担や学習管理が難しい場合は、派遣で働きながら資格取得を目指すのもおすすめです。現場経験を積むことで、未経験でも多くの知識を習得できます。受検資格に必要な実績が積めるのも高ポイントです。
BREXA Engineeringでは、幅広い建設業の現場を経験できます。大手ゼネコンの現場もあり、経験の幅が広がるぶん資格取得のチャンスが広がります。現在、3,200名以上の技術社員を抱え、資格支援研修や資格取得手当もあり、スキルアップに集中できる環境が整っています。
この記事をお読みの方におすすめの求人
「未経験で施工管理になりたい」「働きやすい職場に転職したい」といった方は、BREXA Engineeringがおすすめです。BREXA Engineeringでは、施工管理未経験でも安心して働ける環境を整備しています。
「キャリア形成」「適正配属」「社内情報連携」の3つの項目を軸として活動するキャリアサポート課が、面談や社内研修を通じて、一人ひとりがより幸せな未来、充実したキャリアを築くための支援をしています。
スタートアップ研修や専門技術研修(建設業界に関する基礎知識)、建築設計ソフト講座など、研修制度も充実していますので、未経験で施工管理に挑戦したい方は、ぜひご応募ください。
まとめ
管工事の仕事には、未経験で特別な資格がなくても就業できます。とはいえ、資格を取得することで、より難易度の高い仕事にチャレンジでき、将来的な転職にも有利です。
管工事施工管理技士は難易度が高すぎず、独学でも取得を目指せる資格です。未経験の場合は、派遣を視野にいれることで、就業しやすく、現場で働きながら知識や実務経験を増やすことが可能です。ぜひ資格を取得し、管工事のスペシャリストを目指しましょう。