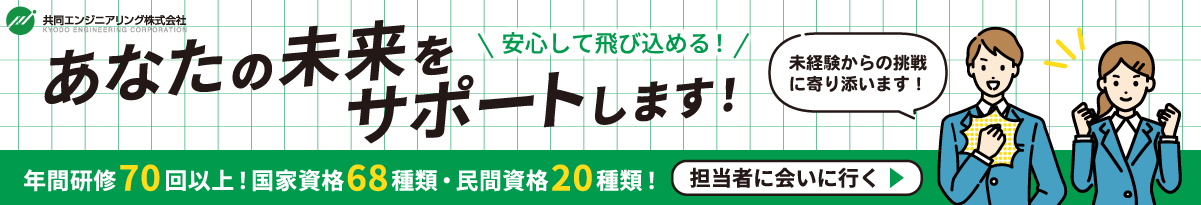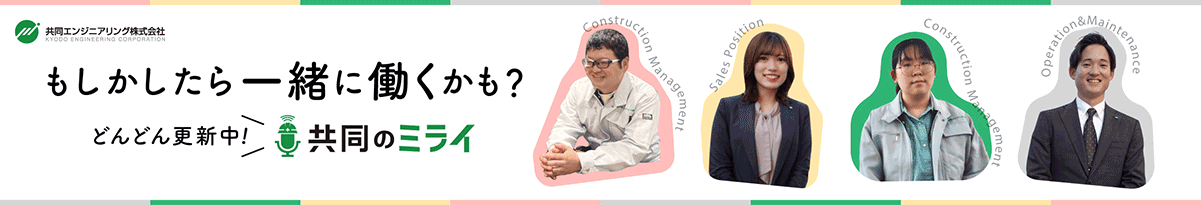目次
インフラ業界とは「社会の基盤となるサービスを提供する業界」

インフラとは「infrastructure(インフラストラクチャー)」の略で、「社会基盤」を指す言葉です。道路や鉄道、上下水道、発電所などが該当します。
つまりインフラ業界とは、私たちの生活を支えるサービス・仕組みを提供する業界のことです。ここでは、インフラ業界の仕組みと業界を取り巻く現状について解説します。
インフラ業界の仕組み
インフラ業界には多種多様な業種・分野があり、それぞれでビジネスモデルは異なります。しかし、経営資源(モノor人)を活用して顧客に価値あるサービスを提供し、収益を上げる点では、どの業種・分野でも共通です。
通勤・通学や外出などで利用する電車(鉄道事業)を例に挙げると、経営資源は「路線・駅」「運転手・整備士」などが該当します。
それらの経営資源を活かして、乗客を目的地まで運ぶサービスを提供し、乗客はその対価として運賃を支払うのが鉄道事業のビジネスモデルです。
インフラ業界を取り巻く現状
インフラ業界では、環境意識の高まりに応じて、脱炭素化や再生可能エネルギー、インフラ利用者の減少などに、どのように取り組むかを課題としています。
再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・地熱など、温室効果ガスを排出しない低炭素の国産エネルギーのことです。電力会社・ガス会社は、そういった再生可能エネルギーの研究・実用化に向けて取り組んでいます。
インフラ業界だけに限りませんが、少子高齢化による人口の減少も深刻です。インフラの利用者が減少していく中で、どのように収益を確保し、インフラを提供していくかが課題となっています。
インフラ業界の主な4つの業種

インフラ業界には多様な業種がありますが、ここでは主要な4つの業種を紹介します。
エネルギー系
電力・ガス・石油など、ライフラインに関わるのがエネルギー系です。太陽光発電や風力発電、地熱発電といった再生可能エネルギーを開発・提供する会社も含まれます。電気やガスなどは国民の生活に欠かせないものであるため、安定性の高い企業が多いといわれていました。
しかし、近年は電力・ガスの自由化や少子高齢化による人口減少により、各企業の競争が激しくなっています。とはいえ世界的に見れば、電力・ガスの需要は増加傾向です。グローバル化が進む現代において、今後も海外での市場獲得が重要視されるでしょう。
交通系
鉄道・バス・航空機といった公共交通機関や、道路・トンネルなどが交通系のインフラです。交通網の発展は国の経済発展に大きく関わっています。しかし高度経済成長期に比べ、新しい鉄道が開通することは少なく、鉄道事業は失速気味です。
そのため、鉄道会社は駅開発に加え、小売業や不動産などの事業運営も行うケースが増えています。道路業界では、高速道路整備に携わることが多い傾向です。国や土木関連の企業に委託され道路整備を行います。
生活系
ゴミ処理場や上下水道、電話・インターネットなどの通信系、テレビ・ラジオなどの放送系が生活系インフラです。インターネットやAIの発展、スマートフォンの普及などにより、通信系の需要が高まっています。
インフラ業界の中でもトレンドや流行による変化の激しい分野ですが、需要が高いため今後も発展していくことが予想されます。
土木・建築系
道路・トンネル・橋梁といった道路整備関連や、公共施設・湾岸施設の管理を行うのが土木・建築系インフラです。また公共施設のバリアフリー化や音声ガイダンスによる誘導・解説サービスなども含まれます。
上記に加え、土木・建築系は既存施設の老朽化への対応も含まれるため、業務幅が広いことが大きな特徴です。ゆえに安定して仕事を得られる魅力があります。
インフラ業界の平均年収

インフラ業界の平均年収は、業種によって異なります。国税庁が公表している資料によると、令和5年(2023年)における各業種の平均年収は、下記の通りです。
業種 | 平均年収 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 775万円 |
情報通信業 | 649万円 |
運輸・郵便業 | 473万円 |
出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
上記の表のみを見ると、運輸・郵便業が極端に少ないように感じられますが、全業種と比較すると決して低い年収とはいえません。
同年における全業種の平均年収は、460万円です。全体の平均と比較すると、インフラ業界の運輸・郵便業は十分高い部類に入るといえます。電気・ガス・熱供給・水道業の775万円も含めて考えると、インフラ業界の年収は全体的に平均よりも高めです。
また、前年比で微増ながらも全体的に平均年収が増加傾向にあります。インフラ業界も、上記の平均年収よりもさらに増加する可能性は十分考えられます。
インフラ業界の現状と課題

インフラ業界は、人々の生活を支える、なくてはならない重要な業種です。一方で、他業種がそれぞれ課題を抱えているように、インフラ業界も例外とはいえません。
ここでは、インフラ業界の現状と抱えている課題を解説します。
インフラ業界の現状
内閣府の「社会資本ストック推計」によると、公的機関によって整備される社会資本ストック(インフラ)は、2020年度時点で993兆円です。過去の推移からみても増加傾向にあり、部門別の内訳をみると、道路のみが全体の3割以上、水道・下水道で2割弱を占めています。
社会資本ストックの特徴は、経過年数にともなって老朽化が進み、定期的な整備が求められることです。実際に、近年は経過年数によって老朽化が進んだ社会資本ストックも多く、新たな整備に加えて効率的な利活用の模索が欠かせません。
直近の数年のみでも、電力業界で新規参入が増えるなど各業種で目まぐるしい変化が生じています。上記のデータが2020年時点のものである点を含めて考えると、2021年以降でさらに変化が生じている可能性も考えられます。
出典:内閣府「社会資本ストック推計」
インフラ業界の課題
インフラ業界の課題は、複数あげられます。中でも急務といえるのが、人材確保と技術者の育成です。
経済産業省の調査では、ダムや導水路の工事・運用などを担うダム水路主任技術者についてすでに人材確保の面で課題が顕著となっていることが記載されていました。
管理が必要な水力発電施設数が増加しているのに対して、ダム水路主任技術者免状の交付件数が、1997年度をピークにゆるやかな減少を見せています。
必要な人材の減少は、管理のみならずメンテナンス事業に対しても大きな影響をおよぼします。どのようなインフラ設備も、老朽化は避けられません。老朽化の進むインフラ設備のメンテナンスを滞りなく続けるためにも、今後は人材確保に加えて技術者育成の必要性が増すといえます。
さらに、健全に経営を維持する観点からも、優秀な人材の確保や未経験からの技術者育成が重要です。少子高齢化社会が続く日本国内において、電気・ガスの国内需要が今後急激に伸びることは考えにくく、減少傾向にある中で限られた顧客を獲得するために、各社の競争は激化すると考えられます。
競争の中で勝ち残る術を得る方法として、人材確保や技術者育成による企業価値の向上が求められます。
出典:経済産業省「電気保安人材の現状分析と取組の方向性について」
インフラ業界で働く3つの魅力

インフラ業界は人々の生活を支える重要な役割を担っています。そのため「仕事が大変」「責任が重い」といったイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。インフラ業界へ転職するか悩んでいる人は、ここで紹介する3つの魅力を参考にしてみてください。
魅力1.社会へ貢献している実感が得やすい
インフラ業界は人々の生活基盤を支えていることから、社会貢献していることを実感できる仕事です。部屋の電気やガス、テレビなどもインフラ業界が密接に関わっています。
私たちが不自由なく暮らせるのも、インフラ業界のおかげといっても過言ではありません。そういった重要な仕事に関わることで、誰かの暮らしを支えている実感が得られるでしょう。
魅力2.業界全体が景気に左右されにくい
インフラ業界は人々の生活に欠かせないサービスを提供しているため、景気に左右されにくいのも大きな魅力です。職種によっては行政との取引もあります。将来的に需要がなくなることも考えにくいため、経営が傾くことは少ないでしょう。
魅力3.安定している企業が多い
インフラ業界は安定している企業が多い傾向にあります。そのうえ住宅手当や扶養手当など、福利厚生が充実している企業も多いため、働きやすい環境が整っているといえるでしょう。
インフラ業界で求められる人材の特徴
業界・業種によって、必要とされるスキルや求められる人材は異なります。インフラ業界への転職を考えている人は、どのような人材が求められるのか知っておくことが大切です。ここでは、インフラ業界で求められる人材の特徴を3つ紹介します。
社会課題を感じている人
近年ではインフラの老朽化が重要な社会課題になっています。金属の腐食やコンクリートの割れなど、経年劣化による老朽化は多くの人の命を奪いかねません。実際にトンネルや橋の崩壊事故もメディアで取り上げられています。
インフラ業界へ転職する場合は、こうした社会課題を改善したいという強い意志が重要です。また人々の暮らしを支える重要な仕事であるため、社会貢献したいという人も求められています。
計画性のある人
インフラ業界は人々の生活を支える基盤であるため、少しのミスでも大きな損失を招いてしまうおそれがあります。そのため、ミスなく安定した生活基盤が供給できるよう、計画的に仕事をこなせる人を求めています。
冷静な判断ができる人
インフラ業界に限った話ではありませんが、仕事には思いがけないトラブルはつきものです。「悪天候により工事の延期」「災害による停電」などのトラブルは、人々の生活に大きく影響します。
しかし、このようなトラブルに対しても冷静に状況を判断し、トラブルを解決していかないと状況は悪くなる一方です。インフラ業界では、適切な対処法を見極める判断力も求められます。
インフラ業界に就職・転職するためのポイント
インフラ業界に就職・転職するためには、事前準備が大切です。下記2つのポイントを押さえて、就活や転職に臨みましょう。
・インフラ関係の最新知識を調べる
・資格やスキルを身に付ける
前述の通り、今後は老朽化した施設の管理・メンテナンスにおける人材確保の困難さなど、インフラ業界にはいくつかの課題があります。また、毎年のように新たな技術の台頭や、働き方の多様化といった変化も生じているため、こまめな情報収集が欠かせません。
インターネットや新聞などで、インフラ関係の最新知識を常に入手するよう心がけましょう。業界専門の情報を仕入れておくと、面接の場でも活用できます。 就きたい業種に適した資格やスキルを身に付けておくことも、就職や転職の確率アップには効果的です。電気工事士や電気主任技術者、ガス主任技術者などが候補としてあげられます。
まとめ
インフラ業界とは、人々の生活を支えるサービス・仕組みを提供する業界のことです。インフラ業界は福利厚生の充実している企業が多いため、安定して働きたい人や社会貢献したい人は、転職を目指してみると良いでしょう。
しかし、インフラ業界は多種多様な業種があるため、転職先選びは悩んでしまうものです。そういった人は、「施工管理」への転職を検討してみてください。
インフラ業界の中でも、施工管理は未経験からでもチャレンジできるやりがいのある仕事です。建設コンサルティング会社「BREXA Engineering」では、未経験者向けの教育体制が充実しております。
導入研修や資格取得研修、キャリアアップ研修など、さまざまな研修制度があるのも強みです。また施工管理経験豊富なプロが講師であるため、レベルの高い研修が受けられます。
また、プラント工場の案件や、O&M(オペレーション&メンテナンス)の職種も取り扱っております。インフラ業界に興味のある人は、ぜひチャレンジしてみてください。