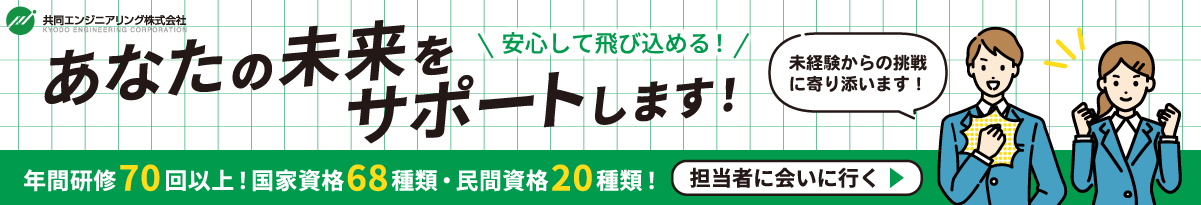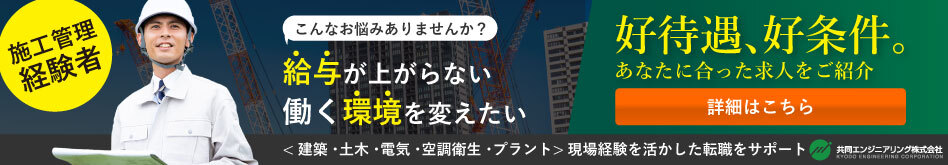目次
二級建築士の受験資格

二級建築士試験の受験資格は、建築士法第15条に基づき、建築に関する学歴や資格(以後、学歴要件とする)に応じて必要な実務経験の年数が定められています。下記は、二級建築士試験を受けるための要件です。
建築に関する学歴や資格など | 実務経験年数(試験時) |
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校などにおいて、指定科目を修めて卒業した者 | 最短0年 |
建築設備士 | 0年 |
その他都道府県知事が特に認める者(外国大学を卒業した者など) | 所定の年数以上 |
建築に関する学歴なし | 7年以上 |
なお、学歴要件を満たしている方は、実務経験がなくても受験できます。下記で受験資格について詳しく紹介します。
大学や専門学校などで建築関連の指定科目を履修する
学歴要件にある「指定科目」とは、国土交通大臣が指定する建築に関する科目のことです。建築やデザイン、土木系の学科で履修できます。二級建築士試験を受験するには、指定科目を所定の単位数履修する必要があります。
下記は、大学、短期大学、高等専門学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校における指定科目と単位数です。
科目 | 単位数 | ||
1.建築設計製図 | 3単位 | ||
2.建築計画 | 2単位 | ||
3.建築環境工学 | |||
4.建築設備 | |||
5.構造力学 | 3単位 | ||
6.建築一般構造 | |||
7.建築材料 | |||
8.建築生産 | 1単位 | ||
9.建築法規 | 1単位 | ||
1~9の合計 | 10単位 | ||
10.複合・関連科目 | 適宜 | ||
1~9+10の合計 | 40単位 | 30単位 | 20単位 |
受験資格(必要となる建築実務の経験年数) | 卒業後0年 | ||
免許登録資格(必要となる建築実務の経験年数) | 卒業後0年 | 卒業後1年 | 卒業後2年 |
なお、高等学校や専修学校などでは必要となる単位数が異なります。詳細は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」の公式サイトにて確認してみてください。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「二級建築士・木造建築士の受験・免許登録時の必要単位数(学校種類別)」
7年間の実務経験を積む
二級建築士試験を受験するには、建築関連の学歴や指定科目の履修が必要です。しかし、学歴要件を満たしていない場合でも、実務経験を7年以上積むことで受験資格を得ることが可能です。この実務経験要件は、令和2年の建築士法改正により、その対象範囲が大きく拡大されました。
改正以前は、建築士の実務経験として認められる業務が設計や工事監理などに限定されていました。しかし、改正後は建築物に関する調査や評価なども実務経験として認められるようになり、受験資格取得のための道が広がりました。
一方で、実務経験を証明するための書類提出がより厳格化された点に留意が必要です。試験申し込み時には、従来よりも詳細な業務内容や実績を記載した新様式の実務経歴書および実務経験証明書を提出する必要があります。
二級建築士の受験資格を得るために必要な実務経験

下記は、二級建築士試験を受験するために必要な実務経験です。
・建築物の設計に関する実務
・建築物の工事監理に関する実務【工事監理者の立場の実務】
・建築工事の指導監督に関する実務
・建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務
・建築工事の施工の技術上の管理に関する実務【工事施工者の立場の実務】
・建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査などに関する実務【建築主事または指定確認検査機関の立場の実務】
・消防長または消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
・建築行政に関する実務
・住宅行政に関する実務
・都市計画行政に関する実務
・建築教育に関する実務
・建築物に係る研究開発に関する実務
・大学院の課程におけるインターンシップ
・その他(既存建築物の利活用検討又は維持保全計画策定の業務、営業関連業務、建築に関する知識を必要とする図書、雑誌の編集など)
本項では、実務経験を積める職場や実務経験をカウントする際の注意点について解説します。
実務経験を積める職場
二級建築士試験を受験するための実務経験を積める職場は、主に3つです。下記では、それぞれの職場の特徴について解説します。
〇ゼネコン
ゼネコン(総合建設業者)は、建築工事の元請業者として、さまざまな業者と協力しながら工事全体を統括する役割を担っています。特に、ゼネコンが主に携わる建築一式工事の監理は、実務経験の項目として正式に認められています。
そのため、ゼネコンの設計部門や建築部門に所属し、設計業務や工事監理に直接関わることで、必要な実務経験を積むことが可能です。
〇設計事務所
設計事務所は、建築設計や工事管理などを主な業務とする職場です。設計事務所では、建築物の設計図や施工図の作成に携わる機会が多く、図面作成スキルや建築基準法の知識を深められます。
また、建築士の設計業務や工事監理業務の補助を通じて、建築プロジェクトの全体像を把握しながら実務経験を積むことが可能です。
〇ハウスメーカー
ハウスメーカーは、主に戸建て住宅の企画、設計、施工監理、販売をしている企業です。大手ハウスメーカーに就職・転職する場合は、建築に密接に関わる部門である「設計部門」「工事監理部門」「積算部門」に所属しましょう。
実務経験をカウントする際の注意点
令和2年の建築士法の改正によって、二級建築士試験の実務経験要件の範囲が拡大されました。新たに追加された実務は、施工日(令和2年3月1日)以降に実施してカウントされます。 したがって、新たに追加された実務を施工日前に実施していても、実務経験としてカウントされない点に注意が必要です。
二級建築士の試験概要

二級建築士試験には、学科と設計製図の2種類の試験区分があります。下記では、それぞれの出題形式や試験時間など、試験の概要を紹介します。
学科試験
下記は、二級建築士試験における学科試験の概要です。
・出題形式:五肢択一式(マークシート方式)
・詳細科目:学科I(建築計画)、学科II(建築法規)、学科III(建築構造)、学科IV(建築施工)
・出題数:100問
・試験時間:学科Iと学科IIで3時間、学科IIIと学科IVで3時間、合計して6時間
設計製図試験
下記は、設計製図の試験概要です。
・出題形式:事前に公表する課題の建築物について、条件に沿って設計図書を作成する
・詳細科目:設計製図
・出題数:1課題
・試験時間:5時間
設計製図の試験では、法令を遵守し、課題に沿った建築物を設計できる製図スキルが求められます。なお、過去の課題は下記の通りです。
・令和4年:保育所(木造)
・令和5年:専用住宅(木造)
・令和6年:観光客向けのゲストハウス(簡易宿所)(鉄筋コンクリート造)
最短で二級建築士になる方法
下記は、最短で二級建築士になる方法です。
1.大学、短期大学、高等専門学校などで指定科目を修めて卒業する
2.資格試験を受験して合格する
3.免許を取得する
二級建築士試験の受験資格には一定の学歴要件がありますが、大学や短期大学などで指定科目を修めて卒業していれば、実務経験がなくても免許を取得できます。
ただし、免許取得に必要となる実務経験は最終学歴によっても異なります。高校や中学校が最終学歴の場合、2年以上の実務経験が必要です。
まとめ
二級建築士試験の受験資格は、建築士法第15条に基づき、建築に関する学歴や資格に応じて必要な実務経験の年数が定められています。建築関連の学歴や指定科目の履修があれば、実務経験がなくても二級建築士の試験を受けられ、免許を取得可能です。建築関連の学歴がない場合は、建築実務が7年以上必要です。
二級建築士を取得したいものの、実務経験がなくて困っている方は、ぜひ「BREXA Engineering」へご相談ください。「BREXA Engineering」は、国内外に豊富な実績をもつ建設コンサルティング企業です。幅広い求職者と面接しており、経験の有無や職種を問わず募集しています。
面接では、お話ししやすい雰囲気づくりを心がけており、求職者のキャリアビジョンを丁寧にヒアリングしています。充実した研修制度を用意しており、未経験でも着実にスキルアップが可能です。国家資格取得も支援しているので、二級建築士試験を受験したい方は、ぜひご応募ください。