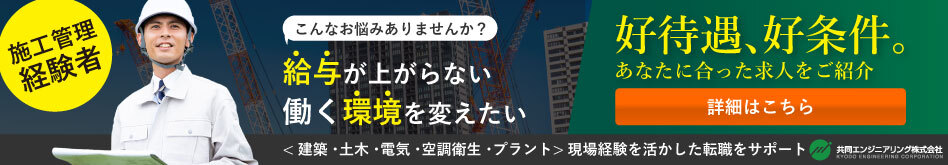目次
一級建築士の難易度・合格率

一級建築士の資格を取得するには、「学科の試験」と「設計製図の試験」の両方に合格する必要があります。難易度・合格率は下記の通りです。
【総合合格率】
一級建築士の平均合格率(令和2年から令和6年までの5年間)は、9.82%です。つまり、受験者の約9割が不合格の難易度の高い試験であるといえます。
・令和2年:10.6%
・令和3年:9.9%
・令和4年:9.9%
・令和5年:9.9%
・令和6年:8.8%
【学科】
学科試験は、毎年約28,000~30,000人が受験しています。令和2年から令和6年までの5年間の平均合格率は、19.28%です。
・令和2年:20.7%
・令和3年:15.2%
・令和4年:21.0%
・令和5年:16.2%
・令和6年:23.3%
【製図】
設計製図の試験は、毎年約10,000人が受験しています。平均合格率は32.62%で、学科試験と比べると合格率は高めです。しかし、難関な学科試験を突破した方でも半数以上が落ちる試験であることから、高難度であるといえるでしょう。
・令和2年:34.4%
・令和3年:35.9%
・令和4年:33.0%
・令和5年:33.2%
・令和6年:26.6%
出典:建築技術教育普及センター「直近5年間の試験結果」
一級建築士の難易度が高い理由
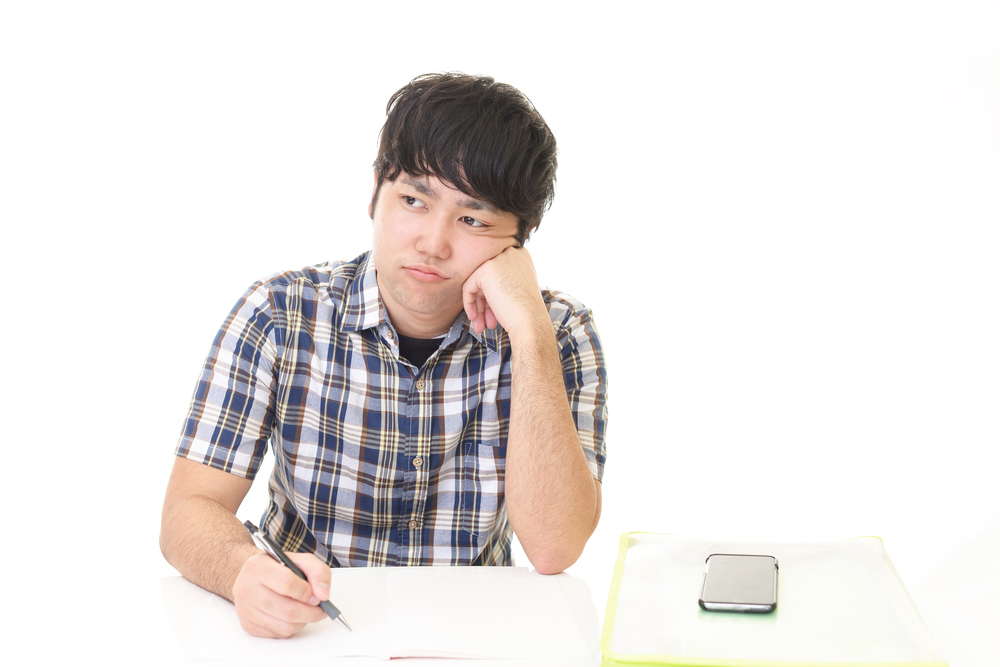
一級建築士試験に合格するためには、なぜ難易度が高い試験であるかを理解することが大事です。難易度の高さを理解することは、学習時間を適切に見積もり、必要な準備を整えるために欠かせません。下記では、一級建築士の難易度が高い理由を3つ紹介します。
試験の出題範囲が広いから
学科試験は、下記の5科目から出題されます。
・学科Ⅰ(計画)
・学科Ⅱ(環境・設備)
・学科Ⅲ(法規)
・学科Ⅳ(構造)
・学科Ⅴ(施工)
出題範囲が広いと、カバーすべき知識が膨大になります。学科試験で出題される5科目すべてに均等に時間を割く必要があり、効率的に学習を進めなければなりません。限られた時間の中で優先順位をつけ、得意分野を強化しつつ苦手分野を補う戦略的な学習が必要です。
また、試験当日も時間配分や問題選択の判断力が問われるため、事前のシミュレーションや過去問演習を繰り返す必要があります。
モチベーションの維持が大変だから
一級建築士試験は年に一度しか実施されず、長期間にわたる学習と準備が必要なことから、モチベーションを維持するのが困難です。
まず、一級建築士試験は学科試験と設計製図試験の2段階構成です。学科試験は例年7月第4日曜日に実施され、これに合格しなければ同年10月第2日曜日に行われる設計製図試験を受験できません。
学科試験に合格しても、その後すぐに設計製図試験に向けての学習を続ける必要があり、トータルで約半年以上の勉強期間が求められます。このように長期間にわたり高い集中力を保つ必要があるため、途中でモチベーションが低下する受験者も多くいます。
さらに、試験問題の難易度が高いため、学習には多大な労力と時間が必要です。特に学科試験では広範な分野をカバーしなければなりません。1つの分野に集中しすぎると、ほかの分野の対策が疎かになり、全体的なバランスを保つことが難しくなります。
法改正などにより資格試験の内容が変化するから
一級建築士試験では、建築基準法をはじめとする法規関連の知識が重要視されますが、これらの法律は社会情勢や技術の進化に合わせて定期的に改正されるため、最新の情報を常に把握する必要があります。古い参考書や過去問を中心に勉強を進める場合は注意しましょう。
一級建築士に合格するための勉強方法

下記では、効率的な勉強方法を学科と設計製図に分けて紹介します。
学科試験の勉強方法
学科試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に1,000時間程度といわれています。つまり、1年で取得を目指す場合、1日3時間程度の勉強時間が必要です。その点を踏まえて、下記で紹介する勉強方法を参考にしてみてください。
スケジュールを立てる
勉強を始める前に、試験日から逆算して学習スケジュールを立てることが大切です。特に学科試験は出題範囲が広く、各科目の配点や難易度に違いがあるため、効率的に勉強を進めるためにも入念な計画が欠かせません。
一級建築士試験の学科試験には5科目ありますが、配点が多い科目から勉強を進めると良いでしょう。具体的には、下記の順序から始めるのがおすすめです。
1.法規
2.構造
3.環境・設備、施工
4.計画
【法規】
法規は配点が高いことや、試験で法令集を持ち込みできることから、高得点が狙える科目です。ただし、法令集の内容は膨大で、新しい法律が施行されることもあるため、長期的な学習計画が欠かせません。
【構造】
構造は計算問題が多く、苦手意識を持つ受験者が多い科目です。しかし、公式や解き方を一度理解すれば安定して得点を取れるため、学習初期から計算練習を積み重ねましょう。
【環境・設備】および【施工】
環境・設備は計算問題が中心ですが、公式さえ覚えれば短期間で得点力を高めやすい科目です。施工は暗記事項が多いため、単語カードや表などを活用した暗記法を活用すると良いでしょう。
【計画】
計画は内容が比較的理解しやすく、暗記中心の学習で対応できます。出題範囲が広いため、スキマ時間を活用して少しずつ知識を積み重ねる学習法が効果的です。建築史や話題になった建築作品など、出題される可能性のあるトピックも押さえておきましょう。
過去問を解く
一級建築士試験では、過去問と似た問題が出題されることも少なくありません。そのため、過去問を繰り返し解くことで、よく問われる内容や問題形式に慣れ、試験の傾向をつかめるようになります。
また、問題を解く過程で、自分の苦手分野を洗い出すことが可能です。苦手分野に集中して取り組むことで、安定して点数が取れるようになります。ほかにも、過去問を繰り返し解くことで、解答の手順やコツを身につけ、スピーディーかつ正確に解く力を養える点もメリットです。
過去問は建築技術教育普及センターの公式サイトでダウンロードできるため、ぜひ取り組んでみてください。
出典:建築技術教育普及センター「過去の試験問題等」
苦手科目をなくす
一級建築士試験の学科試験では、科目ごとに基準点を満たすことが合格の条件とされています。つまり、1科目でも基準点に達しなければ不合格となってしまうため、苦手科目を克服しなくてはなりません。
苦手科目を克服するためには、まず「どこが苦手なのか」を分析する必要があります。過去問を解き、苦手な科目や問題を洗い出しましょう。
設計製図の勉強方法
学科試験に合格した後は、3か月後の設計製図の試験に向けて勉強を進めます。設計製図の試験に必要な勉強時間には個人差がありますが、一般的には平日1日2時間、土日で合計12時間程度が目安です。下記では、設計製図の勉強方法やポイントについて解説します。
製図スピードを上げる
設計製図の試験は6時間半という長時間にわたるものですが、製図だけに集中できるわけではありません。エスキス(設計の構想)や要点記述、最終チェックにも時間を割く必要があるため、製図にかけられる時間は限られています。制限時間内に製図を完成させるためには、効率的な作業とスピードアップが不可欠です。
まずは設計製図の試験における時間配分を決めましょう。推奨される時間配分は、下記の通りです。
・製図:3時間
・エスキス:2時間
・要点記述:1時間
・見直し:30分
製図スピードを上げるには、実践形式の練習を重ねるのが効果的です。本番と同じ時間配分を設定し、時間内に製図を完成させる練習を繰り返しましょう。
課題文を正確に読む練習をする
設計製図の試験では、課題文に記載された条件や要件を的確に把握し、それに基づいたプランニングと製図を進める必要があります。課題文を正確に読み取るスキルを身につければ、各項目の重要度が判断でき、「何を取り入れ、何を捨てるのか」を素早く決定して効率的に作業を進めることが可能です。
添削サービスを利用する
自己流での学習に限界を感じた場合は、添削サービスを利用するのがおすすめです。添削サービスでは、経験豊富な講師やプロの建築士から客観的な評価を受けられます。自分では気づかない設計の欠陥や表現ミスを指摘してもらえるため、より完成度の高い図面を作成できるようになります。
また、資格学校で模擬試験を受けるのも良いでしょう。本番と同じ時間設定や試験形式での練習によって、試験当日の流れに慣れることが可能です。ただし、費用がかかる点には注意が必要です。
まとめ
一級建築士の資格を取得するには、学科試験と設計製図の試験の両方に合格する必要があります。令和6年の学科試験の合格率は23.3%、設計製図の試験は26.6%、総合合格率は8.8%と、難易度の高い試験であるため、十分な対策をして臨みましょう。
「建設関連の資格取得を目指している」「未経験だけど建設業で働きたい」といった方は、BREXA Engineeringへご相談ください。BREXA Engineeringは建設コンサルティング企業であり、経験の有無や職種を問わず建設業で転職・働きたい方を募集しています。
面接では、求職者のキャリアビジョンや理想を丁寧にヒアリングし、条件にぴったりの職場を紹介しています。国家資格取得のサポートや研修制度も充実しているので、安心してご応募ください。