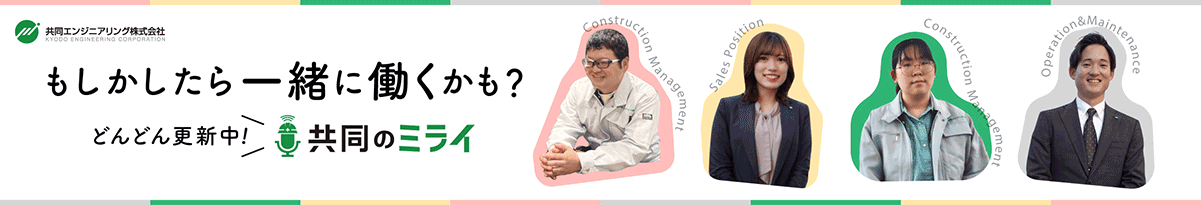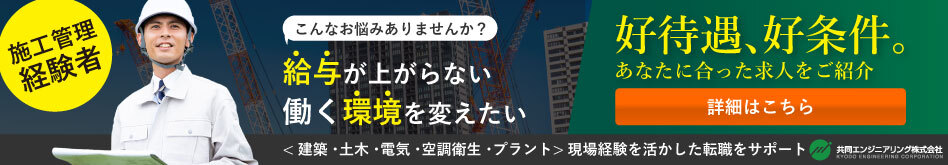目次
エネルギー管理士とは?

エネルギー管理士とは、省エネ法の制定にともない定められた国家資格です。工場などでエネルギーを効率的に使用することを目的としています。多量のエネルギーを使用する工場において省エネは大きな課題であり、エネルギー管理士はエネルギー使用方法の改善・管理をします。
主な仕事内容は下記の通りです。
・エネルギー管理標準の作成業務
・管理標準に従った設備の管理と計画の実行
・エネルギーの管理 ・報告書の作成
・中長期計画書の作成
製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業の5業種の工場において、熱・電気の年間使用量が一定以上ある場合は「第一種エネルギー管理指定工場」に指定されます。指定工場ではエネルギーの使用量に応じて、エネルギー管理士を1〜4人配置しなければなりません。
指定工場におけるエネルギー管理者は有資格者でないとできない業務であり、独占業務になります。政府による省エネが推進されていることも相まって、将来性のある資格といえるでしょう。
エネルギー管理士に向いている人の特徴
 エネルギー管理士に向いている人には、下記で紹介する特徴があります。あてはまる方は、エネルギー管理士への転職や資格取得によるキャリアアップを成功させられる可能性が高いでしょう。
エネルギー管理士に向いている人には、下記で紹介する特徴があります。あてはまる方は、エネルギー管理士への転職や資格取得によるキャリアアップを成功させられる可能性が高いでしょう。
理工系の知識がある人
エネルギー管理士の試験には、学歴などの制限はありませんが、専門区分として「熱分野」「電気分野」のどちらかを選択して受験しなければなりません。理系出身の方なら、知識を活かして勉強をスムーズに進められるので、向いているといえます。
文系出身の方もエネルギー管理士として活躍可能ですが、理系知識や関連業務経験がない場合、資格取得のための勉強に時間を要する可能性があります。
広い視野を持っている人
エネルギー管理士は細かな数値を扱うことも多くありますが、あらゆる視点からものごとを捉えられる、広い視野を持つ人が向いています。
具体的なデータから、企業が過剰に使用したエネルギー量の原因などを把握するためには、その背景や相関関係を見抜く必要があるためです。
また、中長期的な改善計画の立案にも、将来を見据えられる広い視野が求められます。
常に一歩先をイメージして行動できる人
エネルギー管理士は、エネルギーを使用する設備の管理や監視を通じてエネルギーの合理的な使用を促し、将来の環境や生活を守る重要な役割を担います。
そのためには、現在の使用状況を管理するだけでなく、新たなエネルギー技術の導入、再生可能エネルギーの普及に対する高い意識も求められます。
常に一歩先をイメージして行動や計画に落とし込める人はエネルギー管理士の適性があるといえるでしょう。
計画を立てるのが得意な人
エネルギー管理士の仕事の中には、企業のエネルギー使用に関する各種計画の立案や、計画書作成業務があります。
これらの業務には、課題解決力や期限までの遂行力、将来を見通す力などが必要です。また、エネルギーに関する重要な改善提案を行う際には、上層部などを納得させられるだけの説得力も求められます。
日常的に計画を立ててものごとを実現することが得意な人や好きな人は、その能力を業務に活かせるでしょう。
マネジメントや管理が得意な人
エネルギー管理の主な業務は、企業のエネルギーの合理的使用を監督することです。現場作業よりもマネジメント業務を得意とする人に向いている傾向があります。
また、省エネ計画の策定においては、法令遵守とともに関係部署からの情報収集や調整を行わなければならないこともあります。この点でも、高いマネジメント力が求められるといえます。
エネルギー管理士の将来性は?
 エネルギーの年間使用量が原油換算年間3,000キロリットル以上の工場のうち、製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)では、エネルギー管理士の配置が必須です。
エネルギーの年間使用量が原油換算年間3,000キロリットル以上の工場のうち、製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)では、エネルギー管理士の配置が必須です。
そのため、エネルギー管理士は、自動車工場や電子機器工場、化粧品工場、食品工場などで需要があります。
近年では太陽光発電をはじめ、さまざまな発電設備の開発が進んでおり、今後とも電気供給業において需要が増加する可能性が高いでしょう。
また、省エネ対応が重要視されるなか、製造業以外での需要も高まっており、幅広い分野にて高い将来性が期待できます。
エネルギー管理士の資格を取得するメリット
ここからは、エネルギー管理士を取得する二つのメリットについて紹介します。
電力・エネルギー会社への転職が有利になる
エネルギー管理士は社会的なニーズが高く、電力・エネルギー会社への転職に有利です。エネルギー政策で省エネが推進されている限り、需要がなくなることはありません。
また近年では、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)やネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)といった省エネ設備・建物が登場しています。
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスとは、年間の消費エネルギー量を実質的にゼロ以下にする家のことを指します。一方、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルは、室内環境の快適さを実現しつつ、1年間における一次エネルギーの収支ゼロを目的とした建物のことです。
エネルギー管理士はこのような設備・建物を維持管理するために需要が高まると考えられます。
エネルギー管理士の有資格者が応募条件の求人は少なくありません。新しいエネルギー設備の登場で需要は今まで以上に高まるため、安定的に仕事を受けられることもメリットです。
年収アップが期待できる
エネルギー管理士の資格保有者の平均年収は500〜600万程度です。さらなる需要が見込まれることからも、キャリアを積めば1000万円も狙えるでしょう。また、エネルギー管理士の保有者に資格手当や現場手当を支給する会社も少なくありません。
エネルギー管理士を取得したからといって年収が1000万になるわけではありません。転職する企業やそのほかの条件がかけ合わさることで高収入につながることも理解しておきましょう。
エネルギー管理士の受験資格や試験課目について
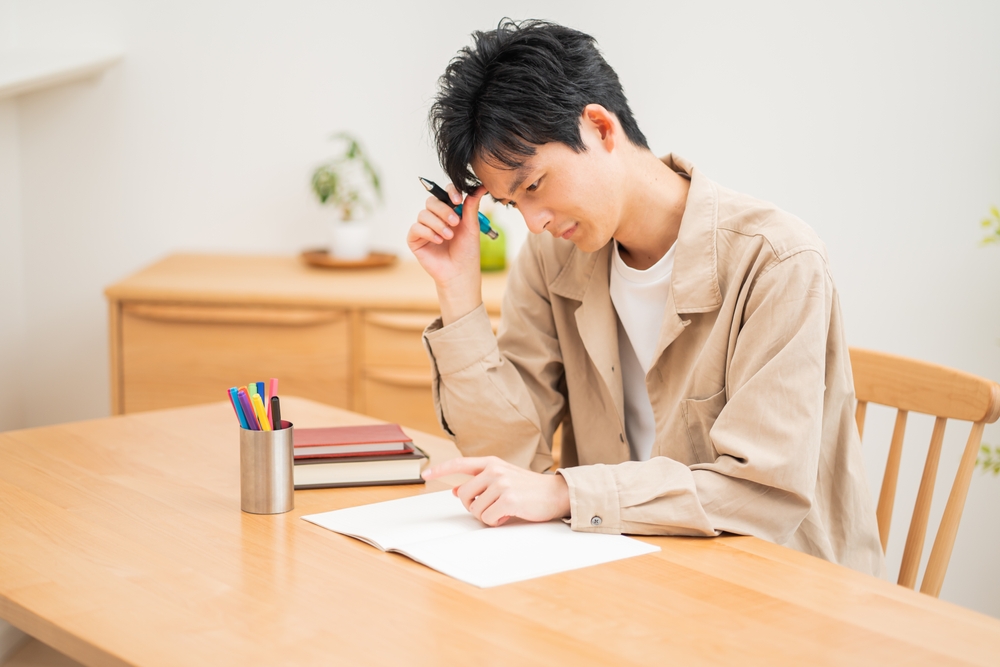
エネルギー管理士を取得するためには「国家試験に合格する方法」と「実務試験+研修を受ける方法」のふたつです。ここでは、国家試験の概要について紹介します。
エネルギー管理士試験の受験資格
エネルギー管理士試験を受けるための受験資格は特にありません。基本的には誰でも受験できますが、免許取得・登録には1年以上の実務経験が必要です。この実務経験は、試験に合格してから積むケースでも問題ありません。
また、実務経験が3年以上なら、7日間の認定研修「エネルギー管理研修」を受講して修了試験に合格することで、免許取得が可能です。この場合、国家試験を受験する必要はありません。
エネルギー管理士の試験課目
試験課目は、必須基礎のほか、選択可能な「熱分野」と「電気分野」があります。どちらを選択しても合格後の資格内容は変わりません。
区分 | 課目 | 内容 | 時間配分 |
必須基礎 | エネルギー総合管理及び法規 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令、エネルギーの総合管理 | 80分 |
熱分野 | 熱と流体の流れの基礎 | 熱力学の基礎、流体工学の基礎、電熱工学の基礎 | 110分 |
熱利用設備及びその管理 | 燃料及び燃焼管理、燃焼計算 | 110分 | |
燃料と燃焼 | 計測及び制御、熱利用設備 | 80分 | |
電気分野 | 電気設備及び機器 | 電気及び電子理論、自動制御及び情報処理、電気計測 | 110分 |
電力応用 | 工場配電、電気機器 | 110分 | |
電気の基礎 | 電動力応用、電気加熱、電気化学、照明、空気調和 | 80分 |
なお、課目ごとに合否が出るようになっています。受験年から4年以内に再受験する場合は、すでに合格した課目は免除される仕組みです。
エネルギー管理士の試験形式
エネルギー管理士の試験は、マークシート方式の筆記試験で行われます。筆記用具はHBの鉛筆もしくはシャープペンシルの使用が義務付けられています。そのほか、時計や電卓などの持ち込みも許可されていますが、細かくルールがあるため注意が必要です。
受験に当たっての注意事項が気になる方は、試験前に「受験に当たっての注意事項」(一般財団法人 省エネルギーセンター)をお読みください。
エネルギー管理士の難易度は高い!合格率は?
エネルギー管理士試験の過去4年間における合格率は下記のようになっています。
出典:
一般社団法人全国エネルギー管理士連盟「エネルギー管理士情報」
一般財団法人省エネルギーセンター「第47回エネルギー管理研修 修了者発表(合格発表)」
| 国家試験 | 研修試験 |
令和6年度 | 37.0% | 51.7% |
令和5年度 | 37.8% | 67.1% |
令和4年度 | 33.9% | 61.3% |
令和3年度 | 31.9% | 61.2% |
国家試験の合格率は約30%と低く、難易度の高い資格であることがわかります。また、研修試験の合格率は60%前後と高い傾向にあります。研修の受講には3年以上の実務経験や技術的素養が必要であり、誰もが挑戦できる国家試験の受験者と比べて、受講者のレベルは平均的に高めです。
エネルギー管理士の資格を取る勉強は最短で100時間、期間にして3〜6か月必要といわれています。未経験で理数系が苦手な人は、1〜3年をかけて取得することもあります。
エネルギー管理士試験の勉強方法は?
エネルギー管理士の国家試験を受けるに当たって、どのように勉強を進めれば良いのか悩んでいる方も少なくないでしょう。ここでは、課目ごとに合った勉強方法を紹介します。
まず、エネルギー管理士の勉強で注意したいのは、課目Ⅰから始めないことです。出題範囲が膨大であるため、課目Ⅰから始めると挫折する可能性があります。ここでは、おすすめの勉強順で解説します。
課目Ⅱの対策
課目Ⅱは「熱力学」「流体工学」「伝熱工学」の基礎が主な出題範囲となっています。計算問題がメインとなるため、公式を理解したうえで、過去問を繰り返し演習しましょう。
課目Ⅳの対策
課目Ⅳは「計測方法」「自動制御」「熱利用設備」が主な出題範囲となっています。「計測方法」「自動制御」に関しては暗記すれば問題ありません。「熱利用設備」は、課目Ⅱの内容を理解している必要があります。課目Ⅳの前に課目Ⅱから学習するようにしましょう。
課目Ⅰの対策
課目Ⅰは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令」「エネルギーの総合管理」が主な出題範囲となっています。課目Ⅰ〜Ⅳの基礎問題となっており、ほとんどが暗記です。基本的には、毎年出題される傾向が決まっています。そのため、合格を目的とした対策をするのであれば、過去に出題された問題を解くことで、合格点に必要な知識は身につけられます。
課目Ⅲの対策
課目Ⅲは「燃料および燃焼管理」「燃焼計算」が主な出題範囲となっています。「燃料および燃焼管理」に関しては、ひたすら暗記していくだけです。「燃焼計算」は高校レベルの化学で習う熱化学方程式が理解できていれば問題ないでしょう。燃焼計算は課目Ⅲのなかでも配点が高くなっていますが、計算パターンが決まっているため、過去問を解いていけば大丈夫です。
まとめ
省エネの専門家でもあるエネルギー管理士は、将来的にも需要の高い資格です。有資格者を求めている企業も数多く存在するため、転職やキャリアアップに有利でしょう。比較的難易度の高い試験ですが、課目ごとにしっかりと対策をしていけば合格するチャンスは十分にあります。