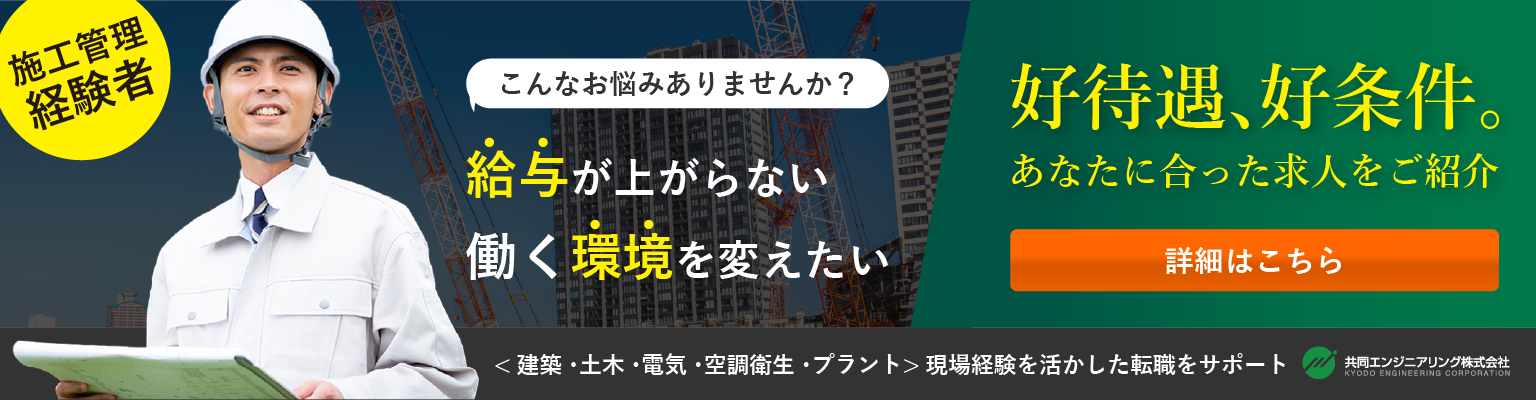目次
2級建設機械施工管理技士とは

2級建設機械施工管理技士は、大小さまざまな建設機械の運転操作のほか、主任技術者として施工管理も担えます。建設機械施工管理技士には1級と2級があり、どちらも国土交通大臣指定機関が実施する国家資格です。
まずは、仕事内容や1級建設機械施工管理技士との違いを解説します。
仕事内容
建設機械による施工を円滑に進めるため、2級建設機械施工管理技士は、安全、品質、工程、コストの管理のほか、工事計画の策定、安全書類の作成などを担います。建設機械施工管理技士として乗れる機械は、受検科目で選択した種別の建設機械のみです。
検定に合格した後は、受検科目の種別に応じた「事業所内特定自主検査者」の資格取得、または講習科目の一部免除も受けられることから、建設機械の検査にも携われます。
1級建設機械施工管理技士との違い
1級と2級では、担当できる工事の種類が違います。工事の種類が限定される2級に対して、1級を取得すると下請発注額にかかわらず、すべての工事に対応できます。
また、扱える建設機械も両者で違います。1級は、第1種~第6種の建設機械すべての運転操作と検査を担えます。
そのほか、1級には監理技術者の資格が与えられます。監理技術者は、下請発注額の合計が4,500万円以上の工事(建築一式工事の場合は7,000万円以上)で下請負人を指導、監督する職務です。主任技術者よりも高度な知識や経験が求められます。
受検資格も異なります。第一次検定の受検資格は、2級が満17歳以上、1級が満19歳以上です。第二次検定の受検資格も、実務経験をはじめとする要件に違いがあります。
2級建設機械施工管理技士が乗れる機械

2級建設機械施工管理技士の試験に合格すると、次の6種別のうち、選択した種別の建設機械を主任技術者として扱えます。
種別 | 機械名 |
第1種 | ・ブルドーザー |
第2種 | ・パワー・ショベル |
第3種 | ・モーター・グレーダー |
第4種 | ・ロード・ローラー |
第5種 | ・アスファルト・プラント |
第6種 | ・くい打機 |
なお、検定試験を受検する際は、最大2つの種別を選択できます。その場合、奇数種別と偶数種別から1つずつ選択しなければなりません。
2級建設機械施工管理技士を取得するメリット
2級建設機械施工管理技士のメリットは、大型建設機械を扱えるだけではありません。次に、2級建設機械施工管理技士の資格を取得する2つのメリットを紹介します。
仕事の幅が広がる
2級建設機械施工管理技士の資格を保有していれば、一般建築業と特定建設業のうち、下請発注額が4,500万円未満の下記の工事において、主任技術者の職務を担えます。
・土木(一式)工事
・とび/土工/コンクリート工事
・舗装工事
主任技術者は、鉄筋工事、型枠工事のうち下請金額が4,000万円未満の場合を除き、建設業法で配置が義務付けられています。また、複数の種別で資格を取得すれば、さらに仕事の幅を広げられるでしょう。
2級よりも活躍の場が増える1級建設機械施工管理技士へのステップアップにもなります。
転職が有利になる
建設機械施工管理技士は、建設工事で必要となる技術力と経験を証明できる国家資格です。主任技術者の要件にもなっていることから、2級建設機械施工管理技士の資格を保有していれば、建設業の転職市場でも一定の需要が見込めます。
また、企業によっては資格手当も支給されるほか、昇進、昇給の要件になる場合もあります。
2級建設機械施工管理技士の試験概要

ここからは、検定試験の内容や受検資格、受検手数料を解説します。試験概要を事前に把握して、計画的に学習を進めましょう。なお、本記事で記載している情報は2025年1月時点のものです。最新の情報を知りたい方は、公式サイトからご確認ください。
出典:一般社団法人日本建設機械施工協会「1・2級建設機械施工管理技術検定試験」
第一次検定の選択問題や第二次検定の実技試験では、下記から選択する種別の科目で出題されます。
種別 | 科目 |
第1種 | トラクター系建設機械 |
第2種 | ショベル系建設機械 |
第3種 | モーター・グレーダー |
第4種 | 締め固め建設機械 |
第5種 | 舗装用建設機械 |
第6種 | 基礎工事用建設機械 |
早速、詳細をみていきましょう。
試験内容
まずは試験内容を紹介します。
第一次検定
第一次検定は、共通問題、選択問題ともに四択のマークシート記入方式です。共通問題では、32問のうち25問解答します。
【共通問題】
科目 | 出題内容 |
土木工学 | 建設機械による建設工事の施工管理を適確に行うために必要な土木工学に関する概略の知識、設計図書を正確に読み取るための知識 |
施工管理法 | 建設機械による建設工事の施工管理を適確に行うために求められる基礎的な能力のほか、施工計画の作成方法、工程管理、品質管理、安全管理など、施工管理の方法に関する基礎的な知識 |
建設機械原動機 | 建設機械の内燃機関の構造、機能、運転、取り扱い、衰損、故障、不調の原因並びに対策に関する概略的な知識 |
石油燃料 | 石油燃料の種類、用途、取り扱いについての概略的な知識 |
潤滑剤 | 潤滑剤の種類、用途、取り扱いに関する概略的な知識 |
法規 | 建設工事の施工管理を適確に行うために必要な法令に関する概略的な知識 |
選択問題は、種別に科目が設定されます。20問必答です。
【選択問題】
種別 | 科目 | 出題内容 |
第1種 | ・トラクター系建設機械 | ・トラクター系建設機械の構造、機能、運転、取り扱い、衰損、故障、不調の原因及び対策、施工方法、施工能力の測定に関する一般的な知識 |
第2種 | ・ショベル系建設機械 | ・ショベル系建設機械の構造、機能、運転、取り扱い、衰損、故障、不調の原因と対策、施工方法、施工能力の測定に関する一般的な知識 |
第3種 | ・モーター・グレーダー | ・モーター・グレーダーの構造、機能、運転、取り扱い、衰損、故障、不調の原因と対策、施工方法、施工能力の測定に関する一般的な知識 |
第4種 | ・締め固め建設機械 | ・締め固め建設機械の構造、機能、運転、取り扱い、衰損、故障、不調の原因並びに対策、施工方法、施工能力の測定に関する一般的な知識 |
第5種 | ・舗装用建設機械 | ・舗装用建設機械の構造、機能、運転、取り扱い、衰損、故障、不調の原因並びに対策、施工方法、施工能力の測定に関する一般的な知識 |
第6種 | ・基礎工事用建設機械 | ・基礎工事用建設機械の構造、機能、運転、取り扱い、衰損、故障、不調の原因と対策、施工方法、施工能力の測定に関する一般的な知識 |
第二次検定
第二次検定では、共通の筆記試験と種別の実技試験が行われます。
筆記試験では、「施工管理法」について出題されます。四択のマークシート記入方式で、10問必答です。建設工事の施工管理や施工計画の作成、施工計画に基づく施工方法、並びに手順の選定など、主任技術者に必要な知識と能力が問われます。
実技試験では、下記の種別で実際に建設機械を操作して合否を判定します。
種別 | 科目 |
第1種 | トラクター系建設機械操作施工法 |
第2種 | ショベル系建設機械操作施工法 |
第3種 | モーター・グレーダー操作施工法 |
第4種 | 締め固め建設機械操作施工法 |
第5種 | 舗装用建設機械操作施工法 |
第6種 | 基礎工事用建設機械操作施工法 |
受検資格
次にそれぞれの受検資格をみていきましょう。
第一次検定
受検年度に満17歳以上となる方に受検資格が与えられます。実務経験は不問です。
第二次検定
第二次検定の受検資格は、次のいずれかを満たす場合に限られます。なお、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業の建設機械施工に関連する実務経験のみが対象です。
(1)1級の第一次検定に合格後、受検種別で施工管理の実務経験が1年以上
(2)2級の第一次検定に合格後、受検種別で施工管理の実務経験が2年以上
(3)2級の第一次検定の合格者で、受検種別に関する建設機械を操作施工した実務経験(補助作業を含む)が6年以上
受検手数料
第一次検定、第二次検定の受検手数料は、それぞれ下記の通りです。
・第一次検定:14,700円(1種別につき)
・第二次検定:27,100円(1種別につき)
2級建設機械施工管理技士の合格率
令和6年度2級建設機械施工管理技術検定の第一次検定では、受検者数6,280人のうち2,616人が合格し、合格率41.7%という結果でした。合格基準は60%以上です。
令和6年度2級建設機械施工管理技術検定の第二次検定では、受検者数994人のうち515人が合格し、合格率は51.8%でした。筆記試験は60%以上、実技試験は70%以上の得点で合格基準に達します。
第二次検定の合格率は、近年減少傾向にあります。とはいえ、第一次検定で40%台、第二次検定で50%台の合格率は、他の国家資格と比較しても比較的高い水準といえるでしょう。
なお、本記事で記載している情報は2025年1月時点のものです。最新の情報を知りたい方は、公式サイトからご確認ください。
出典:一般社団法人日本建設機械施工協会「1・2級建設機械施工管理技術検定試験」
まとめ
2級建設機械施工管理技士の資格は、主任技術者の要件にもなっているため、建設業界でのキャリアアップを目指す方におすすめです。大型建設機械に乗れるだけでなく、施工管理をはじめとするより難易度の高い業務に携わるチャンスも広がります。
「BREXA Engineering」では、施工管理やCADオペレーター、O&M(オペレーション&メンテナンス)職などを募集しています。面接では、一人ひとりが求めるものや将来の理想をヒアリングし、多種多様な価値観やキャリアビジョンに寄り添った面接をいたしますので、お気軽にご相談ください。
また、資格取得支援制度(資格取得手当含む)によって、働きながらスキルアップを目指せる環境です。建設機械施工管理技士の資格を取得して、建設業界でキャリアアップを図りたい方は、ぜひご応募ください。