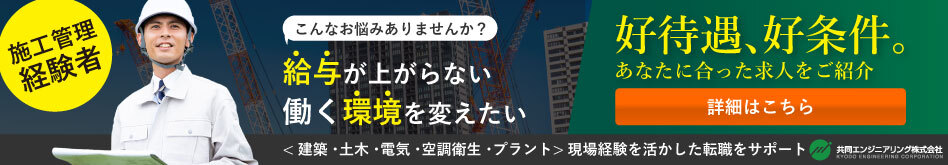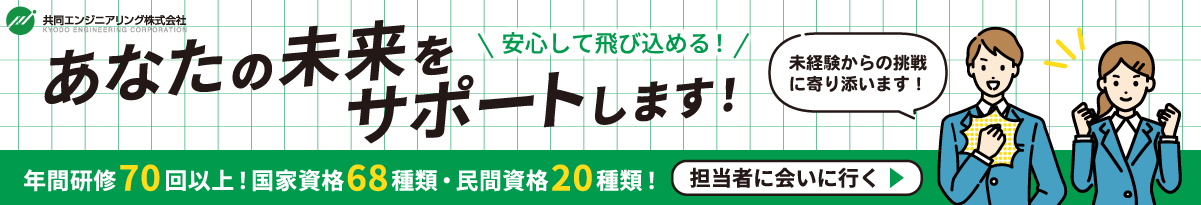RCCMとは?

RCCMは、建設コンサルタント(※)業務に関連する資格です。シビルコンサルティングマネージャ(Registered Civil Engineering Consulting Manager)の略称で、一般社団法人「建設コンサルタンツ協会」が認定する民間資格です。
RCCMは管理技術者や照査技術者、業務担当者になるために必要とされています。国土交通省が重要視する専門職としての知識と技術を有していることを証明できる資格です。
現在の土木工事は、環境保護や自然災害の対応といった要素も厳しく問われるため、RCCM資格保有者の役割は大きくなっています。近年は技術者不足が課題となっていることも相まって、RCCM資格保有者を積極的に採用する企業も増えていくと考えられます。
※建設コンサルタントとは、道路や河川をはじめとする社会資本を整備するために、調査計画や設計などの技術コンサルティングサービスを行うことです。
RCCMを取得するメリットとは?
RCCMは、建設コンサルタントをするために必要な資格です。取得することでさまざまなメリットを得られます。ここでは、RCCMを取得する3つのメリットを確認しましょう。
技術者として高く評価される
専門分野における知識・技術を有する技術者として高く評価されるのがメリットです。RCCMを取得すると、管理技術者や照査技術者として、全般的な安全管理や健康管理、福祉に対しての責任を担えます。土木工事に関わる専門職としての知識や技術をもった人材として認められるため、社内でも責任ある仕事を任せられるようになるでしょう。
年収アップが期待できる
RCCMを取得することで、年収アップも期待できます。建設コンサルタントの平均給与は月収40万円、年収は500万円程度です。建設業界では知識や技術力が重視される傾向にあり、資格取得によって年齢や性別に関係なく高収入が得られる可能性もあります。
そもそもRCCMを受検するためには、一定の実務経験年数が必要です。RCCMの受検までに、ほかの資格を取得している可能性も高く、給与交渉に活かせるでしょう。
転職・キャリアアップに有利
RCCMは建設コンサルタント業界では必須の資格となっています。建設業界全体で技術者が不足している背景もあり、RCCM取得者は転職・キャリアアップに有利です。RCCMの取得は専門分野の知識・技術力を有していることの証明でもあるため、即戦力としても期待されます。
RCCMは官公庁発注の土木設計業務において、受注競争の際に重視される資格です。建設業界での競争を勝ち抜くためにも、RCCMの有資格者を採用したい企業は少なくありません。
RCCMの受検資格や難易度について

ここからは、RCCMの受検資格や難易度など試験の概要について紹介します。
受検資格:一定の実務経験年数が必要
RCCMを受検するためには、一定の実務経験年数が求められます。受検資格として満たさなければならない実務経験年数は、下記のように学歴ごとに異なります。
・大学院修了者(修士課程/博士課程前期):5年以上
※大学院(修士課程/博士課程後期)は在学期間を実務経験年数とみなす
・大学卒業者:7年以上
・短期大学もしくは高等専門学校卒業者:9年以上
・高等学校卒業者:11年以上
・中学校卒業者:14年以上
実務経験年数とは、建設コンサルタント業務に従事または、これを管理した合計年数のことです。2019年から従来よりも実務経験年数は3年短縮されています。
試験内容と形式:試験Aと試験Bのふたつ
RCCMの試験は「RCCM試験A」と「RCCM試験B」のふたつで実施されます。「RCCM試験A」は問題Ⅰ・Ⅱを、「RCCM試験B」は問題Ⅲ・Ⅳを受検する仕組みです。
・問題Ⅰ:受検する専門技術部門の業務経験【記述式】
・問題Ⅱ:業務関連法制度、建設一般の知識、技術者倫理等【択一】
・問題Ⅲ:管理技術力【記述式】
・問題Ⅳ:土木関連の基礎的技術知識と受検する部門の専門技術知識【択一】
上記のように記述式と多肢択一式の問題が出され、CBTで実施します。CBTとは、コンピュータを利用した試験方式のことです。
合格率:4割程度
RCCM試験の過去4年間における合格率は下記のようになっています。
年度 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
令和5年 | 5,509 | 2,253 | 40.9% |
令和4年 | 5,451 | 2,626 | 48.2% |
令和3年 | 5,723 | 2,698 | 47.1% |
令和1年 | 5,659 | 2,371 | 41.9% |
平成30年 | 4,905 | 1,871 | 38.1% |
平成29年 | 5,571 | 2,312 | 41.5% |
引用元:一般社団法人 建設コンサルタンツ協会「RCCM資格試験の状況」
※令和2年度の試験は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止
過去4年間のデータを紐解くと、合格率は40%前後です。そもそも受検資格に一定の実務経験年数が求められるため、受検者のレベルは低くありません。合格率だけ見ると最難関の資格ではないものの、誰でも簡単に合格する試験ではないことも事実です。
資格取得後:登録・更新が必要
資格試験の合格者が活動するためには、RCCM登録簿に登録し、登録証の交付を受けなければなりません。必要な書類を添付して建設コンサルタンツ協会に提出しましょう。登録には試験合格後に「RCCM登録講習」の受講も義務付けられています。
また、RCCMは4年ごとに更新をする必要がある資格です。更新するためには、資格の満了日までに直近の登録講習の受講と自主学習を修了し、所定のCPD単位を取得しなければなりません。
RCCM試験に合格するための勉強方法
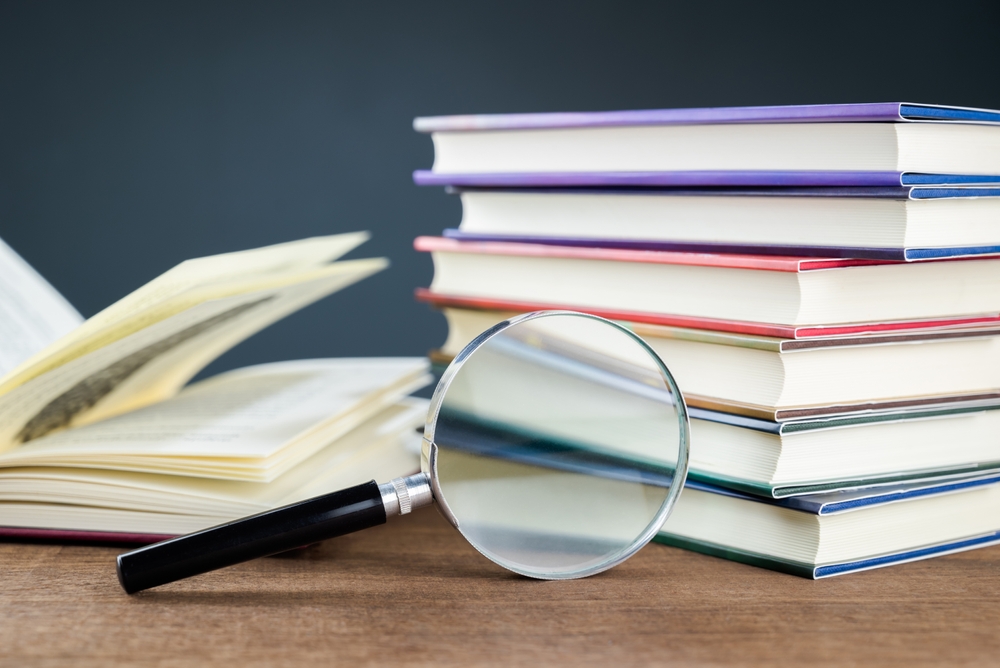
ここからは、RCCMの資格を取得するための勉強方法を紹介します。
問題Ⅰの対策
問題Ⅰの対策として、直近数年間分の業務実績を整理して回答を作成しましょう。発注者、業務名称、職務内容、履行時間を記述できるようにします。記述式の問題は自分で見直すというよりも、RCCM有資格者に添削してもらうようにしましょう。上司など身近な人に確認してもらい、アドバイスをもらえると効率的に勉強を進められます。
問題Ⅱの対策
問題Ⅱの対策として、過去問を中心に勉強を進めていきましょう。業務契約、共通仕様書、白書などから幅広く出題されますが、毎年似たような問題が多数出る傾向にあります。比較的対策がしやすく、過去問を活用して内容を押さえれば、高得点が狙えます。問題の傾向がつかめるようになるまで、ひたすら過去問を解いていく勉強方法がおすすめです。
問題Ⅲの対策
問題Ⅲは、あるテーマに対して1600文字以内で論述します。国土交通白書をもとにテーマが設定されているため、国土交通省で出されている資料を読み込み、情報を収集することが大切です。社会課題の背景や問題、現在取り組まれている対応策、解決策などをまとめておくと理解しやすいでしょう。4つの問題のなかでは、特に時間に余裕を持って取り組む問題です。
問題Ⅳの対策
問題Ⅳの対策として、問題Ⅱと同様に過去問をひたすら解いていきましょう。インターネット上にはRCCM試験の過去問をまとめたサイトも存在します。また、講習会に参加することで問題集を手に入れられます。数多くの問題に触れて慣れることが大切です。
RCCMの資格が活かせる仕事

ここからは、RCCMの資格が活かせる仕事を紹介します。
建設コンサルタント
建設コンサルタントは、建設・土木工事に際して、専門的な知見からサポートや助言をする仕事です。
多くの社会資本(ダム、橋、空港、道路などのインフラ)は、税金を使って建設されるため「設計・施工分離の原則」を守る必要があります。そのため、実際の施工は建設会社が行い、設計や管理は建設コンサルタント会社が行うのが一般的です。
建設コンサルタントは、工事が決まると、行政などと契約して工事の企画や事前調査の段階から関わります。その後は進捗に応じて、施工計画の管理や検査、工事の維持管理や評価、分析などを担います。
RCCMは、建設コンサルティング業界に携わる技術者の育成や技術力アップを目的として設けられた資格です。RCCMを取得すれば建設コンサルタントとして最大限に力を発揮できます。
資格取得後に建設コンサルタント会社での経験を積むことで、将来は建設コンサルタントの技術者として独立可能です。
建設コンサルタントとして働くメリット
RCCM取得者が建設コンサルタントとして働くメリットを紹介します。
【他の資格との併用でさらにレベルアップできる】
建築士や技術士などの資格も一緒に取得すれば、建設コンサルタントとしてさまざまな視点からアドバイスでき、スキルアップにつながります。
【最新の技術や知識が得られる】
建設コンサルタントは、さまざまな工事の管理や企画立案を行うため、常に最新の技術や知識に触れることができます。RCCMの資格取得で得た知識と合わせて建設コンサルタントの業務に活かせます。
【社会貢献できる】
建設コンサルタントは、人々の生活の利便性を高めるような社会資本の建設に携わることも多々あります。自分が関わった仕事や建造物で人々の生活が豊かになると、社会貢献している実感ややりがいが生まれるのは大きなメリットです。
建設業界におけるさまざまな職種
RCCMの資格を活かすには、建設コンサルタント会社に就職するのが最善であるというイメージが強くあります。しかし、RCCMは建設に関する幅広い知識を問うものなので、施工側である建設会社においても役に立つ資格です。
例えば、施工側であるゼネコンやサブコン、建設機械メーカー、土木関連の研究員や教育機関の教員などの仕事にもRCCMの資格が役に立ちます。
ゼネコンやサブコンで施工に携わる場合、RCCMの資格取得で得た管理や企画立案などの知識が大いに活用できます。また、建設機械メーカーでも、建設に関する過程の知識などがあれば機械の営業での活用が可能です。
高等教育機関(大学など)の教員の場合は、建設コンサルタントやゼネコンへの就職を希望する学生に対してより専門的に教えることもできます。
建設業界の他職種に挑戦するメリット
建設コンサルタント以外の他職種に挑戦するメリットを紹介します。
【適性に合った職業や興味のある職業に就ける】
建設業に関わる仕事という範囲であれば、設計や解析だけでなく施工にも興味がある方や、教員になりたい方でも、RCCMを活かして働けます。建設会社の場合は、土木や建築など、得意とする分野が企業によって異なりますので、RCCMの資格を活かした転職をするのであれば土木部門に強い建設会社を選ぶと良いでしょう。
【自己アピールに使える】
RCCMは、専門性が高い資格です。取得していると、転職や就職の際にアピールポイントとして使えます。前職も建設業であるなら、経験やスキルも活かすことができるため、よりステップアップした転職をすることも可能です。
まとめ
建設コンサルタントの分野で重宝されるRCCMは、転職やキャリアアップに有利な資格のひとつです。技術者の人手不足も相まって、有資格者を求める企業も少なくありません。RCCMを取得することで、年収アップも期待できるため、建設業界で活躍したい方は勉強を進めていきましょう。