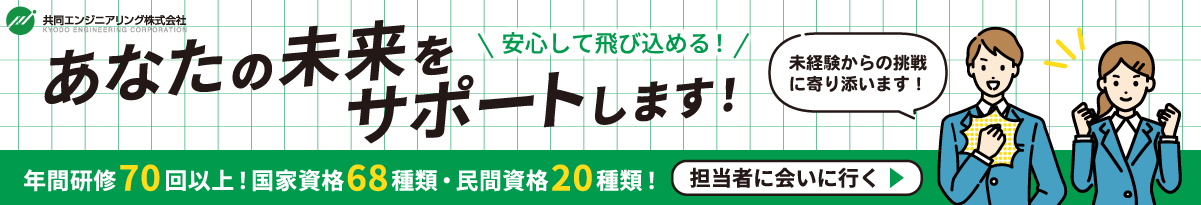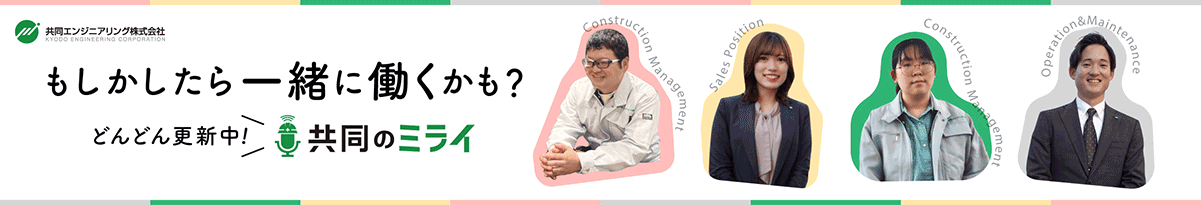目次
一級建築士と二級建築士の「仕事」の違い
 一級建築士と二級建築士の業務内容自体には大きな差はありませんが、担当できる建物の規模や構造に違いがあります。ここでは、一級建築士と二級建築士の違いを仕事の観点から解説します。
一級建築士と二級建築士の業務内容自体には大きな差はありませんが、担当できる建物の規模や構造に違いがあります。ここでは、一級建築士と二級建築士の違いを仕事の観点から解説します。
設計可能な建物の範囲
一級建築士は、建物の規模や構造に関係なく、すべての建物の設計・監理が可能です。一方、二級建築士は主に下記のような制限があります。
【木造建築物の場合】
・階数が3階以下、かつ高さが16m以下
・延べ面積が1,000㎡以下(特建を除く)
【鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの場合】
・階数が3階以下、かつ高さが16m以下
・延べ面積が300㎡以下
上記の制限により、二級建築士は主に戸建住宅や小規模な建物の設計を担当します。一方、一級建築士は高層ビルや商業施設、病院、学校などの大規模かつ複雑な建物の設計・監理が可能です。
共通の仕事
一級建築士と二級建築士は、物件規模によって必要な申請などは異なりますが、実際の業務フローはあまり変わりません。
設計業務
設計業務では主に下記の業務を行います。
・建築物のコンセプトの考案
・意匠の考案
・図面作成
・構造・設備の検証
・各所打ち合わせ
・申請手続き
・工事会社選定・見積もり精査など
設計業務と聞くと「作図」のイメージが強いかもしれません。しかし、作図は建築士が行う業務のひとつにすぎず、作図を行うためにはクライアントに何度もヒアリングする必要があり、プランに問題ないか検証する工程も大切になります。
また、実際に施工する会社を選定し、予算内にプランを調整する必要もあります。そのため、柔軟なアイデアはもちろんのこと、プロジェクトマネジメント能力やタスク管理能力が問われる仕事といえるでしょう。
監理業務
監理業務は、工事が始まる準備から竣工までの工程を監理する仕事です。現場で起きた問題点に対し、設計的アプローチをもとに解決策を考案します。
また、定期的に検査を行い、工事の進捗確認を行います。まれに設計と監理を分ける場合がありますが、多くの物件は設計者が下記の業務を担当します。
・工事業者との打ち合わせ
・実施図面の作成
・中間検査や引き渡し検査
・竣工図面の取りまとめ
一級建築士および二級建築士は、設計責任者として現場確認の機会が多くあります。また、業者やデベロッパーとの定期的な打ち合わせも多発します。細かな業務が増えてくるので、スケジュール管理が重要です。
一級建築士と二級建築士の「資格」の違い
 一級建築士と二級建築士は、どちらも建築に関する専門資格ですが、資格の交付元や受験資格、免許登録の要件などに違いがあります。それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
一級建築士と二級建築士は、どちらも建築に関する専門資格ですが、資格の交付元や受験資格、免許登録の要件などに違いがあります。それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
資格の交付元
一級建築士は国家資格であり、免許は国土交通大臣から交付されます。全国どこでも有効な資格として扱われ、大規模な建築物の設計や監理を行うことができます。
一方、二級建築士の免許は各都道府県知事が交付します。資格の有効範囲は原則として取得した都道府県内に限られ、設計・監理ができる建築物の規模にも制限があります。
受験資格
一級建築士と二級建築士では、試験を受けるための条件が異なります。
一級建築士の受験資格には、大学や短期大学、高等専門学校、専修学校などで建築関連の指定科目を修めて卒業することが必要です。または、二級建築士資格を取得した後、一定の実務経験を積むことで受験資格を得ることも可能です(※)。さらに、建築設備士の資格を持っている場合も受験が認められます。
二級建築士の受験資格は、一級建築士よりも幅広く設定されています。大学や短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校などで指定科目を修めて卒業すれば、最短で受験が可能です。また、建築設備士の資格を持っている場合は、実務経験なしで受験できます。建築関連の学歴がない場合は、7年以上の実務経験が求められます。
※一級建築士の受検資格における実務経験に関して、平成30年以降、試験の前後に関わらず免許登録時までに積んでおけば良いことになりました。詳細は下記をご覧ください。
出典:国土交通省「令和2年から建築士試験の受験要件が変わり、新しい建築士制度がスタートします!」
免許登録
試験に合格しただけでは、建築士として業務を行うことはできません。免許の登録手続きを完了することで、正式に建築士として活動できるようになります。
一級建築士の場合、上記の通り、国土交通大臣が指定する登録機関で免許の登録を行います。登録後は全国で業務が可能になります。
二級建築士の場合は、取得した都道府県で免許登録を行い、その都道府県内で業務を行うことが基本となります。
なお、それぞれの登録要件は下記の通りです。
学歴・保有資格など | 実務経験 | |
一級 | 大学 | 2年以上 |
短期大学(3年) | 3年以上 | |
短期大学(2年)・高等専門学校 | 4年以上 | |
二級建築士 | 二級建築士として4年以上 | |
国土交通大臣が同等と認めるもの | 所定の年数以上 | |
建築設備士 | 建築設備士として4年以上 | |
二級 | 大学・短期大学・高等専門学校 | なし |
高等学校・中等教育学校 | 2年以上 | |
実務経験(※) | 7年以上 | |
都道府県知事が同等と認めるもの | 所定の年数以上 |
※実務経験のみで二級・木造建築士試験を受験する場合は、引き続き、受験資格要件として実務経験が必要です。
出典:国土交通省「令和2年から建築士試験の受験要件が変わり、新しい建築士制度がスタートします!」
一級建築士と二級建築士の「試験」の違い
 一級建築士と二級建築士の試験には、試験内容や合格率において明確な違いがあります。
一級建築士と二級建築士の試験には、試験内容や合格率において明確な違いがあります。
試験内容
一級建築士試験は、学科試験と設計製図試験の2つで構成されています。学科試験は下記の5科目からなり、四肢択一式で出題されます。
・学科I(計画):20問
・学科II(環境・設備):20問
・学科III(法規):30問
・学科IV(構造):30問
・学科V(施工):25問
学科試験の合格者のみが、設計製図試験(試験時間:6時間30分)に進むことができます。
一方、二級建築士試験も学科試験と設計製図試験で構成されていますが、学科試験は下記の4科目で、五肢択一式で出題されます。
・学科I(建築計画):25問
・学科II(建築法規):25問
・学科III(建築構造):25問
・学科IV(建築施工):25問
学科試験の合格者のみが、設計製図試験(試験時間:5時間)に進めます。 このように、一級建築士試験は科目数が多く、試験時間も長いため、より広範な知識と深い理解が求められます。
合格率
過去5年間(令和2年~令和6年)の一級建築士と二級建築士の合格率を比較すると、下記の通りです。
年度 | 一級建築士合格率 | 二級建築士合格率 |
令和2年 | 10.6% | 26.4% |
令和3年 | 9.9% | 23.6% |
令和4年 | 9.9% | 25.0% |
令和5年 | 9.9% | 22.3% |
令和6年 | 8.8% | 21.8% |
一般的に、合格率が30%以下になると「難しい資格」といわれており、一級建築士も二級建築士も難易度の高い資格とされています。
まとめ
一級建築士と二級建築士の違いは、主に設計・監理できる建物の規模、資格の交付元、受験資格、試験内容にあります。自身のキャリアプランに合わせて、資格取得を検討してみましょう。
建設業界に未経験から挑戦できるBREXA Engineeringなら、下記のような特徴があり、ゼロからキャリアを築くことが可能です。
・基本的に週休2日制でプライベートも充実
・自社オリジナル研修で充実の教育体制
・あなたに対し4部門の担当者がサポート
安定した環境でスキルを身に付け、一級・二級建築士を目指す第一歩を踏み出しませんか。詳しくはこちらをご確認ください。
>>BREXA Engineeringの未経験者向けページはこちら