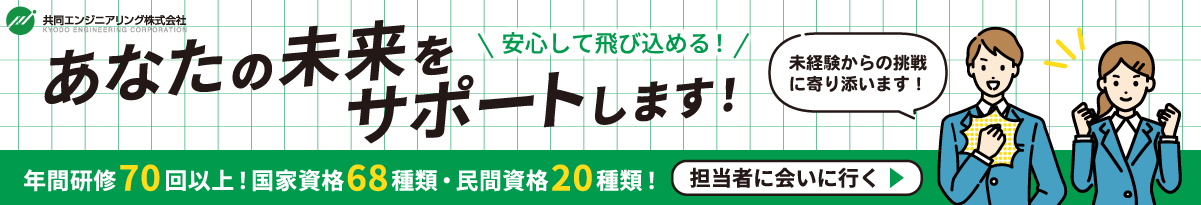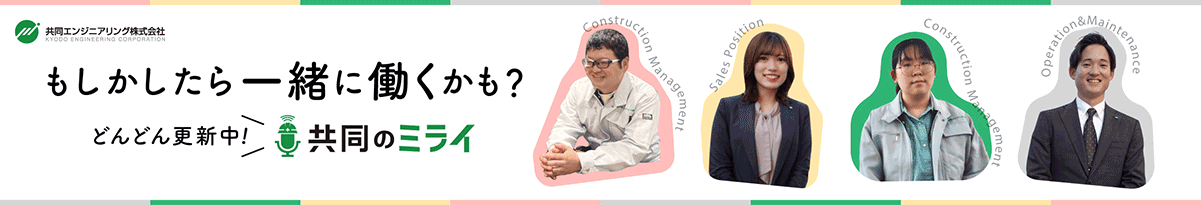目次
プラントエンジニアリング業界とは?

プラントとは日常品や鉄鋼の製造から、石油やガスといったエネルギー精製などの工場設備のことを指します。プラントに勤務する技術者をプラントエンジニアと呼び、プラントの設計や建設工事、メンテナンスなどの業務を行うのがプラントエンジニアリングです。
プラントエンジニアリング業界は、海外での工場建設にも携わっており、国や化学メーカー、電力業界、鉄鋼業界、水処理業界、産業廃棄物業界などといった大きな組織を相手に仕事をすることになります。
プラントエンジニアリング業界の現状と今後の展望
ここではプラントエンジニアリング業界の現状と、今後の展望について紹介します。
受注高は増加傾向にある
エンジニアリング業の受注高は、2011年から2021年の10年間はほぼ横ばいの状態が続いていました。しかし、2022年以降はエンジニアリング業の需要に変化が見られるようになりました。
2022年には、約8兆2,360億円だった受注額が、2023年には約8兆9,625億、2024年には約9兆1,773億(※)にまで増加しています。プラントエンジニアリング業の中でも特に増加しているのが、電力プラント、化学プラントシステム、環境衛生システムなどです。
出典:経済産業省「特定サービス産業動態統計調査の調査の結果」
※2024年の数値は、経済産業省が2025年3月に年間補正し、確報として公表したものです。
海外や再生可能エネルギー関連の需要が期待されている
今後の動向として、世界全体ではプラントエンジニアリングの市場規模の拡大が見込まれています。
特に期待されているのが、中東やアフリカ、ラテンアメリカなどでの市場の成長です。新興国での景気拡大は、新たなプラントの建設につながります。
日本国内においても新たな分野でのプラントエンジニアの需要が期待できます。環境に配慮したプラントの建設が意識されるようになったためです。再生可能エネルギー関連や二酸化炭素排出の少ないプラントの建設が見込まれます。
また、国内にあるプラントの多くは老朽化が問題になっています。プラントの建て替え需要やAIなどを活用したソフトエンジニアリングの需要も旺盛です。
プラントエンジニアリング業界に属する企業の種類

プラントエンジニアリング業界には、主に下記3つの企業の種類があります。
・EPC
・サブコン
・施工会社
それぞれの特徴についてみていきましょう。
EPC
EPCとは下記の単語の頭文字を組み合わせた略称であり、プラントの設計から建設までを一括で請け負う「元請け企業」を指します。
・E=Engineering(設計)
・P=Procurement(調達)
・C=Construction(建設)
「E」の設計とは、クライアントの要望を受けてプラント建設に関する企画を立案し、基本設計・詳細設計を行う工程です。
「P」の調達は、クライアントの要望と予算の兼ね合いをみながらプラント建設に必要な資材や機器を選定・発注し、現地に輸送する工程を指します。
「C」の建設は、設計をもとに実際にプラントを建てる工程です。プラントの外装工事だけでなく、配線・配管や空調設備など、すべての工事が含まれます。
プラント建設は非常に大掛かりであるため、ひとつの企業がすべての業務を担うことができません。そこで、EPCがリーダーとなって各企業に業務を割り振りし、プロジェクトを進めていきます。
サブコン
サブコンとは「subcontractor」の略称であり、プラント建設の一部の業務を担う下請け企業を指します。
排水・空調などの設備周りの工事、杭工事、足場工事、防水工事など、企業によって得意とする分野が異なります。
また、似た業種であるゼネコンとの違いについては、以下の記事を参考にしてください。
施工会社
施工会社とは、EPCやサブコンからの依頼で工事を行う「孫請け企業」を指します。プラント建設では土木工事や配管工事、電気工事などさまざまな工事が発生しますが、いずれも専門的なスキルや資格が必要です。
そこで、EPCやサブコンは、各工事に特化した施工会社に工事を依頼します。
プラントエンジニアリング業界の業務内容

プラントエンジニアの業務は、工場設備の企画や設計、資材調達、システム開発、施工管理と多岐に及びます。それぞれの業務内容は以下のとおりです。
・工場設備の企画や設計
生産規模や製造する製品に合わせて最適なプラントを提案し、プラント建設の設計を行います。作業の流れや全体の構造を決めたら、建築・電気・配管など各専門分野に分かれて設計を行います。
・資材調達
設計をもとに発電装置、配管、電気設備、制御システムなどの設備機器や資材を発注します。発注費用を予算内に抑えながら、工期に合わせて建設現場に機器資材を送り届けなければなりません。また、搬入時の検査なども行います。
・システム開発
プラントを構成する電気供給システムや制御システムなどを開発します。近年、IoTなどの最新技術やビッグデータを活用するシステム開発が活発になっているので、最新の知識が求められる業務です。
・施工管理
プラントが設計通りに機能するように施工し、管理・保全を行います。建設工事の施工管理と業務内容は変わらないものの、危険物などを扱うため高度な技術が求められる業務です。
・保守・メンテナンス
プラント建設後は、機械に異常や故障がないか定期的に点検し、機械に不具合が確認された場合には修理などの対応を行います。
従来は、プラントの稼働がストップしないよう、エンジニアが24時間365日常駐し、緊急対応に備えるのが一般的でした。しかし近年では、技術の進歩により、センサーでトラブルを検知したり、ドローンで異常を察知したりするなど、常駐しなくても対応できる技術も取り入れられています。
プラント施工管理の仕事内容については、下記で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
大規模な工事に携われるプラント施工管理の仕事内容と魅力を紹介!
プラントエンジニアリング業界で働くやりがいやメリット

ここでは、プラントエンジニアリング業界で働くことのやりがいやメリットについて紹介します。
社会貢献度の高い仕事に就ける
社会を支える重要なインフラである石油やガス、電気などを生み出すためにはエネルギープラントが必要不可欠です。また、廃棄物や排水の処理にもプラントは欠かせません。
このように、社会基盤の根底となる設備の建設に携われる業務は、社会貢献度の大きさを実感しやすく、やりがいを感じる方は多いです。
海外を視野に入れて働ける
日本のプラントエンジニアリング企業は、海外でのプラント建設に主軸を移しています。海外の売上比率が7割以上という企業も多く、海外赴任や海外出張が多い業界です。
グローバルなビジネスに携わりたい、海外で働くチャンスがある企業に勤めたい方はやりがいを感じられるでしょう。
年収が高い
プラントエンジニアの平均年収は、669.4万円です。一方、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、全職種の平均給与は460万円でした。
この数字を比較すると、プラントエンジニアの年収は一般的な会社員よりも高い水準にあることがわかります。
プラントエンジニアとしてさらなる年収アップを狙うなら、専門資格の取得や、より規模の大きな企業への転職・就職を検討するのも有効な手段です。
出典:
職業情報提供サイトjob tag「プラント設計技術者」
国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
プラントエンジニアの年収については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
「プラントエンジニアの平均年収は高い!年収アップの方法も紹介」
形に残るものをつくれる
プラントは何もない土地に建設され、その場所に長く残ります。そのため、自分の成果を実感しやすく達成感が得られるでしょう。
事業規模が大きく、スケールの大きなプロジェクトに携わっているという満足感を得られるのも魅力です。
スキルを身に付けて成長できる
海外赴任や出張が多い特性上、海外の関係者と接する機会が多いため、語学力やコミュニケーション力を鍛えられます。
またプラント建設は、ほかの業界では経験できない規模のプロジェクトに携わるため、リーダーシップを求められる仕事でもあります。業務を通じてマネジメントスキルがつくなど、日々の成長を実感できるでしょう。
「さまざまなスキルを身に付けて成長したい」といった向上心がある方にとって、やりがいを感じられる仕事といえます。
大規模なプロジェクトに携われる
プラントは生産設備のため、工事の規模が大きく受注額も多額になりやすい傾向にあります。特に海外ではプラント建設が盛んに行われており、需要も拡大しています。
こうした大規模プロジェクトの企画や設計に携われることも、プラントエンジニアならではの大きな魅力といえるでしょう。
プラントエンジニアリング業界であると有利な資格

プラントエンジニアリング業界で働くにあたって、あると有利な資格にはどんなものが挙げられるのでしょうか。一例として、電気、土木、配管に関する資格を紹介します。
電気工事施工管理技士
電気系のプラントエンジニアの主な役割は、プラントへの電力供給です。そのため、電気工学もしくはそれに付随する知識が求められます。
電気工事施工管理技士の資格があると、発電設備工事や送配電線工事、構内電気設備工事などに携わることができます。電気工事施工管理技士は、工程・品質・原価・安全という4つの施工管理をしながら電気工事を行うプラント建設の現場に必要不可欠な存在です。
電気系のプラントエンジニアとして働くなら、資格を取得しておくと有利になるでしょう。
土木施工管理技士
土木系のプラントエンジニアは、プラントや道路設備、湾岸施設などの設計・施工、管理を行います。土木工学系の専門的な知識が求められるため、土木施工管理技士の資格を取得しておくと良いでしょう。
土木施工管理技士は2級を取得すると、「営業所ごとに配置する専任の技術者」および「建設工事における主任技術者」として認められます。さらに1級を取得すると「営業所ごとに置く専任の技術者」および現場の「監理技術者」として認められることになります。
配管技能士
配管技能士の資格には建設配管作業とプラント配管作業があり、プラント配管作業の資格を取得していれば専門的な知識を持つ技士としてプラント工事に携われます。
この資格があると、プラントに張り巡らされているガスや蒸気、水などを配送する配管の施工に必要な知識と技能を有していることを証明可能です。
技術士
技術士は、高度な専門知識と技術力を持つことを認定する国家資格です。課題解決や研究開発など、幅広い専門分野で活かすことができます。
試験区分は21分野に分かれており、このうち、プラントエンジニアの業務に役立つのは、機械部門、建設部門、化学部門、衛生工学部門、環境部門などです。将来関わりたい分野が明確であれば、その分野の技術士の資格取得を目指すと良いでしょう。
技術士資格を取得するには、一次試験と二次試験の両方に合格する必要があります。なお、指定の教育課程を修了すると一次試験は免除されます。また、資格取得には実務経験も必要です。
関連資格として技術士補があります。実務経験が不足している場合は、まず技術士補を取得し、技術士の補助を務めながら経験を積むルートも有効です。
エネルギー管理士
エネルギー管理士は、「省エネ法」に基づく国家資格です。2006年に省エネ法が施行された際に、「熱管理士」と「電気管理士」の資格がひとつになり、現在のエネルギー管理士になりました。
この資格を取得すると、エネルギー管理者やエネルギー管理員として従事できるようになります。一定の規模以上の事業所や施設では、エネルギー管理者の配置が義務付けられているため、需要が高く、プラントエンジニアとして業務の幅を広げるのに役立つ資格です。
エネルギー管理士になるには、エネルギー管理士試験に合格する方法のほか、エネルギー管理研修を修了して取得する方法もあります。
エネルギー管理士についての詳細はこちらの記事で紹介しています。
「エネルギー管理士の難易度は?独学での勉強時間はどのくらい必要?」
未経験からでもプラントエンジニアや施工管理を目指せる!

「プラントエンジニア業界で働きたいけれど、未経験だから…」という方もプラント技術者や施工管理を目指すことは可能です。
BREXA Engineeringでは、研修やサポート体制を整えており、未経験の方でもプラントや世の中のインフラを支える仕事に携われます。アシスタント業務をこなしつつ、将来的にはプラント技術者として働くことを目指せるでしょう。
研修では建設業界に関する基礎知識を身に付けられます。入社後のコースによっては、各種CAD研修も実施しており、実際の現場で役立つスキルを手に入れることもできます。
国家資格の施工管理技士を取得して施工管理を目指すことも可能なので、プラント技術者に興味がある方は応募してみてください。
まとめ
プラントエンジニア業界の概要や業務内容、今後の展望について紹介しました。プラント建設は海外を中心に需要が高まっており、国内でも一定の需要があります。
これまでは石油や天然ガスなど、化石燃料をベースとしたプラントの建設が事業の中心でした。しかし、今後は脱炭素化の影響でCO2回収技術が重要となるなど、変化が予想されます。
社会のインフラを支える重要な役割を持つ仕事に携われるプラントエンジニアリング業界には、未経験からも挑戦できます。まずはアシスタントとして働いてみてはいかがでしょうか。