目次
技術士補はなくなる?
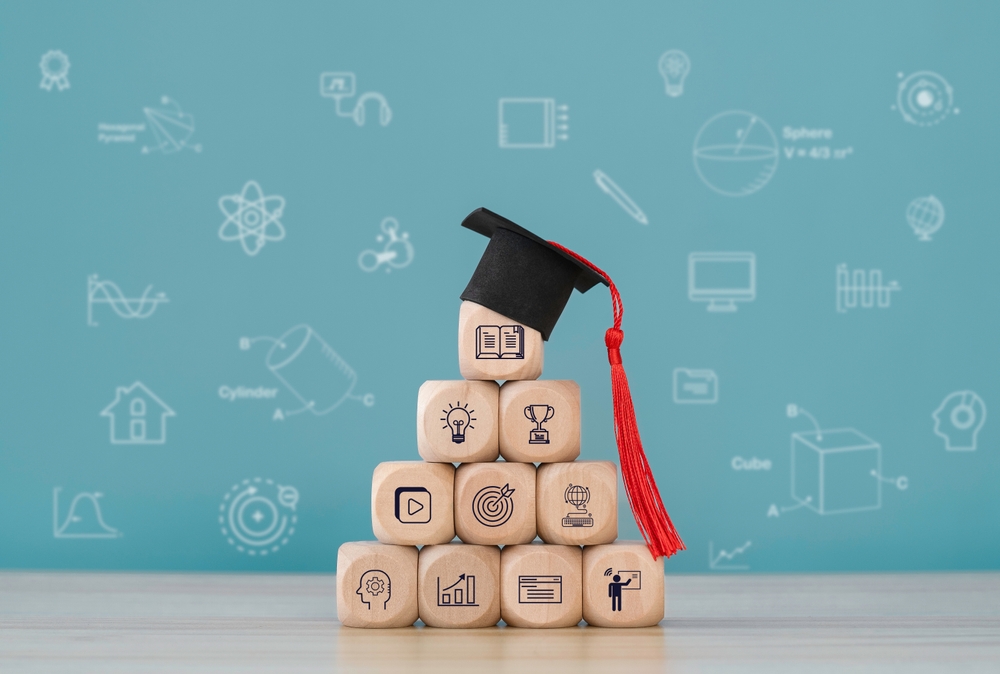
ここでは、技術士補制度をめぐる「廃止」の噂について、現在の状況と背景を詳しく解説します。
出典:文部科学省「今後の『技術士補』資格の在り方について(たたき台)」
現時点での制度状況
技術士補は、2025年9月時点で廃止はされていません。「廃止」ではなく「制度見直し」や「名称変更」が文部科学省の検討会で議論されている状況です。
技術士への登竜門という基本的役割は継続され、より実効性のある制度への改善が検討されています。
名称変更案と目的
名称変更案のひとつとして「修習技術士」という案が検討されています。
現在の「技術士補」という名称では、単なる補助的な立場という印象を与えがちですが、「修習技術士」であれば技術士を目指す過程にある専門技術者というより積極的な意味合いを持たせることができます。
つまり、この変更の目的は、資格取得のプロセスを明確にし、技術士への段階的なステップとしての位置付けを強化することです。
制度の存在意義をわかりやすくし、若手技術者への浸透を図ることで、利用率向上と制度の活性化を目指しています。
技術士補の廃止が検討されている背景
技術士補制度の見直しが議論される背景には、いくつかの構造的な問題があります。
利用率の低さ
最も大きな問題は、技術士補として登録しても二次試験を受験する人が極めて少ないことです。2018年度は、全申込者のうち技術士補経由での受験は1.2%だったそうです。
一方で、実務経験7年以上の直接受験ルートが圧倒的多数(95%)を占めており、技術士補制度が技術士への主要な登竜門として機能していない現実があります。
この数値は制度設計時の想定と大きく乖離しており、技術士補制度の存在意義が問われる要因となっています。
制度の認知度不足
技術士補制度は、登録者数や利用状況の低さが長年の課題となっています。
利用率の低さの背景には、学生や若手技術者に制度が十分に知られていないことや、登録によるメリットが現場で理解されにくいことがあげられます。
大学の工学部においても技術士制度の説明機会が限られており、卒業後に初めて制度を知る技術者も少なくありません。また、企業における技術士補の処遇や活用方法が明確でないことも、制度普及の妨げとなっています。
技術士補は今後どうなる?検討事項を紹介

技術士補制度の将来に向けて、具体的な改善案が複数検討されています。
名称変更と制度位置付けの明確化
「修習技術士」など、段階的育成を示す名称案が有力視されています。この変更により、初学者・若手技術者が目指すべきステップとして認知されやすくすることを狙っています。
名称変更と同時に、制度の目的と役割をより明確に定義し直し、技術士への確実な道筋として機能するよう制度設計の見直しも進められています。
指導技術士の部門制限緩和
現状では、指導技術士は「合格した第一次試験の技術部門と同一の技術部門とする」という規定がありますが、指導技術士の部門を限定しない方向での見直しが進んでいます。
この緩和により、多くの技術士が指導に参画できるようになり、技術士補の指導体制の充実が期待されます。また、分野横断的な指導により、幅広い技術的視野を持つ人材育成が可能になります。
登録期間や要件の見直し
登録期間に上限(例:15年)を設ける案が検討されています。制度利用の動機付けや更新意欲の向上を狙い、技術士試験への挑戦を促進することを目的としています。
受験ルートの明確化・多様化も進められており、技術士試験の受験者数増加を促す仕組み作りが検討されています。実務経験要件の柔軟化や、専門分野に応じた特別ルートの設置なども議論されています。
周知・広報強化策
大学で技術士制度説明会の実施を拡大し、学生時代から制度への理解を深める取り組みが進められています。大学技術士会のような団体と連携して情報発信を強化し、制度の魅力と意義を広く伝える活動も活発化しています。
企業向けの説明会や、技術士補を活用した人材育成の成功事例紹介なども計画されており、産学官連携による制度普及を目指しています。
技術士の将来性とは

技術士制度そのものの将来性と社会的価値について解説します。
社会的評価と活躍分野
技術士は、高度専門技術者としての社会的評価が非常に高い国家資格です。技術士はさまざまな科学技術の分野をカバーしており、機械、電気電子、化学、建設、情報工学など21の技術部門が設置されています。
熟練技術者不足を背景に、技術士への需要は継続的に拡大しています。特にインフラの老朽化対策、環境・エネルギー分野、デジタル技術の社会実装などの領域で、技術士の専門性が強く求められています。
公共事業や大型プロジェクトでは技術士の関与が法的に義務付けられている場合も多く、技術者としてのキャリアアップにおいて技術士資格の価値は今後も高まると予想されます。
近年では、カーボンニュートラルの実現に向けた技術開発や、AI・IoTを活用したスマートシティの構築、災害に強い社会インフラの整備など、新たな社会課題の解決において技術士の役割がより重要視されています。
これらの分野では、従来の技術知識に加えて、社会システム全体を俯瞰できる高度な技術的判断力が求められており、技術士の専門性が強く評価されています。また、企業のESG経営やSDGs達成に向けた取り組みにおいても、技術士の知見が重要な役割を果たしています。
国際的評価
国際的通用性の確保に向けた技術士制度の改革が積極的に進められています。将来的には国際的にも通用し、海外案件でも高い評価を受けやすい資格として発展することが期待されています。
技術士資格は、APEC(アジア太平洋経済協力)エンジニア制度やワシントン協定などの国際的な技術者資格制度との連携も強化されており、グローバル市場でのキャリア展開が可能な資格として位置付けられています。
特にアジア圏でのインフラ整備プロジェクトや技術協力事業において、日本の技術士資格は高い信頼性を持って評価されており、国際的な技術者としての活躍の場が広がっています。
まとめ
技術士補制度は完全に廃止されるのではなく、より実効性の高い制度への見直しが進められています。名称変更や要件の柔軟化により、若手技術者にとってより魅力的で利用しやすい制度に改善される見込みです。
現在、技術士補として登録されている方やこれから登録を検討している方は、制度変更による不利益は生じない見込みのため、安心して取り組むことができます。むしろ、新制度では業務範囲の拡大や学習支援の充実が期待されており、技術士を目指すための環境はより整備される予定です。
技術士資格そのものの将来性は非常に高く、社会のデジタル化や脱炭素化の進展により、高度な技術的判断力を持つ専門家への需要は今後も拡大し続けます。制度の見直しを機に、キャリアアップを目指す方は積極的に技術士補登録と技術士資格取得を検討していきましょう。
こうした動きにあわせて、これから建設業界を目指す方や、年収アップ、キャリアアップを実現したい方はBREXA Engineeringへの応募もご検討ください。未経験から挑戦できる基礎研修や資格取得を支援する制度を整えており、安心して学びながら経験を積むことが可能です。
少しでも興味のある方は、ぜひ以下リンクから詳細をご覧ください。



