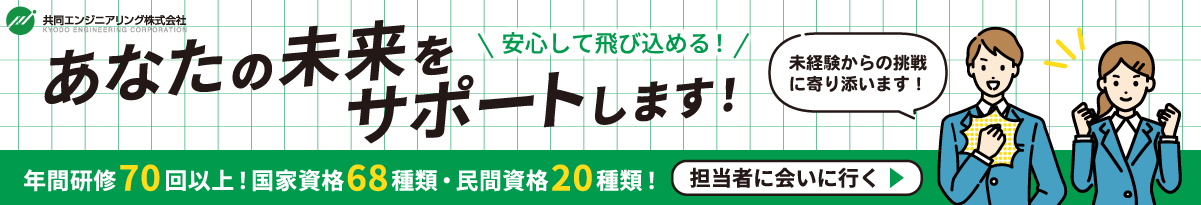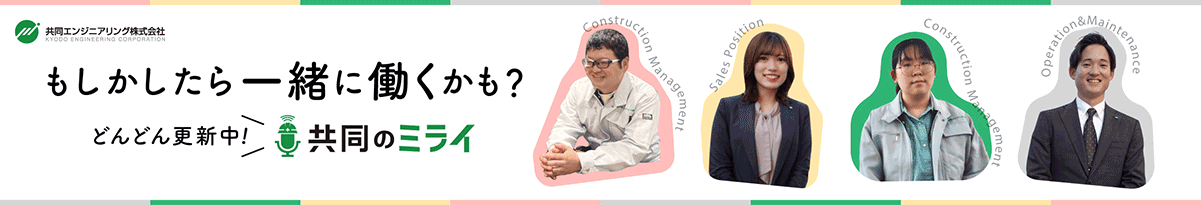建設業における若者離れの現状

なぜ建設業では若者離れが進んでいるのか、その背景と現状をご紹介します。
建設業は人手不足が深刻化している
建設業は、若者に限らず人手不足が深刻化しています。
厚生労働省「一般職業紹介状況」(令和7年6月分)によると、全業種の有効求人倍率(パート含)の実数は1.22倍です。しかし、建設業に関連する業種においては、有効求人倍率(パート含む常用)が「建築・土木・測量技術者」で4.98倍、「建設・採掘従事者」で4.87倍に達しています。
労働人口自体が減少するなか、労働環境に対するマイナスイメージから就業先に選ばれにくいことが人手不足につながっているようです。特に、若者は、労働環境やワークライフバランスを重視する傾向があるため、建設業が敬遠される傾向にあります。
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年6月分)について」
出典:政府統計の総合窓口e-Stat「一般職業紹介状況」
建設業における29歳以下の若者の割合は約1割
国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」によると、建設業就業者は高齢化が顕著です。55歳以上の就業者は35.9%ですが、これからを担う29歳以下の就業者は11.7%(2022年時点)に留まっています。
団塊の世代が全員75歳となる2025年を迎え、働き手がさらに少なくなっています。人手不足の進行は避けられず、今後も建設業ではかなりの人数が不足するでしょう。若手人材の獲得は、建設業界の大きな課題となっています。
出典:国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」
建設業に入職しても辞めてしまう
建設業は、若者の就業者が少ないだけではありません。入職後、短期間で辞めてしまうことも、人手不足に拍車をかけています。
厚生労働省がまとめた「新規学卒者の離職状況」(平成31年3月卒業者)によると、新卒者が3年以内に離職した割合は、全産業で3割を超えています。せっかく若い人材を確保できても定着しないという課題があり、建設業も例外ではありません。
特に、高卒後入社者の3年以内離職率は、全産業35.9%に対して建設業は42.2%と平均より6%ほど高くなっています。
建設業へのイメージと実態は大きく異なる

建設業が若者から敬遠される理由には、「きつい・汚い・危険」という3Kがあげられるでしょう。しかし、建設業はかつてのイメージとは異なり、労働環境は変わりつつある状況です。ここからは、建設業にもたれているイメージと実態との差をご紹介します。
雇用条件は改善されつつある
かつて、建設業界は下請け構造と利益を優先する構造により社会保険に未加入の事業者が多く見られ、問題視されていました。そこで国は2017年以降、建設業界においても社会保険加入の強制を進め、2020年の改正建設業法において社会保険加入を義務化しています。
建設業界は雇用条件が良くないというイメージがありましたが、現在では改善されており、人材確保のために福利厚生を整える企業も増えました。
また、国や業界は労働安全衛生法令の遵守徹底や技術研修の実施、事故防止対策の強化などを推進することで、就業者が安全・健康に働けるよう取り組んでいます。
新3K(給与・休暇・希望)が注目されている
建設業は、厳しい労働環境で働かなければならないということで、若者には敬遠されがちでした。
その状況を変えるため、国は「給与・休暇・希望」を建設業の新3Kとして実現させようと、直轄工事において以下のような取り組みを実施しています。
・下請企業からの見積もりを尊重する企業を優位に評価する「労務費見積もり尊重宣言」促進モデルの発注
・「週休2日対象工事」の発注や適正な工期設定のための指針策定
・ICTや新技術などの活用推進
出典:国土交通省「新3Kを実現するための直轄工事における取組」
新3Kの詳細と実現に向けた建設業界の取り組みについては、こちらの記事で解説しています。
「建設業「新3K」とは?実現するための取り組みも解説」
さまざまな人と関わり多くのことを得られる
建設業は安全管理が重要な職場なので、危険な行動に対しては叱ってくれる先輩が必ずいます。現場でのOJTで指導を受けられることは、経験の浅い若者には重要な成長の機会といえるでしょう。
また、建設業は多くの会社が1つになって建築物を作り上げていきます。業務ではさまざまな人と関わる機会があり、それだけ得られるものが多いことも魅力です。
建設業で若者離れを解消するための企業の取り組み

建設業の若手人材不足解消に取り組んでいるのは、国だけではありません。建設業の企業でも若者離れを解消するべく、さまざまな取り組みを始めています。
働き方改革を推進
建設業は、働き方改革関連法が施行された当初、特別な事情がある場合に限って時間外労働の延長が認められており、残業時間の規制が比較的緩やかな業種とされてきました。
しかし、2024年4月からは他業種と同様に、原則として月45時間、年360時間までという残業時間の上限が適用されるようになりました。
また、特別条項付き36協定の場合でも、以下の上限規制が適用されています。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働+休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働+休日労働の合計が「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がいずれも1か月あたり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6か月まで
月の残業時間の厳格な上限規制の導入により、ワークライフバランスを保ちやすくなっています。建設業界でもこれを受けて長時間労働の見直しが進められており、働き方改革の一環として企業の意識改革が進んでいます。
なお、例外として、災害時における復旧・復興に関連する建設事業に従事する場合は、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6か月平均で月80時間以内とする規制が適用されません。
それ以外の通常の建設業務については、原則通りの上限規制が適用されます。
出典:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」
建設DXの推進による生産性の向上
建設業界の課題として、生産性が低く長時間勤務が発生しやすいことがあげられます。その解決糸口として期待されているのが、BIM/CIMやITツールを活用した建設DXの推進です。
BIM/CIMは、3次元モデルを活用して、建設生産・管理の効率化や高度化を目指したシステムで、長時間労働からの脱却や従事者のモチベーションアップにつながります。
また、業務のデジタル化による業務負担軽減や、テレワーク環境の整備も進められています。建設業は現場作業が中心でテレワークは難しいとされてきましたが、施工管理などデスクワークの必要な業務は一部テレワーク化が可能で、多様な働き方を実現している企業も見られます。
建設DXにより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
「建設DXについてわかる!主な技術と推進のための取り組み」
若者離れが深刻な建設業において良い条件で働くには?

建設業は若者離れが当たり前といわれています。しかし、若手を確保したいと考える企業では、労働環境や福利厚生を改善する動きが見られるため、会社の選択次第で良い条件で働くことは可能です。
良い条件で働ける企業を見つけるには、どのような点に着目すれば良いかをご紹介します。
ポイント1|働き方改革を推進しているか
良い条件で働くには、働き方改革を推進する会社を選ぶことが大切です。
業務効率化を目指せるBIMやCIM、ITツールの導入を積極的に進めている企業は、働き方改革を推進していることが考えられます。
また、建設業は納期や人手不足の関係から休日が少ない傾向です。完全週休2日制の導入に積極的かどうかも、働き方改革を推進しているかの判断基準となります。
ポイント2|福利厚生や手当が充実しているか
福利厚生や手当が充実している会社は、従業員により良い環境で働いてほしいと考えていると判断できるでしょう。また、金銭的な面でもメリットがあります。
健康保険や厚生年金保険などの法定福利厚生だけでなく、交通費や食事手当、家族手当などの法定外福利厚生が充実している会社がおすすめです。
ポイント3|年間休日や勤務時間は適切か
勤務条件の良し悪しを見極める上で、年間休日や勤務時間も重要な指標です。厚生労働省の調査によると、令和5年の全産業平均の年間休日は116.4日でした。これと同程度、もしくはそれ以上の休日数が確保されていれば、比較的働きやすい職場といえるでしょう。
ただし、求人票に記載された休日数が実際に守られているとは限りません。休日出勤が常態化しているケースもあるため、実際の勤務体系や労働環境をよく確認しておく必要があります。勤務時間の長さや夜勤の有無もワークライフバランスに大きく影響するため、あわせてチェックしておきましょう。
出典:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況」
ポイント4|女性や外国人人材が活躍しているか
企業選びのポイントとして、女性や外国人が活躍しているかどうかも注目すべき要素です。女性従業員の活躍が目立つ企業は、ワークライフバランスの確保や職場環境の整備に力を入れている可能性が高く、働きやすい職場であることがうかがえます。
また、外国人材を積極的に受け入れている企業も、働き方改革におけるダイバーシティ推進に取り組んでいる証といえるでしょう。多様な文化や価値観を尊重し、柔軟な組織運営ができる企業は、従業員一人ひとりが力を発揮しやすい環境を整えている傾向があります。
ポイント5|キャリア開発制度は整っているか
良い条件の企業で働くためには、キャリア開発制度の有無も確認しておきましょう。建設業界では、建築士や施工管理技士などの専門資格を取得することで、業務の幅が広がり、昇給や昇進といった待遇面でも優遇されやすくなります。
企業によっては、資格取得を支援するために講習の実施や合格時の資格手当を用意しているところもあります。こうした支援制度が整っている企業は、長期的な人材育成に力を入れている証でもあり、働きがいのある環境といえるでしょう。
さらに、CADやBIM、IoTといった最新技術に対応するための研修制度があるかどうかも、今後のスキルアップやキャリア形成において重要なチェックポイントです。制度の有無だけでなく、実際にどれだけ活用されているかも面接などで確認しておくと安心です。
【補足】実際に働いている人の話も参考にしよう!
求人票や企業のホームページだけでは、職場のリアルな雰囲気や働きやすさまでは見えてこないこともあります。そこで参考にしたいのが、実際にその企業で働いている方の声です。
現場で働く方の体験談を確認することで、ワークライフバランスや職場環境をより具体的にイメージできます。企業によっては従業員インタビューを公開している場合もあるため、積極的にチェックしてみましょう。
BREXA Engineeringでは、現場で働いている方の声をインタビュー形式で紹介しています。実際の業務内容や職場の雰囲気を知る上で参考になりますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。
まとめ

建設業では若者離れや人手不足が深刻な課題ですが、実際には労働環境の改善や新技術の導入、働き方改革の推進など、業界全体に前向きな変化が起こっています。従来のイメージだけで判断せず、企業ごとの取り組みや実情を見極めることで、自分に合った働き方ができる職場と出会える可能性は十分にあります。
これから建設業への就職や転職を考えている方は、将来性や制度面も含めて、ぜひ幅広い視点で選択肢を検討してみてください。
BREXA Engineeringでは、女性の活躍推進と働きやすい環境づくりに力を入れています。女性技術者の割合は32%(2022年12月時点)と、業界平均(※)の約2倍を実現しています(※2020年厚生労働省「労働力調査」より)。各部署に女性が相談しやすい体制を整えており、安心して働ける環境が魅力です。
また、産休・育休制度の整備や残業時間削減の取り組みなど、ライフステージに応じた柔軟な働き方もサポートしています。さらに、入社時の導入研修や資格支援対策講座など、未経験からでも安心して働ける充実の研修制度も完備しています。
建設業界でキャリアを築きたい方は、BREXA Engineeringをぜひご検討ください。