目次
一級土木施工管理技士の合格率
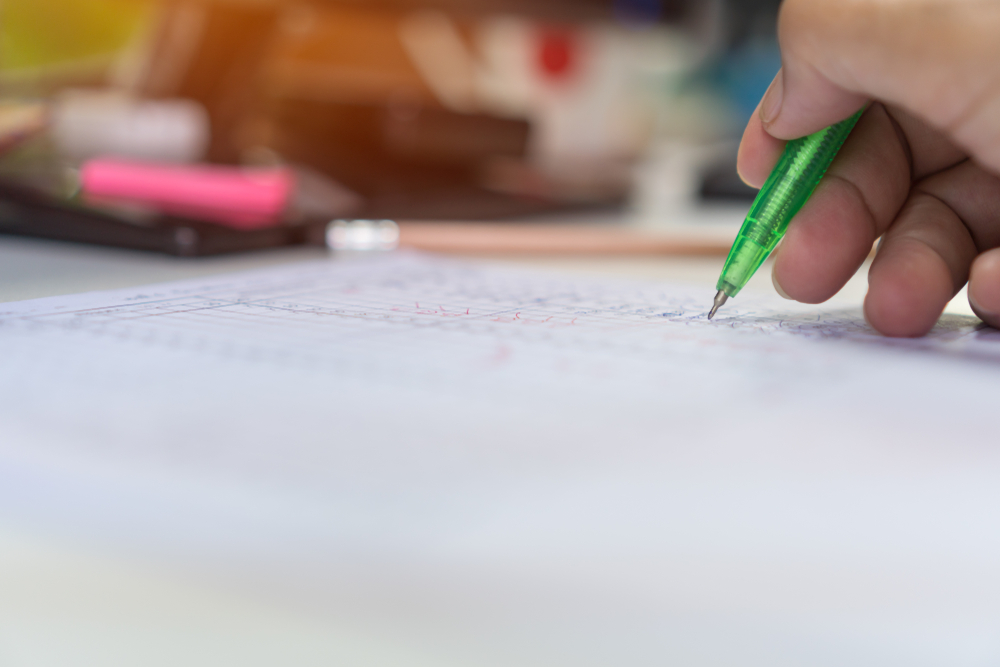
一級土木施工管理技士の試験は、「一次検定」と「二次検定」に分かれています。まず一次検定を受け、一次検定に合格できたら二次検定を受検することが可能です。
一次検定・二次検定はどれくらいの方が通過できているのか、それぞれの合格率を紹介します。
一次検定
一級土木施工管理技士の一次検定の合格率は、45~55%程度です。過去3年間の一次検定合格率をみてみましょう(2025年時点)。
2022年(令和4年度) | 2023年(令和5年度) | 2024年(令和6年度) | |
受検者数 | 38,672人 | 32,931人 | 51,193人 |
合格者数 | 21,097人 | 16,311人 | 22,705人 |
合格率 | 54.6% | 49.5% | 44.4% |
2024年は合格率が44.4%に下がりましたが、それでも平均的には一次検定の難易度は高くないといえます。
また、2021年(令和3年度)4月より、一次検定を合格すると、「技士補」を取得することが可能です。
出典:総合資格学院「1級土木施工管理技術検定の合格率について」
二次検定
一級土木施工管理技士の二次検定の合格率は、30~40%程度が平均です。こちらも過去3年間の二次検定合格率をみてみましょう(2025年時点)。
2022年(令和4年度) | 2023年(令和5年度) | 2024年(令和6年度) | |
受検者数 | 24,462人 | 27,304人 | 27,220人 |
合格者数 | 7,032人 | 9,060人 | 11,224人 |
合格率 | 28.7% | 33.2% | 41.2% |
どの年度も一次検定と比較して、大幅に合格率が低下しています。二次検定に合格しないと資格が取得できないため、一級土木施工管理技士になるのは狭き門であるといえるでしょう。
出典:総合資格学院「1級土木施工管理技術検定の合格率について」
土木施工管理技士の受検資格について詳しく知りたい方はこちら
「土木施工管理技士の受験資格・試験概要を徹底解説!」
一級土木施工管理技士への合格が難しい理由

合格率を見てもわかる通り、一級土木施工管理技士の資格は高い難易度を誇ります。なぜ資格取得が難しいのか、その理由を解説します。
試験範囲が広い
一級土木施工管理技士の試験合格が難しい理由のひとつとして、試験範囲の広さがあげられます。一級土木施工管理技士は、土木工事の現場で「主任技術者」や「監理技術者」として活躍できる職種です。
業務内容は、工程・安全・品質・原価の4大管理以外に、計画の立案から各種書類作成、役所での手続きと幅広く、豊富な知識と経験が求められます。そのため、一級土木施工管理技士の試験では、土木工学や施工管理法、法規など、多くの分野から出題されます。
さらに、各分野を表面的に学習するだけでは不十分で、実務に役立つレベルまで深く理解しておかなくてはなりません。
これほど高いレベルの知識が求められるのは、工事全般を管理するにあたって総合的な専門知識が必要になるからです。
例えば、橋梁工事ひとつとっても、基礎工事や地盤、コンクリート工学、鋼構造学、環境アセスメントや法規など、多様な知識が求められます。
そのため、一級土木施工管理技士に合格するには、約500~600時間の勉強時間が必要です。二級土木施工管理技士の場合、必要な勉強時間は約300~400時間であることから、二級に比べると、より多くの時間を投入することになるでしょう。
広範囲の知識を実務レベルまで習得するには長い時間がかかるため、必然的に資格取得の難易度も上がります。
実務経験が必要
一級土木施工管理技士の資格試験を受検するには実務経験が必要なことも、取得難易度が高い要因です。
一次検定については、2025年時点で19歳以上(2007年4月1日生まれ含む)であれば、実務経験がなくても受検できます。しかし、二次検定は所定の年数の実務経験がないと受検できません。
実務経験とは、現場で4大管理や施工計画作成などの業務に携わることです。雇用形態は問われませんが、資材を運んだだけ、事務仕事をしただけなどでは、実務経験とみなされません。
虚偽の申告が発覚した場合は資格を取り消されるため、全国建設研修センターが発行している受検の手引きなどで実務経験の詳細を確認しておきましょう。
なお、実務経験の年数は学歴によって違いがありましたが、2024年の法改正により、実務経験で一律化され、下記のように変更されました。
2.一次検定合格後、1年以上の特定実務経験を含む実務に就いた場合:3年以上
3.上記以外の場合:5年以上
2028年までは経過措置として制度改正前の受検資格による受検も認められています。
参考:全国建設研修センター「令和7年度 1級土木施工管理技術検定 第一次検定・第二次検定 新受検資格 受検の手引」
二次検定は記述式問題
二次検定では実務経験に基づく記述式問題が出題される点も、一級土木施工管理技士の資格取得の難易度を押し上げています。
施工計画やトラブル対策などを時間内に仕上げなくてはならない上に、自身の考えや経験を的確に文章化する能力が必要となるため、対策が困難です。それにもかかわらず、配点が高いため、スムーズに解けないと合格が難しくなります。
法令や技術基準が頻繁に更新される
土木工事関連の法令や技術基準の改正が多いことも、一級土木施工管理技士の資格取得が難しい原因です。せっかく身に付けた知識も、法令や基準が変更されると再度学び直さなければなりません。
スケジュール通りに学習を進めつつ、最新情報をキャッチアップして反映させる必要があるので学習の難易度が上がります。
土木施工管理技士の難易度や必要な勉強時間について知りたい方はこちら
「土木施工管理技士の難易度はどれくらい?必要な勉強時間とは」
一級土木施工管理技士に合格するための学習スケジュール

一級土木施工管理技士に合格するためには、計画的な学習とスケジュール管理が重要です。 ここでは、一級土木施工管理技士の試験合格に向けた基本的な学習スケジュールを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ステップ1|出題傾向や基礎用語の理解から始める
一級土木施工管理技士の試験対策では、まず基礎用語の理解と出題傾向の把握から始めましょう。しっかりと基礎を固めれば、応用問題にも対応しやすくなります。
また、一級土木施工管理技士の試験では、過去の試験問題と類似した問題が出る場合もあります。最近の過去問を見て、出題パターンや頻出問題の傾向をつかみましょう。
ステップ2|過去問を繰り返し解く
基礎を理解し、ある程度出題パターンがつかめたら、過去問を繰り返し解いて問題の理解度を深めましょう。何度も問題を解いていると徐々に慣れてきて、スムーズに解けるようになってくるはずです。
また、一度覚えても時間が経つと忘れてしまいがちですが、定期的に復習すると記憶が定着しやすくなります。特に間違えた問題は何度も解いてみて、しっかりと記憶を定着させましょう。
ステップ3|得意・不得意分野を理解する
過去問を繰り返し解きながら、自分の得意・不得意分野を明確化して学習の優先順位をつけることも重要です。不得意分野の克服には時間がかかるため、できるだけ早めに学習をスタートしましょう。
得意分野で合格の基準が満たせるようなら、あえて不得意分野を捨て、得意分野の学習に集中するのもひとつの方法です。どちらが自分に合うかを考えてみましょう。
ステップ4|模擬試験を行う
学習が進んだら模擬試験を行ってみましょう。本番で何点くらい取れるのかがわかるので、自分の実力を客観的に評価できるようになります。さらに模擬試験の結果を分析すれば、より正確に自分の弱点を把握できるため、学習効率も向上するでしょう。
また、本番の雰囲気を体感することでペース配分をつかめる、試験当日の緊張感を軽減できるなどのメリットもあります。
なお、一級土木施工管理技士は、日建学院による全国統一公開模擬試験が実施されています。日建学院の教室で受けるか自宅で受けるかを選べるので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
一級土木施工管理技士の資格があると建設業界での転職が有利になりますが、資格の取得難易度が高めです。
幅広い分野の知識が求められるので学習に時間がかかるほか、二次検定は実務経験がないと受検できないため、スケジュールを立てて計画的に学習を進めましょう。
一級土木施工管理技士の資格取得を目指しながら実務経験を積むなら、BREXA Engineeringをご検討ください。
BREXA Engineeringでは経験の有無や職種を問わない採用を実施しており、未経験からでも学べる、成長できる環境を整えています。資格取得支援制度もご用意していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
>>BREXA Engineeringの未経験者向け採用ページはこちら
>>BREXA Engineeringの経験者向け採用ページはこちら



