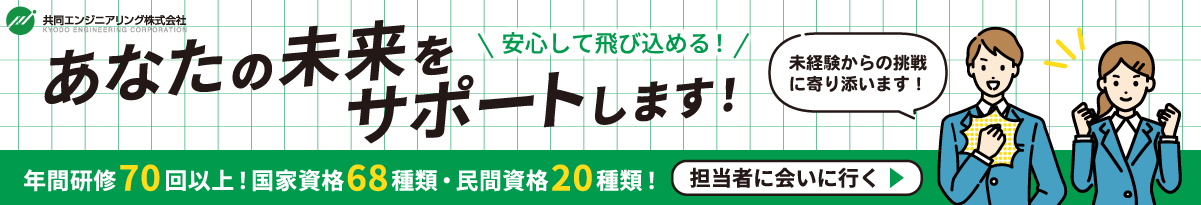目次
設計監理とはどんな職種か

設計監理とは、建物の設計と現場の工事監理の両方を行う仕事です。
設計監理は一般的な建築士と同じように、図面や仕様書の作成までを含む建物の意匠設計、構造設計、設備設計などを建築士が行います。さらに、現場において建物が設計や仕様書通りに造られているのかを確認する工事監理までを、トータルで行うのが特徴です。
設計監理の業務範囲は多岐にわたるため大変ではありますが、やりがいが大きい仕事です。専門的な知識と技能を要する設計業務があるため未経験からの就業は難しく、主に一級建築士、二級建築士、木造建築士などの有資格者が業務を担当します。
設計監理の仕事は「設計」と「監理」にわけられる

設計監理の仕事は、大きく「設計」と「監理」の二つにわかれています。それぞれの仕事の内容を詳しくみていきましょう。
設計
設計監理が行う設計業務は、次の通りです。
条件整理
まず、クライアントの依頼に基づき、敷地条件、法的規制、建築予算などのさまざまな条件を整理します。これは、すべての条件をクリアする建物を設計する必要があるため行います。条件を吟味したうえで建築物の規模や構造設備、外観、意匠などのプランを構築し、クライアントへ提案します。
役所協議
建物を建てる基準は自治体によって異なるため、プランの建物が法や条例に抵触しないか確認が必要です。そのうえで、役所での事前調査や事前協議を行います。
基本設計
クライアントと打ち合わせして、要望にしたがって建物の構造、間取り、設備などの仕様を決め、図面や資料を作成します。平面図や立体図だけではわかりにくい場合は建物の模型、イメージパースなども作成して、クライアントとの情報共有を図ります。
実施設計
建物の方針が決まったら、実施設計で各部の正確な寸法や素材などの仕様を決め、図面を作成します。サンプル素材を使い、クライアントの要望と一致するものを提案して決めていくのが一般的です。
最終的にまとめる実施設計図面は、外観から内部の構造までを明らかにする位置図から、平面図、立面図、断面図、矩計図、展開図、構造図、設備図と多岐にわたります。実施設計図面は完成した段階で施工会社に提示し、見積依頼へと進みます。
確認申請
施工会社の見積依頼と並行して、クライアントの代理で確認申請をします。建築予定地の自治体や民間の審査機関に対して設計図や仕様書を提出し、各種法律の規定をクリアしているか確認を求める手続きです。
監理
設計監理が行う監理業務は、次の通りです。
見積精査
施工会社から提出を受けた見積書に漏れや重複がないか確認し、内容を精査します。見積書が予算を超過している場合は設計の見直しを行い、再度クライアントへの提案を行います。
施工会社選定
見積書や各種資料を確認して、現場の施工を依頼する会社を決定します。施工会社は仕上がりを左右するため、各会社の特性や実績なども考慮して決める必要があります。
工事監理
実際に工事が始まったら、現場で作業の進捗状況を確認します。設計図や仕様書通りの工事が行われているかを点検し、不備がある場合は施工会社に是正を促す重要な仕事です。点検の結果はクライアントにも報告し、1〜2週間に1度を目安に定例会議を開いて、工程、品質、原価、安全の確認を行います。
検査・引渡し
建物が完成したら設計検査を行い、最終確認をします。建物や設備の寸法、強度、性能などが仕様書通りか確認します。その後、役所や審査機関による完了検査を受け、是正点がなければクライアントへ引き渡す流れです。
工事費についても最終精査をし、クライアントに引き渡した後は、継続してアフターサービスに努めます。
設計監理に必要なスキル
 設計監理を担うには、幅広い専門知識と多様なスキルが必要です。具体的には、建築学の基礎や設計の原則、現代建築の動向を把握することが不可欠です。さらに、建築基準法や関連条例などの法的要件を正しく理解し、遵守しながらプロジェクトを円滑に進める能力も求められます。
設計監理を担うには、幅広い専門知識と多様なスキルが必要です。具体的には、建築学の基礎や設計の原則、現代建築の動向を把握することが不可欠です。さらに、建築基準法や関連条例などの法的要件を正しく理解し、遵守しながらプロジェクトを円滑に進める能力も求められます。
また、コスト管理では予算内で最適な設計・施工を実現し、品質管理では設計意図を正しく反映させながら高い施工精度を確保することが重要です。工程管理では、スケジュールを調整しながら各工事が適切なタイミングで進むように監督する必要があります。
加えて、建築主や施工業者、専門工事業者との調整力や交渉力、トラブル発生時の対応力といったコミュニケーション能力も欠かせません。プロジェクト全体を統括し、設計と施工の橋渡しをする役割として、的確な判断力と問題解決能力も求められます。
設計監理に関わる3つの資格
建築の設計や工事監理には専門的な知識と責任が求められます。補助的な業務に携わることは可能ですが、一定の建築物に関しては建築士の資格がなければ、その者の責任において設計や工事監理はできません。これは建築士法により、業務独占業務として定められています。
設計とは、設計図書を作成し、その内容に責任を持つことを指します。一方、工事監理とは、工事が設計図書どおりに実施されているかを確認し、適切な進行を管理する業務です。これらの役割を担うために、建築士には「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類があり、それぞれ業務範囲が異なります。
延べ面積 | 木造建造物 | 木造以外 | すべての構造 | ||||
高さが13m かつ軒高9m以下のもの | 高さが13m かつ軒高9m以下のもの | 高さが13m または 軒高9mを超えるもの | |||||
階数1 | 2階建て | 3階建て 以上 | 2 階 建 て 以 下 | 3階建て以上 | |||
30㎡以下 | 【A】 | 【A】 | 【D】 | ||||
30㎡を超え 100㎡以下 | 【C】 | ||||||
100㎡を超え 300㎡以下 | 【B】 | ||||||
300㎡を超え 500㎡以下 | 【C】 | 【D】 | |||||
500㎡を超え 1,000㎡以下 | 一般 | ||||||
特建 | 【D】 | ||||||
1,000㎡を 超えるもの | 一般 | 【C】 | |||||
特建 | |||||||
下記では、それぞれの資格について詳しく紹介します。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「建築士の種類と業務範囲」
一級建築士
一級建築士は、建築設計・工事監理における国家資格であり、ほぼすべての構造・規模・用途の建築物を扱えます。そのため、大規模な都市開発や公共事業など、ゼネコンや官公庁のプロジェクトに関わるケースが多いのが特徴です。
一級建築士を取得するには、難関な試験を突破する必要があります。合格率は平均10%前後と低く、多くの受験者が数年かけて挑戦するのが一般的です。試験に合格すると、国土交通大臣から免許が交付され、一級建築士として業務に携われます。
さらに、一級建築士の資格を取得した上で、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士になるためには、5年以上の実務経験が必要です。加えて、構造設計の場合は2日間または3日間の講習を受け、修了考査に合格しなければなりません。
二級建築士
二級建築士は、一級建築士と比較して設計できる建築物の範囲に制限があります。合格率は平均25%前後であり、ストレート合格を目指すことも可能です。合格後は、都道府県知事から免許が交付され、建築業務に携われます。
二級建築士は、一級建築士が手がける大規模な建築物に対して、比較的小規模な建物を対象としています。主に戸建て住宅の設計・監理を担当するケースがほとんどです。
2020年の改正建築士法により、実務経験の対象範囲が拡大され、これまでよりも間口が広がりました。その一方で実務経験申告の審査方法が厳格になったため、経験の証明や記録に対する管理が重要になっています。
なお、2025年4月の建築基準法の改正により、二級建築士が設計できる木造住宅の範囲が拡大されています。ゆえに、二級建築士の活躍の場はさらに広がる見込みです。
出典:国土交通省「令和4年改正 建築基準法について」
木造建築士
木造建築士は、木造建築物の設計・工事監理に特化した国家資格です。木造建築士の試験の合格率は35%前後であり、比較的高いといえます。合格後は、都道府県知事から免許が交付され、木造建築物に関する業務に携われます。
木造建築士が設計・監理できるのは、2階建て以下の木造建築物です。また、現在は床面積500㎡以下の木造建築物については、構造耐力などの審査や検査の一部が免除または省略される特例があります。
しかし、2025年の建築基準法改正により、この免除や省略が適用される建物の規模が床面積200㎡以下に縮小される予定です。
出典:国土交通省「令和4年改正 建築基準法について」
【設計監理】施工管理との違いとは
設計監理と施工管理は漢字や語感が似ていて、混同されやすい仕事です。同じ工事現場に携わる仕事でも業務範囲や立場が大きく異なるので、両者の違いを正しく理解して仕事を選ぶ必要があります。
設計監理は、作業が設計図や仕様書通りに進んでいるのかをチェックするのが仕事です。設計監理は建築主側の立場で、設計を行った建築士が工事を点検、確認、是正します。
一方、施工管理は建設事業者の立場で、期限内に設計図や仕様書通りに工事が進むようマネジメントするのが仕事です。現場の作業員を監督するとともに、現場の工程管理、品質管理、原価管理、安全管理を一貫して行うなどの違いがあります。
未経験から目指すなら施工管理がおすすめ

未経験からの転職を目指すなら、設計監理よりも施工管理の仕事がおすすめです。同じ建設関連の専門知識が必要な仕事でも、施工管理には特別な資格や学歴が必要ありません。現場で学びながら働けます。
ここからは、施工管理の魅力を解説していきましょう。
需要・将来性とも高い
施工管理が必要とされる現場は土木、住宅、ビル、公共インフラと多岐にわたり、施工管理は常に一定の需要がある仕事です。 施工管理を含む建設業界は、ニーズが途切れない仕事です。
生活に必要な「衣」「食」「住」のひとつに関わるため、仕事が急になくなることはありません。新築工事だけでなく建て替えもあり、社会情勢に左右されにくく受注が安定しています。
また、建設業は慢性的な人手不足が続いていて、未経験者の育成に力を入れている点も転職におすすめのポイントです。高齢化が進み、若手の人材が求められています。建設業界の職種のなかでも、施工管理は現場で学びながら働けるため、資格や経験のない方でも転職のチャンスがあります。
資格取得でスキルアップできる
資格取得でキャリアアップが目指せるのも、施工管理の魅力のひとつです。資格を取得すれば、仕事の幅を広げられるでしょう。施工管理の仕事で強みになる主な資格は、次の二つです。
・2級施工管理技士
・1級施工管理技士
2級施工管理技士は、施工管理をする人の登竜門となる資格です。経験や資格によらず受検でき、合格すれば現場で主任技術者や管理技士として働けます。上位資格の1級施工管理技士を取得すれば、大規模な建設現場に携わるのも夢ではありません。
施工管理技士は現場に必要とされるため、資格取得で年収アップにも期待がもてます。資格手当の支給で、積極的に資格取得をサポートしている企業もあります。
施工管理の仕事をするのに資格は必須ではないものの、資格は確かな知識や技術があることを証明します。資格取得で職場での評価があがり、任される仕事の幅も広がるため、昇任や将来的な転職に有利に働くと期待できます。
また、令和3年より新たな資格として「施工管理技士補」が設けられました。この資格だけでは主任技術者や管理技士にはなれないものの、責任者を補助する役割が担える資格です。取得により応募の幅が広がる場合もあるので、未経験から施工管理の仕事を目指すなら検討してみましょう。
なお、施工管理の現実や仕事の魅力については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。あわせてチェックしてみてください。
「施工管理が激務って本当?実情とやりがい、激務になりにくい企業に転職する方法も」
まとめ
設計監理の仕事は、建築士として建物を作る、やりがいのある仕事です。とはいえ、設計に関する専門的な知識や資格が必要なので、未経験からの転職なら施工管理の仕事の方が適しています。
施工管理は資格不要で、未経験からでも転職しやすい仕事です。経験がなくて現場についていけるか不安なら、正社員型派遣から始める選択肢もあります。建設業界は需要が安定しているものの、人材が不足していることから転職しやすいといえます。
BREXA Engineeringでは、若手の人材教育に力を入れています。入社後の充実した研修制度で着々と知識やスキルを身に付けられるので、未経験の方でも心配はいりません。キャリア相談や資格取得のサポートもしているため、安心して就業を目指せます。
また、大手ゼネコンの現場も扱っているため、若手のうちから規模が大きい仕事に携わるチャンスがあります。未経験で施工管理の仕事を目指すなら、どうぞお気軽にお問い合わせください。