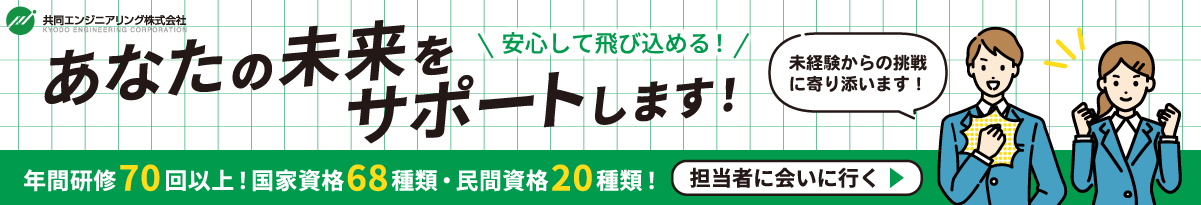建設業がブラックだといわれる理由

建設業界は、他の職種と比較して厳しい労働環境が指摘されることが多いようです。その背景には、労働時間の長さや休暇の少なさ、過酷な身体的負担、そして特有の上下関係や安全面でのリスクが挙げられます。ここでは、その具体的な理由を解説します。
労働時間が長く休みが取りにくいため
建設業では、プロジェクトの締め切りや納期が厳しいことから、夜遅くまで働くことが一般的です。国土交通省の「建設業を巡る現状と課題」によると、年間の実労働時間は、全産業の平均と比べて、90時間ほど長くなっています。
また、休暇については、同調査によると4週8休以上の企業は全体の8.6%にとどまり、4週6休程度が44.1%、4週5休程度が22.9%、さらには4週4休程度以下が13.2%となっています。週休2日を確保できていない企業が多く、十分な休息が取りにくい環境で働く人が多いといえるでしょう。
ただし、現状の労働環境を変えるべく、厚生労働省も対策を行っています。具体的には、建設業の事業者に向け、働く人の休日数を考慮した工期の設定や、処遇改善のため受発注時に適切な金額設定をするよう推奨しています。詳細は下記特設サイトをご覧ください。
出典:
国土交通省「建設業を巡る現状と課題」
厚生労働省「建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト はたらきかたススメ 建設業」
身体への負担が大きいため
建設業界の仕事は肉体的な負担が避けられません。現場では、重い資材を運んだり、長時間同じ姿勢を維持して作業を続けたりすることが求められる場面が多々あります。その結果、筋肉痛や関節痛が慢性化することがあり、さらにストレスも蓄積しやすい環境です。
これにより、生活の質が低下する場合もあり、身体的な負担が仕事の続行を難しくさせることも少なくありません。
昔ながらの体質が残っている現場もあるため
建設業界には、昔ながらの体質が残っている労働環境が存在する場合もあります。例えば、上下関係が厳しく部下がパワハラのように感じてしまうなどです。このような文化は、新入社員や若手の職人が大きなプレッシャーを感じる原因となり、精神的な負担を増加させることがあります。
ただし、この厳しい関係性が若手の成長を促す側面もあり、建設業ならではの育成の一環として捉えられる場合もあります。しかし、その反面、心理的な負担が増大し、離職率の高さにつながる一因ともなっています。
大きな怪我につながることもあるため
建設業界では、高所作業や重機の操作など、危険をともなう作業が日常的に行われています。近年、安全管理の意識は高まりつつありますが、依然として改善の余地がある状況です。
また、不十分な安全対策が原因で、労働災害が発生するケースもみられます。
建設業に従事する5つのメリット

ここまで建設業がブラックといわれる理由を紹介しましたが、建設業には多くの魅力があります。ここでは、建設業に従事することで得られる5つのメリットを解説します。
手に職をつけることができる
建設業界では、スキルや経験を積むことで市場価値が向上し、キャリアアップの可能性が広がります。現場作業や技術習得を通じて得られる専門的な知識は、多岐にわたる分野で活用できます。
例えば、大規模なプロジェクトを任されるようになったり、将来的に独立して専門家として事業を展開したりする道も見えてきます。
需要が高い
建設業界は、今後も需要が見込まれる業界です。住宅や商業施設、公共施設など、生活に欠かせない建造物の需要が安定しているだけでなく、災害復興や都市再生プロジェクトといった公的需要も後押ししています。
こうした背景から、建設業界で働くことは雇用の安定性を確保する意味でも魅力的です。特に社会基盤を支える重要な役割を果たしているため、将来性のある職種といえます。
実績が目に見える
建設業で働く最大の魅力のひとつは、自分の仕事の成果が目に見える形で残ることです。街や地域にそびえ立つ建造物は、自らが携わったプロジェクトの成果であり、多くの人々が利用する姿を見ることができます。 このような達成感や誇りは、他の職種では得られない建設業ならではの魅力といえます。
コミュニケーションスキルが身に付く
建設現場では、多種多様な職種や役職の人々と連携しながら仕事を進める必要があります。そのため、円滑なコミュニケーション能力が養われ、協調性やリーダーシップのスキルも自然と身に付いていきます。こうしたコミュニケーションスキルは、仮に他の業界に転職する際にも大いに役立つでしょう。
未経験でも活躍できる
建設業界では、未経験者にも活躍のチャンスが広がっています。国土交通省のデータによると、業界全体で高齢のベテラン社員が引退するケースが増えており、意欲的に働くことで管理職への昇進も目指せます。
企業によっては、未経験者から必要なスキルを学びながら成長できる環境が整っており、自分の努力次第で大きな成果を上げることが可能です。
出典:国土交通省「建設業及び建設工事従事者の現状」
ブラックな建設会社を避けるポイント

最後に、ブラックな建設会社を避けるためのポイントを解説します。
ポイント1|求人情報をしっかり確認
求人情報には、給与や労働時間、休日、福利厚生など、基本的な情報が記載されています。これらの情報をもとに、その企業が社員の健康や生活を大切にしているかを見極めましょう。特に注目すべき点は下記の通りです。
・給与/資格手当:理想の給与額を明確にし、その条件を満たしているか確認する
・休日:完全週休2日制の求人を探すことで、しっかりと休みを確保できる環境を見つけられる
また、求人情報だけでは不明瞭な点もあるため、面接時に直接質問することも大切です。例えば、実際の労働時間や資格手当の詳細など、気になることを積極的に尋ねることで、安心感が得られるでしょう。
ポイント2|働き方改革の取り組みをチェック
働き方改革は現代の建設業界において注目されている要素です。国土交通省が推進する「建設業働き方改革加速化プログラム」は、業界全体で労働環境の改善を目指しています。2024年からは中小企業も対象となり、さらに本格的な取り組みが期待されています。
求人票を確認する際には、下記の点をチェックしましょう。
・働き方改革への具体的な取り組みが記載されているか
・取り組みによる労働時間や業務負担の改善状況が記載されているか
もし内容が不明瞭な場合は、面接時にしっかりと質問して、企業の姿勢を確認することをおすすめします。
出典:国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」
ポイント3|口コミも確認
実際に働いている社員や過去に勤めていた社員の口コミは、その企業の実態を知るうえで有益な情報源です。匿名で投稿される口コミサイトでは、職場の雰囲気や社風についての具体的な意見を知ることができます。
ただし、口コミはあくまでも参考程度に留めましょう。すべての意見が正確であるとは限らないため、他の情報と併せて総合的に判断することが重要です。
ポイント4|企業と現場の規模も要チェック
企業の規模も労働環境を見極める際の重要なポイントです。中小企業と大手企業にはそれぞれ下記のような特徴があります。
・中小企業:少人数で業務を進めることが多く、業務量が多くなりやすいが、個々の意見を反映しやすい
・大手企業:業務を分担しやすく、労働負担が軽減されやすい一方で、意思決定に時間がかかる場合がある
まとめ
建設業界は、厳しい労働環境が指摘される一方、スキルが身に付いたり、やりがいを感じたりといった魅力が多くあります。自分に合った環境で働きたい方は、求人情報や口コミなどを調べた上で、理想の職場を見つけてください。
BREXA Engineeringでは、未経験から安心してスタートできる環境を提供しています。土日祝休み+長期休暇で年間休日は約120日であり、仕事とプライベートを両立しやすい環境です。さらに充実した研修で、未経験者でも施工管理のスキルをじっくり学べます。建設業界で理想の働き方を実現したい方は、ぜひ下記から詳細をご覧ください。