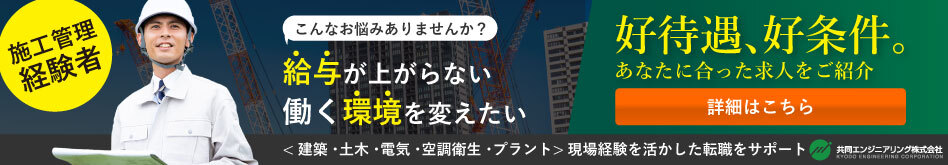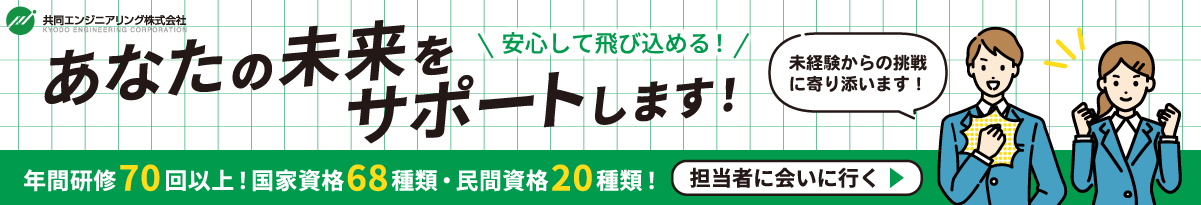目次
建設業界で役立つ資格一覧!キャリアアップ・転職におすすめ

建設業界で役立つ資格は数多くありますが、中でもキャリアアップや転職に役立つ資格を12個ご紹介します。
仕事のモチベーションを高めるためにも、資格取得をひとつの目標としてみてはいかがでしょうか。
建築士
建物の設計や施工、工事監理を行うのに必要な国家資格で、1級建築士・2級建築士・木造建築士の3種類あります。
資格の種類によって、下記のように設計や監理に携われる建物の規模が異なります。
・1級建築士:範囲に制限がなく、学校や病院、百貨店など大型の施設も含めたすべての構造・規模・用途の建造物
・2級建築士:戸建て住宅や小規模な店舗など、比較的小規模な建造物に限定
・木造建築士:小規模かつ2階建てまでの木造建築物に限定
取得するためには「学科試験」と「設計図面試験」の両方に合格する必要があります。
1級建築士の合格率は例年10%程度で、狭き門といえるでしょう。また、2級建築士で約25%、木造建築士で約35%となっているため、全体的に難易度の高い資格です。
出典:
建築技術教育普及センター「直近5年間の試験結果」
建築技術教育普及センター「過去5年間の二級建築士試験結果データ」
建築技術教育普及センター「過去5年間の木造建築士試験結果データ」
建築設備士
空調や換気、排水、電気など建築設備全般の知識を証明する国家資格で、建築士に対し建築設備の設計や工事監理の助言ができます。
建築設備が複雑化・高度化していることや、安全意識の高まりなどから、近年重要視されている資格です。
建築設備士が在籍する企業は評価が上がるため、転職・就職にも有利な資格とされています。
建築士よりも上位の資格なので、受験するには四大卒かつ、1級建築士の取得及び建築設備の実務経験が必要です。
建築士と同じく「学科試験」と「設計製図試験」のふたつをクリアする必要があります。
合格率は例年20%を切っている難関試験です。2022年度の試験の合格率は約16%でした。
1級建築士同様の狭き門ですが、取得すれば業務の幅が広がります。
出典:建築技術教育普及センター「過去5年間の建築設備士試験データ」
電気工事士

電気設備の工事や取扱いに必要な国家資格で、電気設備は無資格者には扱えないため、電気工事に必須となる資格です。
ビルや工場、一般住宅などの電気工事を行えるほか、自宅のリフォームやDIYにも活用できます。
第一種と第二種にわかれており、下記のように担当できる範囲が異なります。
・第一種:ビルや工場など大規模施設の電気工事及び、高圧の送配電線路における電気工事が可能。電線の接続や配電盤の取り付けなどができる
・第二種:一般住宅や小規模施設の電気工事が可能。スイッチ・コンセントの設置や、電気工事が設計通りかチェックできる
どちらも「筆記試験」と「技能試験」の両方に合格する必要があり、第二種のみ年2回受験できます。
例年の合格率はどちらも40〜50%程度です。難易度自体はそれほど高くないものの、電気工事において非常に役立つ資格です。
出典:
電気技術者試験センター「第二種電気工事士試験」
電気技術者試験センター「第一種電気工事士試験」
電気主任技術者
事業用電気設備の工事・運用・維持など、保安監督業務を担う国家資格で、電気工事の現場で監督や電気設備の保守・点検を行います。
第一種から第三種まであり、種別に応じて対応できる電気工作物の種類が異なります。
・第一種:すべての事業用電気工作物
・第二種:電圧17万ボルト未満の電気用工作物
・第三種:電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000KW以上の発電所を除く)
第一種と第二種は一次試験・二次試験の両方に合格する必要があり、第三種のみ一度の試験で合否が決定します。
合格率は例年低く、第三種で10〜15%程度、第一種・第二種では10%前後となっています。
出典:
電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験」
電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験」
電気技術者試験センター「第一種電気主任技術者試験」
第一種〜第三種まで、どの段階においても合格率の低い高難度資格です。実務経験を積みながら、少しずつステップアップしていきましょう。
電気工事施工管理技士
建設工事現場の照明や変電、発電設備など、電線工事の監督を行える国家資格です。
取得することで「電気工事における施工計画の作成」や「工事の工程・安全・品質などの管理」「電気工事の監督業」といった建造物の建設・増築に必要な業務を行えます。
等級は1級と2級にわかれており、それぞれ下記のように業務範囲が異なります。
・1級:特定建設業の電気工事における専任技術者・主任技術者・監理技術者に選定される
・2級:一般建設業の電気工事における専任技術者・主任技術者に選定される
どちらも「第一次検定」と「第二次検定」の両方に、合格する必要があります。
合格率は比較的高い傾向にあり、2022年度は1級が59%で、2級が46.7%でした。
出典:
施工管理技術検定「令和4年度 1級電気工事施工管理技術検定 結果表」
施工管理技術検定「令和4年度 2級電気工事施工管理技術検定 結果表」
キャリアアップや転職に有利な資格でありながら、比較的に合格率が高いため挑戦しやすい資格のひとつです。
建築施工管理技士

工事現場の施工計画書の作成や工程管理などの業務に必要な国家資格です。建築施工管理技士は、現場の監督や依頼主や設計者との打ち合わせなどが主な業務となります。
1級と2級では、扱える工事の規模に差があります。
・1級:工事の規模に上限がなく、超高層マンションやショッピングモール、公共施設のような大規模工事に、主任技術者・監理技術者として従事できる
・2級:小〜中規模の現場(元請け工事における下請合計金額が4,000万円未満※)で、主任技術者として従事できる
※建築一式工事は6,000万円未満
どちらも「学科試験」と「実地試験」に合格する必要があり、合格率は比較的高い傾向にあります。2022年度の合格率は、1級で45.2%、2級で36.6%という結果になっています。
出典:
施工管理技術検定「令和4年度 1級建築施工管理技術検定 結果表」
施工管理技術検定「令和4年度 2級建築施工管理技術検定 結果表」
1級と2級では携われる工事の規模が変わるため、2級からステップアップできれば、大きなキャリアアップにつながる資格です。
土木施工管理技士
ダムや橋・道路・港湾・トンネルといった、ライフラインの工事計画・工程管理・品質管理に必要な国家資格です。
土木施工管理の業務内容は、主に公共工事における施工計画の作成や工程管理、品質管理、予算管理、安全管理などです。建築施工管理技士と同様に、等級によって扱える現場の規模が異なります。
どちらも、学科試験・実地試験をパスする必要があります。
1級、2級ともに例年の学科試験の合格率は半数を超えているものの、実地試験の合格率は30〜40%とやや低い傾向にあります。
出典:
総合資格学院「一級土木施工管理技士試験の合格率」
総合資格学院「二級土木施工管理技士試験の合格率」
管工事施工管理技士
各種管工事の施工計画作成・工程・品質・安全管理に必要な国家資格で、有資格者は各種配管工事に欠かせない存在です。
ひと口に配管工事といっても幅広く、冷暖房設備や空調設備、ガス管配管設備、浄化槽設備、上下水道配管設備、給排気ダクトなど、さまざまなパイプやダクトを設置します。
建築施工管理技士、土木施工管理技士と同様に、1級と2級にわかれており、それぞれ担当できる工事の規模が異なります。
どちらも学科試験・実地試験に合格する必要があり、例年の合格率は1級で50〜60%ほどで、2級で約45%前後となっています。
出典:
総合資格学院「1級管工事施工管理技士 試験の合格率」
総合資格学院「2級管工事施工管理技士 試験の合格率」
キャリアアップや転職に有利な資格ですが、受験者のおよそ半数が合格するため、比較的取得しやすい資格です。
技術士

技術士は、日本の技術者の中でもトップレベルの国家資格です。主に、科学技術に関する計画、研究、設計、分析、試験、評価とこれらを指導するために必要となります。
科学技術をすべて網羅することは難しく、技術士資格では建設、上下水道、機械、環境など、21の専門分野に細分化されています。そのうち最も汎用性が高いのが建設部門です。
また、資格を取得するには、一次検定と二次検定に合格しなければなりません。一次試験は筆記のみで、基礎・適性・専門科目があり、各科目で半分以上の問題に正解する必要があります。
二次試験は筆記と口頭試験があり、すべて60%以上の正解率で合格ラインに達します。例年の合格率は非常に低く、10〜15%程度(二次試験)です。
出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第二次試験 統計情報」
宅地建物取引士
宅地建物取引士とは、「宅建」や「宅建士」とも呼ばれる国家資格のひとつです。毎年20万人前後の方が受験するため、人気の高い国家資格といえます。
試験合格後に登録実務講習を受講すると、宅建士の独占業務である物件取引契約に関する「重要事項の説明」を行うことが可能です。不動産取引の専門家として、お客様に登記の仕方や不動産の詳細、キャンセル時の対応などを説明します。
宅建の試験内容は、4肢択一のマークシート方式で50問(1点/問)出題されます。出題される科目は「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」の4種類です。
全問正解で50点満点となりますが、合格点は受験者全体の成績によって相対的に決まるため、年によって変動します。例年の合格率は15~17%程度であり、しっかりと準備する必要があります。
出典:総合資格学院「宅建士試験の合格率」
CAD利用技術者試験
CAD利用技術者試験は、CADシステムを用いて、正確かつ効率的に図面を作成できる能力を証明する試験制度です。CAD利用技術者試験には下記の3種類があります。
・二次元CAD利用技術者試験基礎
・二次元CAD利用技術者試験1級(建築、機械、トレース)、2級
・三次元CAD利用技術者試験1級、準1級、2級
それぞれの合格率は下記の通りです。
二次元CAD利用技術者試験基礎 | 70~80% |
二次元CAD利用技術者試験 | 2級:50%程度 |
三次元CAD利用技術者試験 | 2級:45~65% |
出典:CAD利用技術者試験「統計情報」
建築積算士
建築積算士とは、建物の建設費用を正確に見積もるスペシャリストとして、建設業界や各企業の営業などの要といえる資格です。かつては、国土交通省が認定する資格でしたが、行政改革の一環で民間資格となりました。
建築積算士になれば、建物を建てるために必要な材料や、従業員の稼働時間、設計図などを見て、どのくらいの費用がかかるのかを算出できます。
資格取得のための試験は、一次試験と二次試験で構成されており、二次試験では図面を確認しながら数量の計測や計算などを行う実技試験もあります。建築積算士の例年の合格率は60%程度です。
出典:公益社団法人日本建築積算協会「建築積算士認定事業による試験実施結果」
まとめ
今回は、建設業界でキャリアアップや転職に役立つ資格をいくつか紹介しました。難易度の高い資格も多いものの、取得できれば業務の幅が広がり、キャリアの選択肢も増えていきます。資格取得をひとつの目標にすれば、仕事へのモチベーションも高まることでしょう。
「スキルを高めたい」「キャリアアップしたい」と考えているものの、今の職場ではなかなか実現できないとお悩みの方は、「BREXA Engineering」で大手案件を経験してみませんか。これまでの経験に自信がない方でも問題ございません。
将来のキャリアを前向きに考えていきたい方は、ぜひ一度ご応募ください。