目次
ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)とは

ビル管理士の正式名称は、「建築物環境衛生管理技術者」といいます。日本建築衛生管理教育センターが主催する、建築物における衛生環境の確保に関する法律(ビル管法)を根拠とした国家資格です。
ビル管法では、特定建築物においてビル管理士の選任が義務付けられています。特定建築物とは、床面積3,000㎡以上の特定用途で使用される建物のことです。学校については、床面積8,000㎡以上の建物が特定建築物に該当します。
ビル管理士の役割は、特定建築物における環境衛生の維持管理や監督です。建築物における管理業務計画の立案や管理業務の指揮監督、建築物環境衛生管理基準に基づく測定や検査結果の評価、維持管理に必要な調査実施の業務を担います。
ビル管理士の難易度が高いとされる理由

ビル管理士の資格取得が難しいとされる理由を、受験資格、必要正解率、試験範囲の3つの観点から解説します。
受験資格がある
ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)は、誰でもすぐに受験できるわけではなく、受験資格を満たさないと試験を受けられません。
受験資格として、申し込み時点で特定用途の建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務経験が2年以上必要です。
特定用途の建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館、ホテル、そのほかのこれらに類する用途の建築物のことです。衛生的環境が類似しており、多数の利用が認められる施設が該当します。
受験資格では、建築物の用途に加え、従事したことのある実務も要件となります。該当する環境衛生上の維持管理に関わるものとは、下記に該当する実務のことです。アフターサービスとして提供する巡回点検などは含まれません。
・空気調和設備管理
・給水・給湯設備管理
・排水設備管理
・ボイラ設備管理
・電気設備管理
・清掃・廃棄物処理
・ねずみや昆虫などの防除
なお、上記とは別に、法律施行規則に規定される環境衛生監視員の業務や保健所の環境衛生担当部署での勤務経験も受験資格に関する業務に含まれます。
必要正解率をクリアしなければならない
ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の試験には、合格基準があります。試験は全7科目から構成されており、各科目について、満点数に対し40%以上を得点しなければなりません。
さらに、全7科目の満点の合計180点に対して65%以上を得点することも求められます。つまり、各科目の得点が40%以上であっても総得点が基準を下回っていると合格できません。反対に、総得点が基準を超えていたとしても、1科目でも40%未満だと不合格となります。
試験範囲が広い
ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の試験は範囲が広いため、十分な準備が必要です。下記の7科目から構成され、合計180問の出題があります。
・建築物衛生行政概論(20問)
・建築物の構造概論(15問)
・建築物の環境衛生(25問)
・空気環境の調整(45問)
・給水および排水の管理(35問)
・清掃(25問)
・ねずみ、昆虫等の防除(15問)
幅広い分野から出題されるため、合格するには全科目をバランスよく学習する必要があります。
ビル管理士の合格率
下記の表は、直近のビル管理士試験の受験者数、合格者数、合格率を示した表です。
第54回(令和6年度) | 第53回(令和5年度) | 第52回(令和4年度) | |
受験者数 | 7,593人 | 8,232人 | 9,413人 |
合格者数 | 1,759人 | 1,819人 | 1,681人 |
合格率 | 23.2% | 22.1% | 17.9% |
出典:厚生労働省「『第54回建築物環境衛生管理技術者試験』の合格発表~令和6年度の合格者は1,759人~」
ビル管理士の合格率は、試験の難易度によって毎年変動します。
過去から現在までの合格率は、表からもわかるように、20%前後です。全体の受験者数に対して合格率が高くないことから、難易度の高い国家資格といえます。
【学習方法】ビル管理士に合格するには
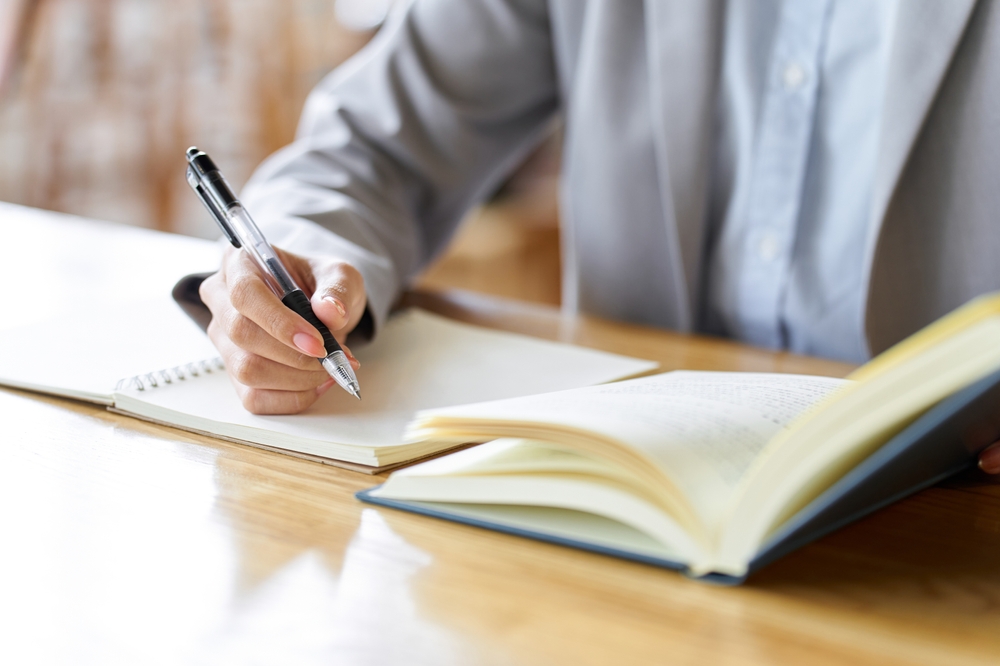
ビル管理士試験に合格するための効果的な学習方法を、3つのポイントで紹介します。
テキストや過去問を繰り返し解く
ビル管理士の基本的な学習方法として、専門の教材を活用して知識を習得したり、過去問題集を利用して問題演習に取り組んだりする方法があります。
ビル管理士の試験に初めて挑戦する場合、まず過去問を解いてみることが、自分の理解度レベルの把握に役立つでしょう。解けなかった問題が特定の科目に集中している場合は、どの科目が苦手であるかの分析にも役立ちます。試験までの学習スケジュールを立てていく際にも効果的です。
また、過去問を解くことは試験の出題傾向を把握するのにも役立ちます。過去と類似する問題が出題される傾向もあるため、出題頻度の高い内容を重点的に学習することがポイントです。傾向把握のためには、数年分の過去問を解くことをおすすめします。
さらに、過去問は反復して解くことによって、出題範囲の広い試験の内容を効率的に習得できるメリットもあります。ビル管理士の試験は問題数が多いため、前半後半に区分するなどして理解と暗記の効率化を図りましょう。
実務経験を積む
ビル管理の現場で設備の管理や保守の業務に携わることも、ビル管理士の試験勉強に役立ちます。実務経験を積むことで、テキストだけでは学べない実践的な知識やスキルを身に付けることが可能です。
ビル管理士の試験では、設備の仕組みに関する部分も出題されます。実際の設備を目にして業務で触れることによって、理解が深まり、知識が定着しやすくなります。テキストだけではイメージしにくい部分をカバーするのに、実務経験は重要です。
また、ビル管理士では、受験資格として実務経験が求められます。実務経験が不足している場合は、受験資格を補いつつ、試験対策ができる点でメリットがあります。
講座を受講する
ビル管理士の試験に特化した講座やセミナーを受講する方法もあります。独学では理解が難しい部分などの解説を受けられるため、効率的に試験対策できるのが受講のメリットです。専用講座であれば、講師から直接指導を受けられるため、苦手な部分の強化にも役立ちます。
通学が難しい場合は、通信講座を選択する方法もあります。動画教材による通信講座であれば、自分のタイミングで学習を進められるため、スキマ時間を活用した効率の良い学習を実現できるでしょう。
なお、ビル管理士の資格は、合計101時間の建築物環境衛生管理技術者講習会を受講することでも取得できます。ビル管理士は難易度の高い資格とされているため、確実に取得する方法のひとつとして検討できるでしょう。
ただし、建築物環境衛生管理技術者講習会を受講するには、学歴や保有する免許に応じた経験年数が必要です。例えば、最終学歴が大学の理工学科などの場合は経験年数1年以上、高等学校の工学系であれば経験年数5年以上が求められます。
まとめ
ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)は、特定建築物において選任が義務付けられている資格です。特定建築物の環境衛生の維持管理に関する業務を担います。
なお、ビル管理士は、特定建築物の管理業務に関わる重要な資格ですが、難易度が高いとされています。試験範囲が広いこと、科目別または全体の必要正解率が定められていること、受験資格が設けられていることが理由です。
受験資格を満たすには、特定用途の建築物で2年以上の実務経験を積まなければなりません。
ビル管理士の資格取得を目指すなら、実務経験を積めるBREXA Engineeringがおすすめです。未経験から維持管理・ビルメンテナンスを募集しており、充実した研修を通して知識やスキルを身に付けられます。
>>BREXA Engineeringの未経験者向け採用ページはこちら
>>BREXA Engineeringの経験者向け採用ページはこちら



