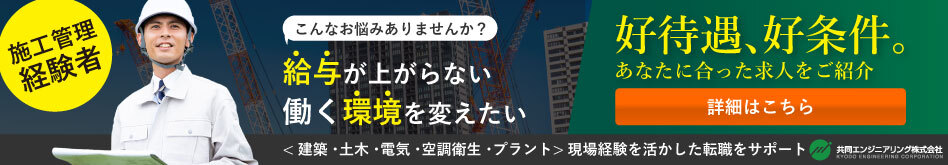目次
【施工管理】建設業界全体でホワイト企業が増えている!その理由は?

建設業界は、若手の就業者が少なく人材が定着しにくいことから、深刻な人手不足に陥っています。そのため、国主導で働き方改革が進められるようになり、大手ゼネコンを中心にホワイト企業が増加しました。
まず、ホワイト企業が増えている理由について、業界の動向を踏まえてご紹介します。
1.働き方改革が浸透している
2019年4月1日より施行された改正労働基準法により、時間外労働の上限が規制されるようになりました。建設業はこれまで上限規制が猶予されていましたが、2024年から時間外労働(残業時間)の罰則付き上限規制が適用されています。
上限の時間は月に45時間、年に360時間です。月に45時間を超えても良いとされるのは、年に6回までです。なお、守らない場合は「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」を科されます。特別な事情があるケースでも、単月で100時間未満、2~6か月間で平均80時間以内、年に720時間以内に収めなければなりません。
ただし、災害からの復興・復旧に必要な業務であれば、「単月で100時間未満」「複数月平均で80時間以内」の規制は適用外です。
このような改革の影響で、労働環境の改善に取り組む企業が増えているのです。
2.適切な工期の設定が推進されている
建設業では、契約工期内に目的物を竣工させることが重要です。しかし、工期の設定に余裕がないため、長時間労働や少ない休日数につながることが課題となっていました。これを受けて、政府は「工期に関する基準」に基づいた適切な工期の設定を推進しています。
「工期に関する基準」とは、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者および受注者(下請負人を含む)が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準です。令和2年7月に中央建設業審議会により作成・勧告されました。
この基準では、工期設定における受発注者の責務として、以下が示されています。
・発注者の責務:受注者や下請負人が時間外労働規制を遵守できる工期設定に協力し、規制違反を助長しないよう十分留意する。
・受注者の責務:契約締結の際、時間外労働規制を遵守した適正な工期による見積りを提出するよう努める。
さらに、令和6年4月からの建設業の時間外労働規制適用を踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、令和6年3月に同基準が改定されました。この改定により、発注者は受注者から時間外労働規制を遵守した適正な工期による見積りが提出された場合、内容を確認し、これを尊重することが明示されています。
また、近年の資機材の納入遅れ等を考慮した工期設定が重要とされており、自然要因(猛暑日)における不稼働を考慮して工期設定を行うことも推奨されています。
3.社会保険の加入率アップ
従来、建設業界には社会保険未加入の会社が多くあり、問題視されてきました。それを受けて、国と業界による以下のような社会保険加入対策が実施され、加入率が向上しています。
・社会保険未加入の業者の公共工事請負不可
・社会保険未加入作業員の現場入場不可
加えて、2020年10月の改正建設業法の施行により、建設業許可・更新時に社会保険加入義務が課されました。そのため、2025年9月末にはすべての建設業許可業者が社会保険に加入する見込みです。
4.建設のDX化
働き方改革の必須であるデジタル技術を活用したDX化は、建設業界でも進められています。
国は建設業におけるIT活用を「i-Construction」と名付け、建設会社の技術開発に協力し始めています。現在さまざまな取り組みを実施中で、2025年までに2割の生産性向上を目指しています。これにより休暇を取りやすい労働環境の実現が期待できます。
とはいえ、建設業界は人手不足のため、働き方の仕組みが整いきっていない企業もあります。転職する際は、次に取り上げるホワイト企業の特徴を押さえておきましょう。
【施工管理】ホワイト企業の7つの特徴

ホワイト企業に明確な定義はないものの、一般的に従業員が働きやすい環境を整えており、適切な賃金が支払われている企業を指します。
自身の働き方に対する考え方によっても基準は変わります。建設業界でホワイトと呼ばれる企業には、以下の7つの特徴が見られることが多いので参考にしてみてください。
残業防止に意欲的
建設業は作業の進捗が気候に左右されることもあり、残業が発生しやすい傾向があります。
残業時間は募集要項に目安が記載されている場合もあるので、自分が何時間まで残業を許容できるかを事前に決めておき、会社選びの参考にすることをおすすめします。
また、離れた事務所やオフィスに戻る必要がなく、現場への直行直帰ができる会社も移動時間を短縮できるので有利です。
給料に納得できる
労働に対して適切な賃金が支払われているか、その給与水準を判断するには、平均値との比較が判断材料になります。国税庁「令和6年民間給与実態統計調査」によると、施工管理を含む建設業の平均年収は約478万円でした。
給与設定は職種や年齢、経験などによって差はありますが、平均よりも大幅に低い場合は業務に見合った給与が支払われていない可能性もあるので注意が必要です。
なお、資格を保有している場合は資格手当がつく会社もあるため確認しておきましょう。各種施工管理技士のほか、電気工事士や建築士などが手当の対象となる傾向にあります。
休日が確保されている
休日がきちんと確保されている企業もホワイトの可能性が高いです。
年間休日日数が120日前後あると、週休2日の働き方ができる可能性が高く、それ以上になると、お盆や年末年始などの休暇が別途用意されていると考えられます。
また、会社として働き方改革が進んでいるのかも検討材料となるので、可能であれば、実際に働いている方の話を聞きにいくことをおすすめします。
有給休暇の消化率が高い
有給休暇を取得しやすい環境は、従業員の休息を尊重している証拠といえます。
職場全体で休暇を取りやすい雰囲気づくりがなされており、従業員のワークライフバランスを重視している企業であれば、施工管理としてメリハリをつけながら働けます。
教育・研修制度が充実している
従業員のスキルアップやキャリア形成を支援するために、教育・研修制度が充実しているのもホワイト企業の特徴です。
例えば、未経験者には基礎から学べる研修プログラムやOJT、中堅・ベテラン社員には最新技術や業界動向を学べるセミナーの開催や資格取得支援など、階層に合わせて制度を提供するところもあります。また、キャリアカウンセリングやリーダーシップ育成を目的とした管理職向けの研修を整備しているところもあります。
このような教育制度の充実は、会社が従業員の長期的な成長を支援している証拠といえるでしょう。
離職率が低く、平均勤続年数が長い
ホワイトな企業は、福利厚生が充実している、人間関係のトラブルが少ないなど、従業員が働きやすい環境を整えています。そのため、会社に対する信頼が高く、離職率が低い傾向です。
加えて、平均勤続年数が長い企業は、従業員が長く働き続けたいと思える魅力的な職場環境を提供していることの表れといえます。逆に離職率が高い企業は、労働環境に問題がある可能性が高いため、転職時の判断材料として確認しておくと良いかもしれません。
経営事項審査の点数が高い
経営事項審査とは、建設業法第4章の2にある「建設業者の経営に関する事項の審査等」のことを指します。
経営事項審査の点数が高いと工事の入札順位が上がり、公共工事を請けやすくなります。公共工事は暦通りに働けることが多いため、ホワイトな環境で働ける可能性が高いといえます。
また、この評価制度は企業の経営状況や技術力、社会性などを総合的に評価するものです。点数が高い企業は経営が安定しており、従業員にとって安心して働ける環境が整っていることを示しています。
【施工管理】ホワイトに働く3つの方法

建設業界の働き方改革は進んでいますが、会社自体がホワイトに見えても、実際は施工管理の業務が忙しく残業が多いケースもあります。ここでは施工管理としてホワイトに働く方法を3つ紹介します。
正社員型派遣で働く
正社員型派遣の場合、配属先の企業が労働を命じることができるのは、派遣元との36協定の範囲内になります。残業が発生する場合には残業手当が支払われ、サービス残業はありません。
労働時間は派遣元や行政からもチェックが入るため、問題があれば是正されます。
また、正社員型派遣では、正社員という安定した雇用のもと、1社に限らず、企業によってはさまざまな配属先を選べるので、自分が働きやすい環境で働けることもメリットです。
施工管理の正社員型派遣のメリットは、こちらの記事でも詳しく説明しています。あわせてご覧ください。
施工管理派遣のメリット・デメリット!派遣会社を選ぶ3つのポイント
正社員型派遣での働き方に興味がある方は、ぜひBREXA Engineeringにお問い合わせください。経験者はもちろん、未経験から施工管理に挑戦したい方のサポートも行っています。
また、未経験の場合は、1人に対し4部門のプロが就業をサポートするため、安心して業務に取り組むことが可能です。建設業界・プラント業界の導入研修や建設基礎研修、資格支援研修など、他にもさまざまな研修を実施し、技術社員が成長できる環境を整えております。興味のある方はぜひお問い合わせください。
ICTツールの導入が進んでいる会社で働く
ITツールの導入が進んでいる会社もホワイトな働き方ができると考えられます。
前述したように、建設業界では国がDX化を推進しており、時代に合った働き方に移行できている建設会社は、ホワイトな労働環境にある可能性が高いです。
ICTツールの導入に積極的な会社は、業務効率化への関心も高いと考えられます。そのため残業が発生する可能性も低いと判断できるでしょう。
女性や外国人採用比率が高い建設会社で働く
女性の活躍が多い場合、産前産後休業や育児休業をはじめ働き方改革に沿った企業運営ができている会社だとアピールできるでしょう。休日や勤務時間についても、業界全体の取り組みと同様に運用されている可能性が高いです。
また、外国人材を活用している企業は、多様性を取り入れる柔軟性を持っていると考えられます。多様な人材が活躍できるよう社内制度を整えている会社も多いので、ホワイトな環境で働けるはずです。
【施工管理】ホワイト企業に転職するコツ

施工管理職で働くにあたって、ホワイト企業へ転職することは、働きやすさや長期的なキャリア形成において重要です。ここでは、実際にホワイト企業に転職するために押さえておくべき3つのコツを紹介します。
コツ1|業界研究し自分に合った分野を見つける
施工管理には、土木工事、電気工事、プラント建設工事、改修工事、設備工事など、多様な分野があり、それぞれ働き方が異なります。自分の生活リズムやキャリアプランに合った分野を選ぶことで、自分にとってホワイトな働き方を実現できる可能性が高まります。
例えば、公共工事やインフラ整備を手がける企業は景気変動の影響が小さい一方で、年度末などに繁忙期が集中し、閑散期とのメリハリが大きい特徴があります。また、高速道路の夜間補修や商業施設の改修工事など、分野によっては深夜作業が避けられないケースもあるため、自分のライフスタイルに合致する分野を慎重に選択することが重要です。
コツ2|実際に働いている方の話を聞いてみる
ホワイト企業への転職を成功させるためには、実際にその企業で働いている方から、職場の内情について話を聞くのが有効です。可能であれば、知り合いや人脈を通じて、現場でのリアルな体験談を聞き出しましょう。
直接社員や元社員から話を聞くことで、企業の労働環境や文化、実際の働き方について本音を知ることが可能です。ネットの情報だけでは見えにくい内部の事情や雰囲気を把握でき、後悔のない転職を実現しやすくなります。
コツ3|関連する資格を取得しておく
施工管理では、資格が実務に直接役立つだけでなく、転職活動においても重要なアピールポイントとなります。資格を取得しておくことで、転職の選択肢が広がり、希望条件に合った企業を見つけやすくなるでしょう。
施工管理経験者も、資格を活用してステップアップを目指すと良いでしょう。施工管理に関連した資格は以下の通りです。
〇施工管理技士
施工管理技士は、建設業法の規定に基づく「施工管理技術検定」の第一次検定と第二次検定の合格者に与えられる国家資格です。資格を取得すれば、建設現場における工事全体の管理を担えるスキルがあることを証明できます。
施工管理技士は、1級と2級にレベルが分かれています。1級を取得すれば、営業所ごとに配置される専任の技術者や、工事現場に配置される主任技術者のほか、一定規模以上の工事で配置が必要な監理技術者になることができ、携われる工事の規模に制限がなくなります。2級を取得すれば、専任の技術者・主任技術者になることが可能です。
〇施工管理技士補
施工管理技士補は、施工管理技士になるための入り口となる資格です。施工管理技術検定の第一次試験に合格すると取得できます。施工管理技士補は、建設業界における技術者不足への対処を目的に、2021年の建設業法改正によって新設されました。1級施工管理技士補を取得すると、監理技術者補佐として業務に携われます。
コツ4|企業や建設現場の規模を確認しておく

企業や工事を担当している現場規模を確認し、慎重に転職先を検討することが重要です。規模が小さい現場が多い場合は、業務負担が少なく、納期が緩やかな場合が多いため、結果的に働きやすい環境が整っていることがあります。
例えば、改修工事やメンテナンスを専門とする企業は、工事の規模が比較的小さいことから、施工管理が担う業務範囲も狭くなるケースも少なくありません。改修工事は住人がいる状態で実施することが多いため、夜遅くまでの作業が避けられるなど、労働時間が安定するというメリットもあります。
大規模な企業は行政や第三者のチェックが入りやすいことから、働き方改革が進んでいる場合も多く、福利厚生も充実している傾向にあります。ただし、大企業は制度面での整備が整っているものの、個別のケアが行き届かないと感じる方がいるのも事実です。
企業規模によってホワイト企業かどうかが決まるわけではありませんが、自分に合った働き方ができる職場を選ぶためにも、企業研究を徹底してみてください。
この記事をお読みの方におすすめの求人
「施工管理で働いているが、働き方を変えたい」「ライフステージの変化に合わせて、ワークライフバランスを見直したい」といった方は、BREXA Engineeringがおすすめです。BREXA Engineeringは施工管理経験者の方をはじめ、未経験者でも安心して働ける環境を整備しています。
施工管理や設計・施工図、プラント施設の維持管理業務など、建設業界に関する幅広い求人を取り扱っています。また、経験者であっても、3~5年目には2級施工管理技士などの資格取得対策や、フルハーネス講習などベテラン講師による中堅技術者向けの研修を用意しています。
「キャリア形成」「適正配属」「社内情報連携」の3つの項目を軸として活動するキャリアサポート課が、面談や社内研修を通じて、一人ひとりがより幸せな未来、充実したキャリアを築くための支援をしています。
まとめ
昨今の建設業界は働き方改革が進んでおり、ホワイトな環境で施工管理の職に就くことは十分できると想定されます。ホワイトな企業であるかは、残業・給料・休日・工期の余裕などから総合的に判断しましょう。サービス残業なく休日をきちんと取り、ワークライフバランスを実現したい方は正社員型派遣での働き方もおすすめです。
技術者派遣を行っているBREXA Engineeringでは、自由で多様な働き方を実現できるよう、さまざまなエリア、仕事内容のプロジェクトのご紹介やキャリアサポートを行っております。
ご興味のある方は、以下から採用ページをご覧ください。