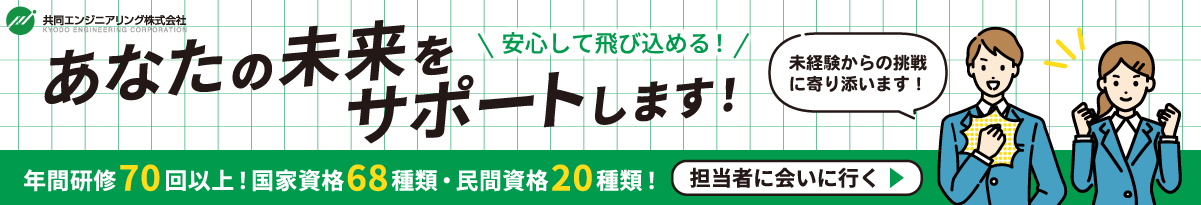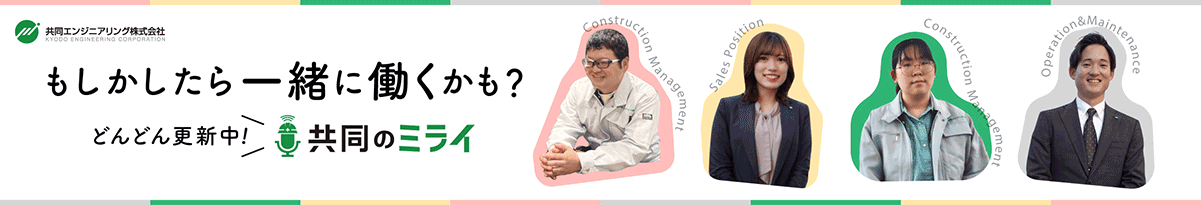目次
建築士の仕事内容
 建築士の仕事は、建築物の設計や工事監理を通じて、安全で快適な建物を作ることにあります。施主との打ち合わせから始まり、設計、工事監理、行政手続きなど、多岐にわたる業務を担当します。ここでは、建築士の具体的な仕事内容について詳しく説明します。
建築士の仕事は、建築物の設計や工事監理を通じて、安全で快適な建物を作ることにあります。施主との打ち合わせから始まり、設計、工事監理、行政手続きなど、多岐にわたる業務を担当します。ここでは、建築士の具体的な仕事内容について詳しく説明します。
ヒアリング
建築士の仕事は、施主とのヒアリングから始まります。建築する建物の目的や施主の希望を正確に把握することが重要です。打ち合わせでは、下記のような点などについて詳細に話し合います。
・建物のデザインやコンセプト
・部屋の数や広さ
・建築に必要な予算
施主の要望を整理し、実現可能なプランを作成するために、建築士は具体的な提案を行います。予算や法規制を考慮しながら、最適なプランを導き出すことが求められます。
設計
設計は、建築する建物の構造や設備、工事方法などを決める工程です。設計には主に下記の3つの分野があります。
・意匠設計:建物の外観や内装のデザインを決定する
・構造設計:建物の耐久性や安全性を確保するため、骨組みを計画する
・設備設計:電気、水道、空調などのインフラを設計する
上記の設計をもとに、工事に必要な設計図や仕様書を作成し、施工業者と共有します。
工事監理
工事が設計通りに進められているかを確認するのも建築士の重要な役割です。工事現場に立ち会い、下記のような点を確認します。
・設計図や仕様書に沿って工事が行われているか
・計画通りに進んでいるか
・鉄筋の数量や配置は適切か
・接合箇所の適切な処理が行われているか
・各種工事が適切に行われているか
これにより、施工の品質を維持し、建築物が設計通りに完成するように管理します。
事務作業
建築士の仕事には、建築に関する各種手続きや契約関連の業務も含まれます。具体的には、下記のような事務作業を行います。
・建設許可や道路使用許可の申請などの行政手続き
・建築主と施工業者の契約書の監修
・契約内容の折衝や調整
・建築物に関する調査や鑑定
建築士の資格別の仕事内容
 建築士は、建築基準法に基づく国家資格で、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類に分かれています。それぞれの資格について、担える仕事内容を紹介します。
建築士は、建築基準法に基づく国家資格で、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類に分かれています。それぞれの資格について、担える仕事内容を紹介します。
一級建築士
一級建築士は、国土交通大臣の認可を受けた資格で、設計・工事監理ができる建物に制限がありません。大規模な建築物の設計に携われるため、幅広い分野で活躍できます。
具体的には、延べ面積が500㎡を超える学校や病院、劇場、公会堂などの公共施設、高層ビル、大型商業施設、マンションの設計・工事監理が可能です。耐震設計や防火対策など、高度な専門知識が求められます。
二級建築士
二級建築士は、都道府県知事の認可を受けた資格で、設計・工事監理ができる建物の規模に制限があります。
具体的には、木造建築では基本的に2~3階建てで延べ面積1,000㎡以下、鉄筋コンクリート造や鉄骨造では延べ面積が30~300㎡以下の建築物が対象となります。また、学校や病院、劇場、百貨店などの公共施設でも、延べ面積が500㎡以下であれば設計・工事監理が可能です。主に住宅設計を中心とした業務に携わるケースが多くなります。
木造建築士
木造建築士は、都道府県知事の認可を受けた資格で、設計・工事監理ができる建築物は木造に限られます。
具体的には、2階建て以下で延べ面積300㎡以内の木造建築物の設計・工事監理が可能です。住宅はもちろん、小規模な店舗や公共施設の設計にも携わることができます。地域密着型の設計事務所や工務店での業務が多い傾向にあります。
建築士の1日の流れ
 建築士の1日は多岐にわたる業務で構成されています。下記は、一般的な建築士の9:00~18:00のスケジュール例です。
建築士の1日は多岐にわたる業務で構成されています。下記は、一般的な建築士の9:00~18:00のスケジュール例です。
・9:00 出社
自宅から自転車や車で事務所に出勤します。出勤後、まずメールを確認し、クライアントや業者からの連絡に対応します。
・10:00 打ち合わせ
クライアントやメーカー、工務店などとの打ち合わせを行います。設計から確認申請まで、さまざまな連携が必要です。
・12:00 昼食・休憩
約1時間の昼食休憩を取ります。スケジュールが立て込んでいる場合は、簡単な食事で済ませることもあります。
・13:00 設計作業
午前中の打ち合わせ内容をもとに、設計図の作成やデザインの検討、修正を行います。設計の変更があれば図面を書き直し、スタッフに模型作成を依頼します。完成した模型をチェックし、必要に応じて修正を加え、完成形に近づけていきます。また、建築雑誌で素材をチェックしたり、対応できる業者を調べたりすることもあります。
・18:00 退勤
1日の業務を終え、帰宅します
このように、建築士の1日は、打ち合わせ、設計作業、修正作業など、多岐にわたる業務で構成されています。日々の業務を通じて、クライアントの要望を形にし、建物を完成させていきます。
建築士の資格を活かせる就職・転職先
建築士の資格を取得すると、建築に関するさまざまな分野で活躍する道が開けます。 ここでは具体的な就職・転職先を4つ取り上げ、それぞれの特徴を解説します。
ハウスメーカー
ハウスメーカーは、住宅の企画・設計・販売を一貫して行う企業であり、多くの建築士が活躍しています。また大手ハウスメーカーでは、すでに確立されたデザインや施工方法をもとに住宅を提供するケースが多いため、ゼロから設計する機会は限られることがありますが、その分、安定した環境で設計業務に携われる点が魅力といえるでしょう。
勤務形態は平日休みが多く、顧客対応のために土日が出勤日となることもあります。営業職との連携が求められる場面も多く、コミュニケーション能力が求められる職場です。
設計事務所
設計事務所は、住宅だけでなく商業施設や公共建築など、多様な建物の設計を手がけます。建物の企画から設計、監理までを担当し、自由度の高いデザインを追求できるといえるでしょう。個性を活かした設計に関心がある建築士にとっては、魅力的な選択肢です。
特に、独立を目指す建築士にとっては、設計事務所での経験を大いに活かせます。業務は多忙になりがちですが、実績を積むことで将来的に独立しやすくなる点も考慮したいところです。
建築会社・ゼネコン
建築会社やゼネコンには、営業、設計、施工管理、研究開発など幅広い職種があります。大規模なプロジェクトに携われるため、建築士としてスケールの大きな仕事をしたい場合には適した環境といえるでしょう。
また、一級建築施工管理技士や建設業経理士などの資格を持っていると、就職・転職の際に有利に働きます。例えば、施工管理の仕事では、現場での指揮や安全管理なども求められます。建築士の知識を活かしながらプロジェクトを進めることができるのは大きなアドバンテージです。
建設業経理士は建設業特有の会計処理のプロフェッショナルとして、建設会社に就職する際に役立ちます。実務経験なしでも、資格保有者は評価される可能性があるでしょう。
公務員
公務員として地方自治体の建築部門に勤める道もあります。この場合、民間企業とは異なり、主に既存の建築物の維持管理や耐震補強、都市計画の策定などが主な業務です。新たな建築を設計する機会は限られますが、社会の基盤を支える重要な役割を担う醍醐味があります。
安定した雇用環境が魅力であり、ワークライフバランスを重視する人に向いています。ただし、公務員試験に合格する必要があるため、公務員を目指す場合はしっかり対策しましょう。
まとめ
建築士は、建築物の設計や工事監理を通じて、安全で快適な建物を生み出す役割を担います。施主とのヒアリングから設計、工事監理、行政手続きまで幅広い業務をこなし、専門知識と実務経験を活かして建築プロジェクトを推進します。
資格によって設計・監理できる建築物の規模が異なり、キャリアパスも多岐にわたります。設計事務所やハウスメーカー、ゼネコン、公務員など、就職先の選択肢も豊富です。自身の目指す働き方に合った環境を見つけ、理想のキャリアを築いていきましょう。
建築士や建設業界の仕事に興味があるものの、「未経験から本当に始められるのか……」と不安に感じていませんか。そんな方には、未経験から施工管理やCADオペレーターを目指せるBREXA Engineeringがおすすめです。
BREXA Engineeringでは、充実した研修と資格取得支援制度が整っており、未経験からでも安心してスキルを習得できます。さらに、基本的に週休2日制でワークライフバランスを確保できる環境です。建築士を目指すキャリアの第一歩目として、ぜひ下記から詳細をチェックしてみてください。
>>BREXA Engineeringの未経験者向けページはこちら