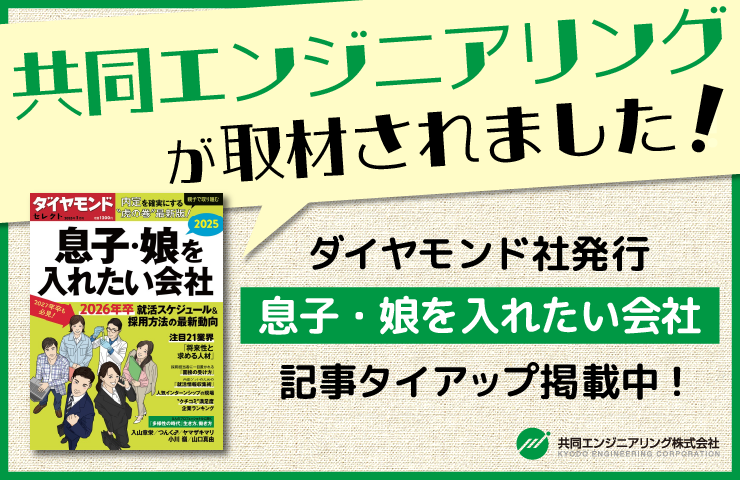世界規模の最先端の半導体工場に挑む!現場から社内まで多方面へ貢献
下田 剛暉さん
飲食店店長から超巨大機器の設備施工管理へ。メイン担当者として、現場の管理から施工図・計画書作成など多岐にわたり活躍中。
入社年:2020年中途入社
現在の業務:設備施工管理(現場のメイン担当者) 客先・業者との打ち合わせ、施工図作成、各種工事の計画書・手順書の作成
休日の過ごし方:ドライブ、旅行、料理
過去の現場経歴:
2020/10~
半導体工場にて大型機器の定期整備・補修工事(広島)
2023/10~
岡山の新築工場にて搬入・据付工事(岡山)
2024/10~
半導体工場にてコンプレッサーの更新工事(広島)
飲食店店長から施工管理へ。将来を見据えた「手に職」への転身
――建設業界に目を向けたきっかけを聞かせてください。
高校時代から勤めていたアルバイト先の飲食店に、高校卒業後はそのまま正社員として就職しました。アルバイト期間も含めると6年間就業し、副店長から店長へと順調にキャリアを築きました。やりがいを感じる一方で、将来を見据えたときに「より専門性の高い技術を身につけて手に職をつけたい」という気持ちが強くなりました。施工管理であれば、飲食業で培ったコミュニケーション力やマネジメント経験を活かして、技術職としてスキルアップできる最適な道だと考え、転職を決意しました。
――共同エンジニアリングを選んだ決め手を教えてください。
同業他社からも内定をいただきましたが、研修制度の充実度、給与体系、グループの規模感など総合的に検討しました。中でも、未経験者でも基礎から学べる研修制度が整っていたことが大きな魅力でした。また、選考中に感じた丁寧でスピーディーな対応にも安心感があり、「ここでなら頑張れそうだ」と思い、入社を決めました。

目の前に広がるのは規格外の超巨大機器。挑戦の連続が確かな技術と自信に。
――最初に配属された半導体工場の現場について教えてください。
広島の半導体工場に配属され、大型機器の定期整備と補修工事に携わりました。中でも印象に残っているのは、住宅用エアコンの約2000倍に相当する能力をもつ、2000冷凍トン級のターボ冷凍機のメンテナンスです。機器1台の重量は30〜40トンと規格外で、まずはそのスケールの大きさに驚きました。
作業では、まず冷媒を全て抜き取り、トラックほどの大きさの部品をチェーンブロックやウィンチを使って一つひとつ分解して清掃します。壊れている部品はその都度交換して正常に動作するよう整備します。お客様と相談しながら、60台以上のメンテナンス計画を立て、順に対応していきました。

※イメージ図 ターボ冷凍機は、大型の建物を冷やすためのいわば“超巨大エアコン”。定期的な点検・清掃・部品交換を行うことで、冷却効率を保ち、エネルギーのムダを防ぐことができます。
――未経験からのスタートで、どのような壁に直面しましたか。
専門用語の多さと作業工程の複雑さは大きな壁になりました。
しかし、わからないことをそのままにせず、「メモを取ってすぐに先輩に確認する」「自分でも調べて知識をつけていく」といった行動を徹底しました。
未経験だったので、とにかくお客様や現場の所長に安心して任せてもらえるよう、毎日が必死でした。その分、学びや経験が多く、良いスタートダッシュを切れることができました。
――岡山の新築工事での経験が、キャリアの転機になったそうですね。
2現場目では岡山に異動し、半導体工場の新築工事で機械設備の搬入・据え付けのメイン担当者になりました。
3階建ての工場に、300キロある空調機器の据え付けが必要で、現場所長や設計担当のベテランも「設備で一番難しい作業になる」と頭を悩ませていました。何度も計画書を提出し、寸法的に入らない機器については建築担当者と交渉して工事の順序を調整しました。関わる人数が非常に多かったので、毎日現場を駆け回るほど忙しい日々でした。
周りの方々の協力のおかげもあり、計画が通って無事に搬入据付けができた瞬間は達成感で胸がいっぱいでした。自分が立てた計画が成功できたという事実が何よりの自信になりましたし、今の自分を支える大きな経験になっています。
――現在は、現場業務から図面作成まで幅広くスキルアップされています。
広島に戻り、半導体工場で大型コンプレッサー(圧縮機)の更新工事に携わっています。老朽化したコンプレッサーを新しい設備に入れ替える工事です。現場での管理業務に加えて、施工図や各種計画書、手順書の作成も任されるようになりました。
Rebro CADを使って配管や機器の配置を自分で考えながら、配置図・配管図・ダクト図を一から作成し、それをもとに職人さんやお客様、他業者と打ち合わせを行い、施工へとつなげています。
自分が描いた図面が形になっていく、というまさに建設の醍醐味を肌で感じています。
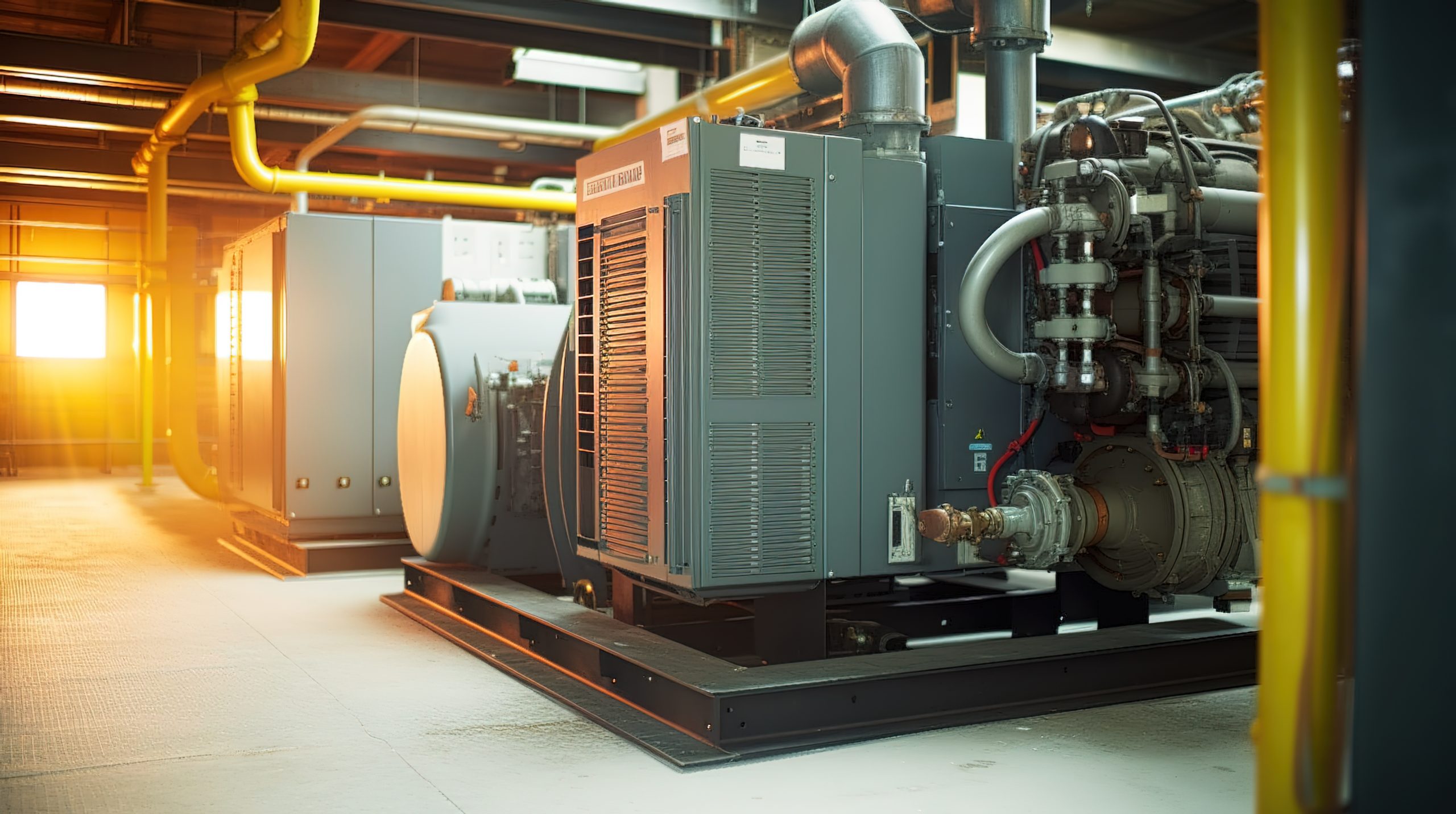 ※イメージ図 コンプレッサーとは、空気やガスを圧縮して圧力を高める装置。圧縮した空気を使って機械や工具を動かすことや制御することができます。下田さんが更新するコンプレッサーは総重量が9tという巨大設備。
※イメージ図 コンプレッサーとは、空気やガスを圧縮して圧力を高める装置。圧縮した空気を使って機械や工具を動かすことや制御することができます。下田さんが更新するコンプレッサーは総重量が9tという巨大設備。
――施工管理としてどのような強みが身につきましたか。今後の展望はありますか。
大型機器の搬入や据え付けといった施工分野における知識やノウハウは、自分の中で着実に蓄積されてきていると感じています。
その背景には、広島・岡山といった異なる現場で多くの経験を積めたことが大きいですね。環境が違うことで対応の仕方も変わり、知識が偏ることなく、工程や段取りの組み立て、安全面への配慮など、俯瞰して見る力が身についたと感じています。
それに私自身、転勤や出張は抵抗なく、仕事では経験を積めて、休日は知らない土地へ観光ができるとむしろ仕事の楽しみの一つになっています。
今後も様々な現場を経験して、ゆくゆくはお施主さんやチームの仲間から「安心して任せられる」「また一緒に仕事をしたい」と思ってもらえるような信頼関係を築ける技術者になりたいです。

“人に勧めたい会社”。会社の制度を元にさらなる飛躍へ
――社内活動にも積極的に貢献されています。社内活動や共同エンジニアリングの魅力について教えてください。
以前、社内報に自身の現場の経験談を投稿しました。もともと社内報は更新されるたびに読んでいて、中には技術社員の投稿で”現場の専門用語集”をつくるという企画があって私自身楽しみながら勉強になっていたんです。私の経験も誰かの参考になればという思いでした。共同エンジニアリングの魅力は、そういった社内のつながりがあることに加えて、スキルアップのための環境がしっかり整っているところだと思います。
資格取得支援講座が豊富に用意されていて、私も直近で講座を受けながら一級管工事施工管理技士の一次試験を受検し無事合格点に達しました。
さらに、自分の頑張りや貢献が人事評価にもきちんと反映される人事考課制度があるので、モチベーションを保ちながら成長していける会社だと感じています。
――ご紹介で入社されたご友人もいらっしゃるそうですね。
地元の友人が、かつての私と同じように「手に職をつけたい」と話していたんです。そこで、自身の体験談を交えながら共同エンジニアリングを紹介しました。未経験者への研修制度やキャリアアップの充実さなど魅力が伝わり、実際に入社することになったんです。奇遇なことに、今は同じ現場に配属されていて時折現地で顔を合わせることもあります。紹介してから3年半以上経ちますが、今も現場で頑張っている姿を見ると、うれしさと同時に自分ももっと頑張ろうと刺激になっています。
――建設業界を目指す方へメッセージをお願いします。
建設業界は、施工管理や職人など、多岐にわたる仕事がありますが、全体として人手不足や世代交代が進んでいます。その分、現場全体で若い世代を育てようという雰囲気があり、道は広く開けていると感じます。
もちろん、専門性が高い職業であり、施工管理の立場になれば責任も伴います。時には諦めそうになることもあるかもしれませんが、そこで粘り強く取り組めば必ず成果は返ってきます。自分の力を信じて、一歩踏み出してほしいと願っています。
※2025年11月4日時点の記事です