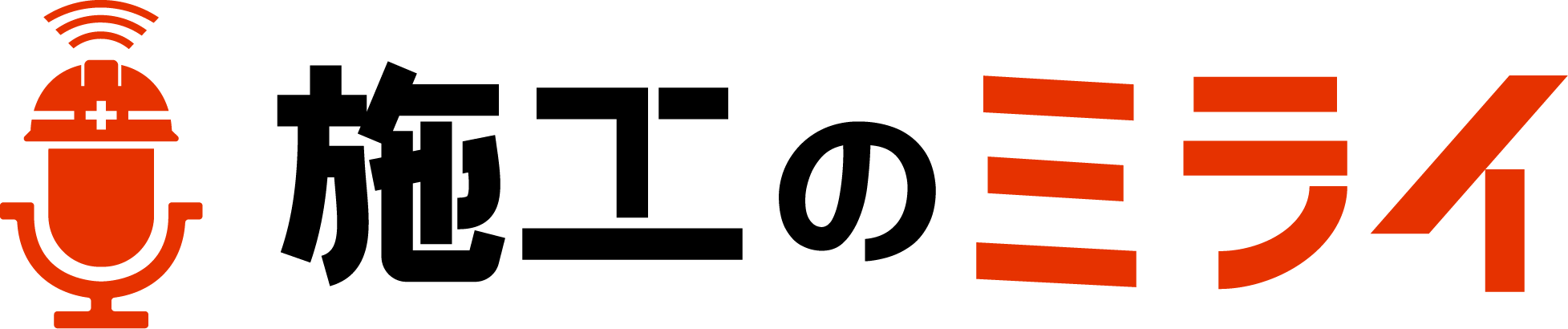一から建物が立ち上がる瞬間に立ち会い、夢を現実に変えていく
山根康祈さん
高専の建築学科を卒業後、青森・宮城・山形の現場で施工管理業務を経験。新築からリフォームまで幅広く携わる技術者を目指して奮闘中
入社年:2023年4月新卒
現在の業務:施工管理 現場内での施工写真や施工記録の管理作業、材料の手配作業など
休日の過ごし方:ドラマ鑑賞、近所の飲食店巡り、読書
過去の現場経歴:
2023年5月〜 再処理施設における配管補強工事の施工管理(青森)
2024年7月〜 マンション新築工事の施工管理(宮城)
2024年10月〜 プリンター関連機器製造工場の新築工事における施工管理(山形)
幅広い選択肢が用意されている技術者派遣の働き方を選択
――建築学科を志望したきっかけと、卒業後に共同エンジニアリングを選んだ理由を教えてください。
幼少期から、建造物や工事現場を見るのが好きでした。物心ついてから、特に影響を受けたのは、かつてテレビで放送されていた「某・劇的リフォーム番組」です。匠の技と工夫による魔法のようなリノベーションを見て、建築の魅力に引き込まれました。
建築に携われる仕事を志し、高専の建築学科に進学。最初はリフォームのような住空間の改修に興味があったのですが、学びを深めるなかで「新築現場での施工管理」に興味が移っていきました。建物を一から作り上げる過程に、より強い魅力を感じたからです。
就職活動では、施工管理者に職種を絞り、建設系企業を30社ほど検討しました。その中で共同エンジニアリングを選んだ決め手は、施工管理以外にも設備メンテナンスなど、幅広く業務を経験できる点に魅力を感じたからです。
さまざまなジャンルと職種の選択肢が用意されている共同エンジニアリングなら、より自分に合った働き方が見つけられると思ったのです。また、1つの会社で1つの現場を極めるよりも、複数の現場を経験できるほうがより成長できるのではとも考えていました。
「大きな建物をつくりたい」学生時代の夢を、地元の東方エリアで叶える

――最初に配属されたのは青森県の現場だったのですね。
青森県にある原子力関係の施設で配管補強工事の施工管理を担当しました。既設の配管を補強する工事で、6名ほどのチームで動いていました。新人の私に対しても職人の皆さんがとても優しく、丁寧に指導してくださいました。良好な関係を築けるよう、職人さんが疑問に感じていることや困っていることにしっかり耳を傾け、その都度先輩に確認するよう心がけていました。
同じ東北でも、地元の宮城に比べて青森は雪が非常に多く、冬の厳しさには驚きました。朝起きると一面の銀世界。まず、車までの通路を確保するところから始まり、駐車場の雪かきも日課でした。正直「本格的な雪国は大変なのか」と思ったこともありましたが、この経験を通じて、どんな環境でもやっていけるという自信がつきました。都会に比べると静かですが、その分、のんびり穏やかに過ごせるという良さも感じました。
1年間青森で基礎を身につけながら、「2級建築施工管理技士補」の資格を取得しました。そこで「建築の現場も経験したい」と会社に伝えたところ、地元の宮城県でのマンションの新築工事に配属となり、続いて山形県で工場の新築工事に携わって今に至ります。
――現在担当されている現場について詳しく教えてください。
プリンター関係の機器製造工場の新築工事現場で施工管理を担当しています。ピーク時には約200名の職人さんが作業する大規模な現場で、私はその中の1チーム(約10名)を担当しています。
まっさらな敷地に少しずつ建物が立ち上がっていき、壁や梁が組み上がって建物らしくなっていくのを見るのが楽しいです。学生時代に思い描いていた「大きい建物を作りたい」という夢が、まさに実現している感覚があります。
現在は建築工事がほぼ完了し、内装や設備の取り付けといった仕上げ段階に入っています。完成まではあと3か月ほどの予定です。
現場ごとの特性や工法を体験できることも魅力のひとつ
――共同エンジニアリングの教育・研修制度、キャリアサポートについて教えてください。
入社してすぐにフルハーネス型墜落制止用器具特別教育と職長教育を受講しました。また、青森で取得した「建築施工管理技士補」についても、働きながらの勉強は大変でしたが、2~3週間に一度の頻度で資格支援研修があり、大きな助けになりました。基本的に定時で帰れていたので、帰宅後勉強時間を確保することはできていたのですが、一人で教科書を読んでいるだけではなかなか頭に入りませんでした。その中で、研修で講師の方の説明を聞くことで、理解が進みました。
キャリアパスについても、定期的にキャリアサポート課と面談の機会があり、今後やりたいことを話すと、それに必要な資格やキャリアの積み方などのアドバイスをもらえます。資格勉強も未来のキャリアのためと思うと、明確な目標となって頑張れます。配属先も、希望や将来のビジョンを考慮して決定されるため、非常に心強いと感じています。
――現場が変わる「技術者派遣」の働き方の魅力と大変さはどのようなものですか?
私の場合、1年に1回の頻度で異動を経験してきました。都度新しいことを覚えるのは大変ではありますが、現場ごとの特性や工法を見ることができて、とても楽しいです。
プラント工事から建築工事へと分野が変わったことで、知識とスキルの幅も広がりました。1つの会社では経験できない幅広い現場を経験できるのは、共同エンジニアリングならではの魅力だと思います。
また、将来的には東北以外の都市部の現場にもチャレンジしてみたいと考えています。そのためにも、まずは慣れ親しんだ地域で力をつけたいです。
――今後のキャリアビジョンを教えてください。
現状はまだ一人で現場を回れるレベルではありませんが、今後は一人で担当できる範囲を広げていきたいです。後輩が入ってきたら、頼ってもらえるような存在になりたいと思っています。
新築工事の面白さを実感する一方で、もともと興味のあったリフォーム工事にもいつか挑戦してみたいという思いもあります。少しずつでも新しいことにチャレンジすることで、自分のスキルや知識が広がっていくと実感しています。2級建築施工管理技士の二次試験も、条件となる経験年数を積んだらすぐに受験する予定です。
――建築学科の学生や就職を検討している方にアドバイスをお願いします。
たくさんの建物を見にいくことをおすすめします。私の学生時代はコロナ禍の影響で見学の機会が限られていましたが、実物を見ておくと、現場に出たときに「この構造、あのとき見た建物に似ている」といった連想がしやすく、理解も深まります。
技術者派遣という働き方は、幅広い経験を積めて自分の成長につながる働き方だと思います。共同エンジニアリングなら、そうした挑戦をサポートしてくれる環境が整っていると感じています。
※2025年10月28日時点の記事です