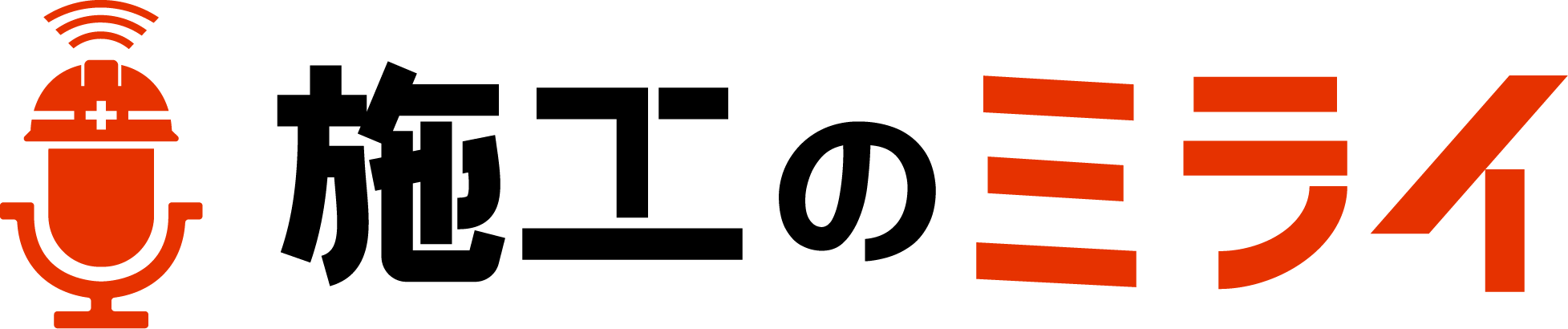「人のためになる仕事」を軸に新たなキャリアスタート
――建設業界への転職を決めた経緯と、共同エンジニアリングを選んだ理由を教えてください。
海上自衛隊では約9年間、船の運用や修理などに携わってきました。「人の役に立ちたい」という気持ちから入隊したのですが、より広い分野で社会に貢献したいという想いが芽生え、建設業界への転職を考えるようになりました。
もともと自衛隊の業務で業者の方と図面を見ながら現場を回る機会があり、その経験から施工管理の仕事にも親しみを感じていました。なかでも海上プラントや発電所といった大規模インフラに関心があり、プラント事業で飛躍している共同エンジニアリングと出会いました。
――入社の決め手は何だったのでしょうか。
一番の決め手は、私が希望していたプラント関係の仕事に携われることでした。また、選考過程で建設業界未経験であることを相談した際、海上自衛隊での船の修理経験を評価していただけたことも大きかったです。完全にゼロからのスタートではないという評価をもらえたことで、安心して入社を決めることができました。
――最初に配属された現場はどのようなところでしたか。
最初に配属されたのは大手プラントエンジニアリングの原子力施設内の配管工事を行う大規模現場でした。放射線管理の厳しい現場で、多くの業者が関わる中、私は施工管理として他業者との調整をしながら配管や穴埋め工事を担当しました。
長年現場で働く職人の方々は知識が非常に豊富で、毎日が学びの連続でした。施工管理の基礎は、この現場での2年間で身につけられたと思います。
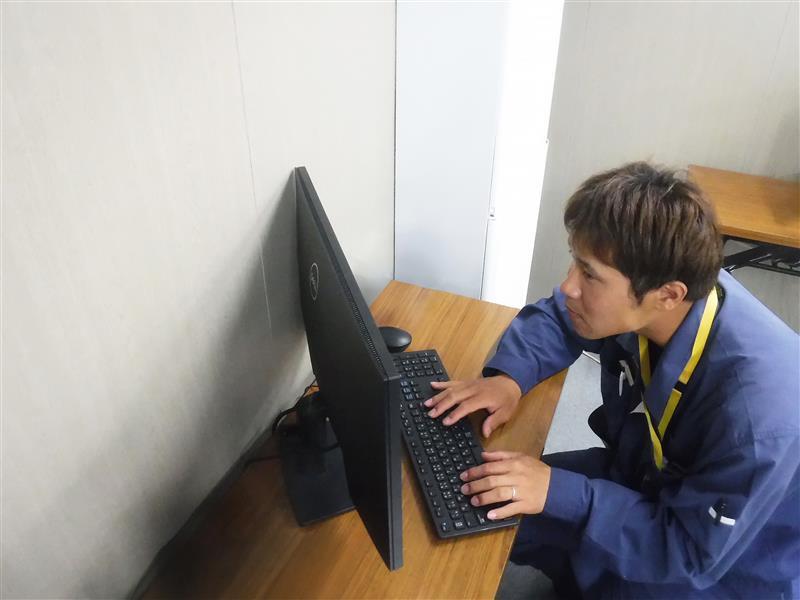
配管工事から電気工事へ 青森で広がる専門性
――現在の具体的な業務内容を教えてください。
現在は同じ施設内で、警備設備の電気工事に携わっています。防犯カメラやセンサーの取り付け工事の施工管理です。原子力施設という性質上、テロへの安全対策や技術不正利用防止が重視されており、セキュリティ設備の増設が求められています。
前回の配管工事とは異なり、電気工事は配線関係の図面が中心になるので最初は難しく感じました。施工管理は私を含めて2~3名、業者さんは5名前後のチームで動いています。
業務の中で特に意識しているのは、電気工事の安全性です。配線ミスは事故につながる可能性もあるので、細かく確認するようにしています。また、センサーやカメラが正常に動作していないと設備が意味をなさないので、配線に問題がないか、センサーが反応するかなど、一つひとつの確認を徹底しています。
――配管工事から電気工事への転換で、やりがいの違いはありますか。
やりがいを感じるのは、防犯対策として長期間使われ続ける設備を完成させられることです。カメラが正常に映り、センサーが反応したときの達成感は、配管工事とはまた違った喜びがあります。配管工事では、一から作り上げて、そこに蒸気や水道が通った瞬間の達成感がありました。電気工事では、緊張感のある緻密な過程を乗り越えて、ようやく完成したという安堵感が特徴的です。
――青森配属の経緯について教えてください。
実は青森には縁があったのです。海上自衛隊時代に青森に勤務していたことがあり、妻も青森出身です。家族のことを考えて、転職するなら青森でと決めていました。今の現場は基本的に土日祝日休みなので、家族や自分の時間も確保できており、ワークライフバランスは良好だと感じています。希望していた地域で、理想の働き方ができていることが長期就業の決め手となっています。
――青森での生活や働き方で、魅力や特徴的な点はありますか。
都心にはない大規模プラントなど地方ならではの現場に携われることが魅力です。特に、最初に配属された原子力施設では、他のプラントと共通するスキルに加えて、極めて高い安全性の確保や厳格な規制順守、さらに原子力・放射線に関する専門知識など、多方面にわたる学びの機会に恵まれました。
環境面でも、冬は現場での除雪作業が欠かせませんが、春から秋はさわやかで過ごしやすい気候の中、大自然の中でのびのびと仕事ができています。
特徴的な点では、最初は方言に驚きました。私は山形出身なので「方言で苦労はないかな」と考えていたのですが、青森の方言は想像以上に手ごわく、特に年配の職人さんの話は1割も理解できないこともありました。同じ地方出身の業者さんに通訳してもらうこともあったほどですが、今はだいぶ慣れてきました。
充実のサポート体制と成長 青森のエネルギー分野でさらなる活躍を
――共同エンジニアリングのサポート体制について教えてください。
資格支援研修制度がとても充実しています。第二種電気工事士の資格を取得する際、土曜日や日曜日に資格支援講座が開催され、筆記試験と実技試験の両方をサポートしてもらいました。施工管理技士以外の資格も支援してくれるため、さまざまな資格に挑戦しやすく、とてもありがたいです。
当初は電気の知識がゼロの状態だったので自分でも勉強する必要があり、平日は30分程度自主勉強を続けていました。外作業で体力的に疲れている中での勉強は大変でしたが、定期的に開催される会社の資格支援講座があったからこそ、自主勉強と講座を組み合わせて効率的に学習を進めることができました。
――営業担当者のサポートはいかがですか。
営業担当や事務の方の対応も至れり尽くせりで、配属先についても親身になって考えてくれます。現場の継続確認や、新しい現場の提案など、こちらの希望に丁寧に応えてくれます。
共同エンジニアリングの強みは、青森にいてもさまざまな分野に挑戦できることです。私も、配管工事から電気工事へと分野が変わったことで、新しい知識やスキルを身につけることができました。1つの会社では経験できない幅広い現場を経験できるのは、東北エリアをはじめ全国でシェアがある共同エンジニアリングならではの魅力だと思います。
――今後のキャリアビジョンを教えてください。
4年目を迎えた今は、引き続き現場での知識を増やし、信頼される施工管理技術者として成長していくことが当面の目標です。
そのためにもまずは、電気工事施工管理技士の資格に再挑戦する予定です。前回は1問足りずに不合格でしたが、電気の仕事が楽しく、自分に向いていると感じているので、今後も電気関係の資格取得を中心に専門性を高めていきたいと考えています。
また、太陽光発電にも興味があります。青森県内では原子力発電に限らず、風力や太陽光発電など再生可能エネルギーの取り組みが進んでいるので、ゆくゆくは新しいエネルギー分野での経験も積んでみたいです。
※2025年7月25日時点の記事です