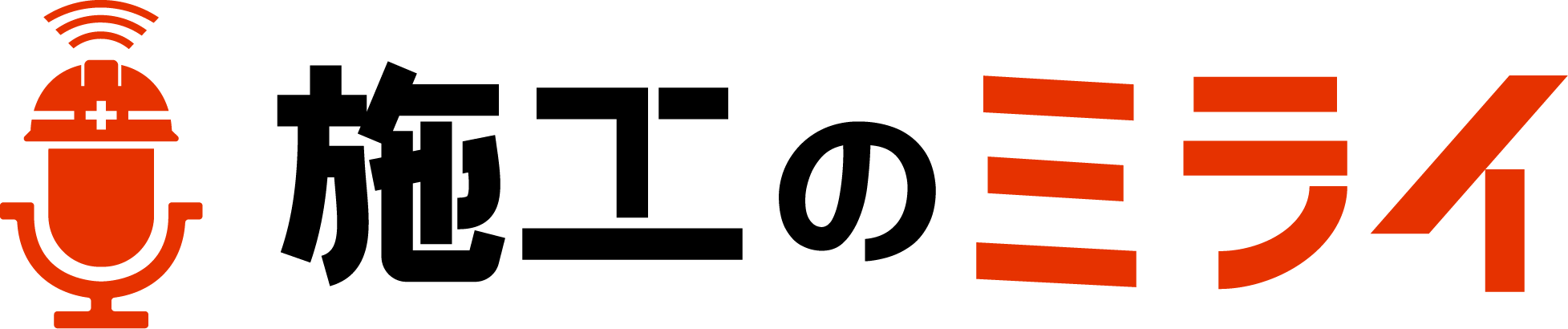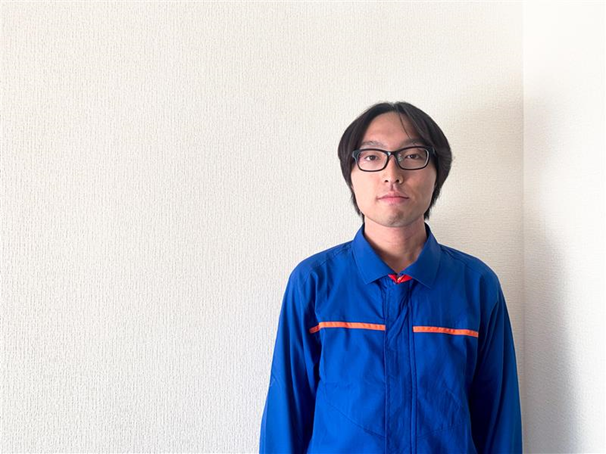お客様の希望を、職人さんと一緒に叶える「架け橋」のような仕事
――学生時代から就職に至るまでの経緯を教えてください。
大学では、経済学を専攻しサークル活動は軽音楽部に所属。学校の創立記念イベントの運営委員を務めるなど、人との関わりが多い学生生活を送りました。
就職活動では、そうした「人と関わる仕事」を軸に職種を探していた中で、施工管理者という職種を知りました。
お客様側からの「こういうものを作ってほしい」という依頼を、職人さんに作業してもらって実際に形にしていく、その受け渡しの部分に興味を持ちました。お客様の希望を叶える、いわば「架け橋」のような役割に魅力を感じ、入社を決めました。
知識ゼロの新人時代から、関係各所の調整を任されるまで
――現在の業務内容と、入社後の知識・スキル習得プロセスについて教えてください。
現在は、プラント施工管理者として、大手石油会社系列の化学メーカーで、ポリエチレンを作っている工場の既存設備の保全メンテナンスをしています。現場全体では職人さんが150名程度、施工管理者が50〜60名程度常駐している大規模な現場です。
入社当初は、先輩から「知識がつくと現場が楽しくなるよ」と言われてもピンと来ませんでした。そもそも、打ち合わせでみんなが話している内容がまったく理解できないのです。建設用語はもちろん、職人さんが使っている工具の名前すらわかりませんでした。職人さんに「“メガネ”取って」と言われて、自分がかけている眼鏡を外しそうになったこともあります。配管やボルトを締めるための「“メガネレンチ”を取ってほしい」という意味だったのですが、一事が万事、そのような調子でした。
そんな中でも、職人の方々は怒ったりせず、逐一親切に教えてくれました。だんだん覚えてくると「おー、わかってきたね」とニコニコと見守ってくださり、その優しさに支えられながら、知識を積み重ねてきました。
――キャリアの最初は新設工事の現場にいたと聞いています。今の既存設備の保全業務との違いはありますか。
新設工事と既存設備の保全では、仕事の進め方が大きく違います。新設工事の場合は、何もないところにどんどん新しいものを建てていくので、段取りに比較的自由度があります。しかし、保全業務では、既に動いている機械や設備を一度止めなければならない場合があり、生産との兼ね合いを常に考慮しなければなりません。
仮に、調子が悪くなった設備があった場合、今機械を止められるのか、2か月先の定期停止のタイミングまで待つのかといった判断が必要になります。突発的な修理もありますし、計画的に年1回行うメンテナンスもあります。止めなくても直せるものは稼働中に行いますが、停止が必要な場合は生産部門と綿密な調整が必要で、こうした部分が新設工事では経験しなかった新たな挑戦です。
――日々の業務で工夫している点を教えてください。
業務で一番工夫しているのは、関係各所との調整です。作業する側は人員や時間の制約があり、生産側は稼働を止めたくないという事情があります。その中で、いつまでに何をする必要があるのか、職人さんたちにリミットをしっかり伝えて、できるかできないかの返事をもらいます。できない場合は応急処置で対応するか次の機会まで待つか、といった判断が必要です。
6年目になって一番成長したと感じるのは、この調整能力です。最初の頃と比べて、関係する部署や会社との折り合いをつけて、みんなの希望と制約のバランスを取ることができるようになりました。これは、がむしゃらに取り組んだ姿勢を評価してもらい、「頑張って動いてくれる」という信頼関係を築けたからだと思います。まだベテランの方のように、一発で的確な見立てはできませんが、「次はうまく調整します」という姿勢を見せることで、周囲の信頼を得られるようになりました。

仕事のやりがいと充実した資格サポートが支える長期キャリア
――仕事を通じて最もやりがいを感じる瞬間を教えてください。
4年間関わった新設設備のプロジェクトが完遂したときです。現場での工事期間は2年半ほどでしたが、その前の検討期間も含めると全体で4年という長期プロジェクトでした。
建屋の建設から機器・配管・電気の設置までが終わり、いざ稼働させてみると不具合で止まってしまうこともありました。その度に全員で原因を探し、対応策を練る日々が続きました。協力して問題を解決していく過程は、大変でしたがやりがいもありました。苦労の末に設備が正常に稼働したときの達成感は本当に大きく、4年間の苦労が全部報われたような感動がありました。
しんどいときもありますが、達成感があるというのが施工管理の魅力だと思います。知識がついてくると、現場で起きていることの背景や意味がわかるようになって、単純に作業を管理するだけでなく、全体の流れを把握して先を見据えた判断ができるようになります。そういった成長が実感できる瞬間も大きなやりがいのひとつです。
――仕事で大変さを感じるとき、乗り越えるために心がけていることを教えてください。
何か失敗したときは、しっかり反省しますが、引きずらないことを心がけています。現場でお世話になった方から、「1回目のミスは誰にでもある。同じミスを繰り返さなければよいだけ」と教えてもらい今でもこの考え方は大切にしています。
そして、困ったときは一人で抱え込まず、営業担当に相談しています。丁寧に話を聞いてくれますし、具体的なアドバイスをくれます。こうした一人ひとりに寄り添ったサポート体制も前向きに働ける理由の一つです。
――共同エンジニアリングで働く魅力について、求職者の方に向けてメッセージをお願いします。
資格取得や講座のサポートが充実している点は大きな魅力です。私も、安全に関わる特別教育(フルハーネス型墜落制止用器具や酸素欠乏・硫化水素危険作業など)は、会社のサポートで履修しました。今後は、施工管理技士資格の取得を検討しているので、定期的に開催される資格支援研修も積極的に活用していきたいです。
また、さまざまな現場を経験できることの価値も大きいと思います。私も化学プラントから製薬工場まで、異なる現場で働くことで、幅広い知識と経験を身につけることができました。
施工管理は、人と接するのが好きな方や調整業務に興味がある方には非常に向いている仕事です。最初はわからないことばかりですが、現場で経験を重ねることで必ず成長できます。そして、プロジェクトが完成したときの達成感は格別です。ものづくりの現場に関わりたい方に、ぜひおすすめしたいです。
※2025年7月16日時点の記事です